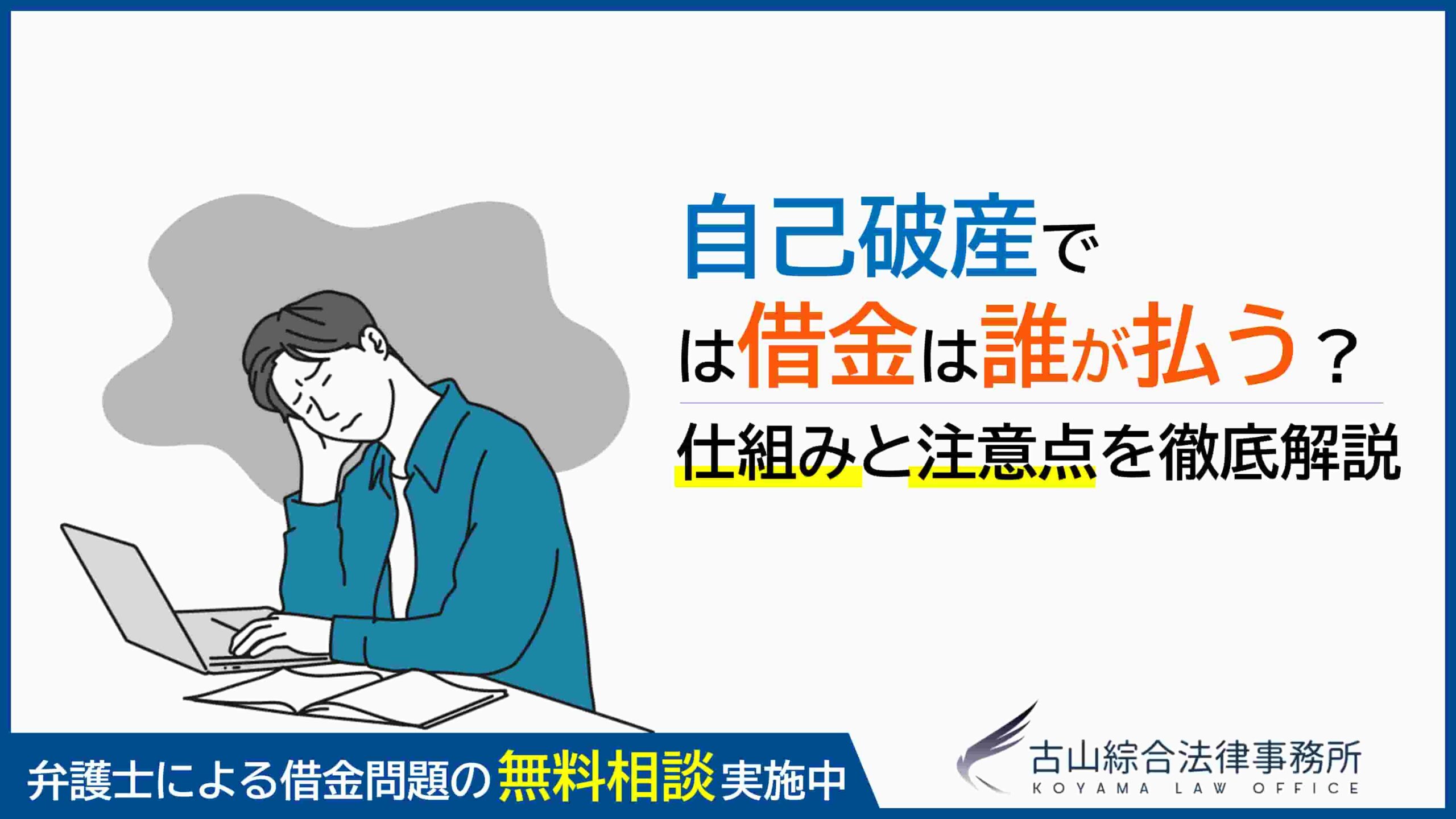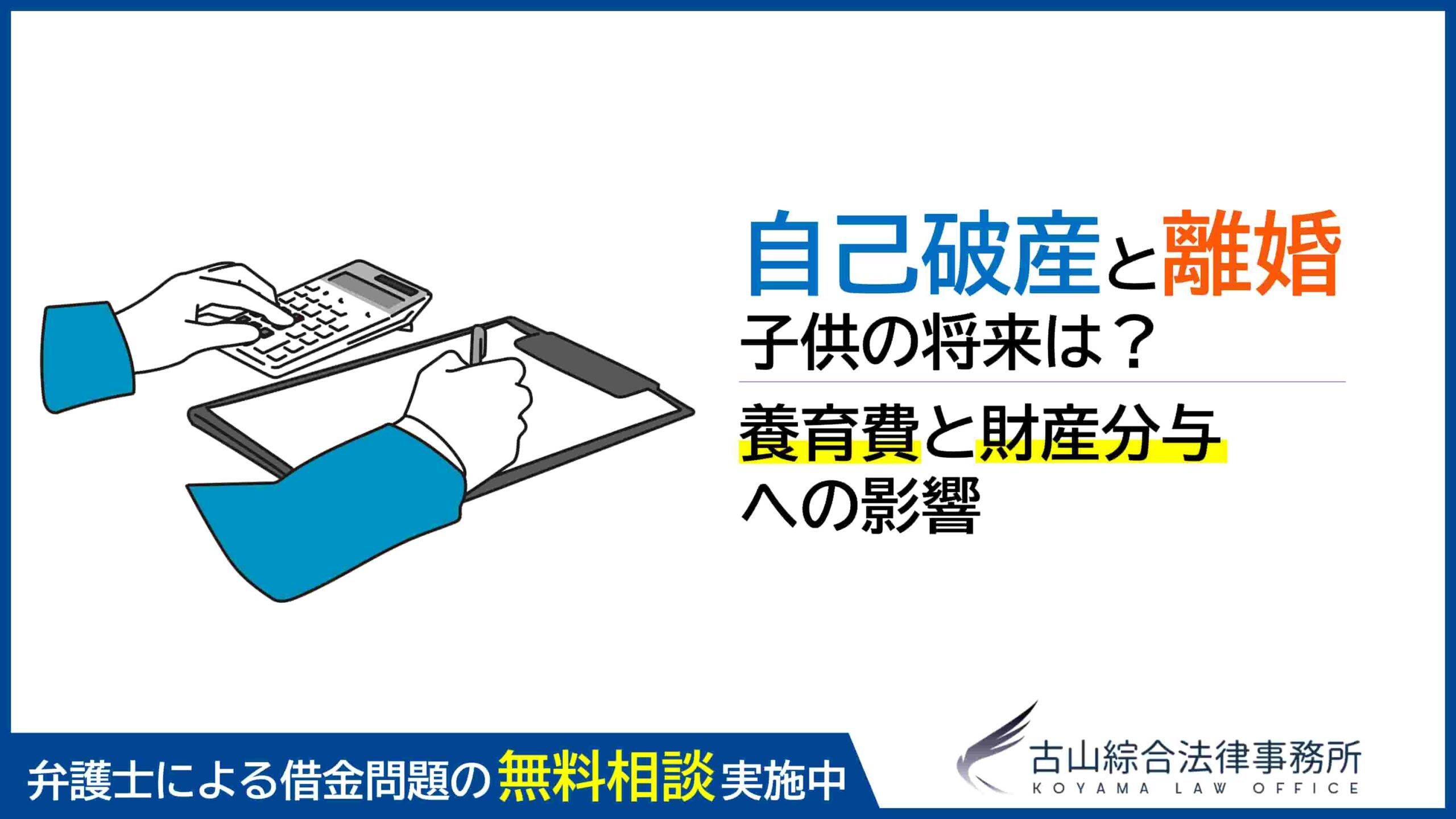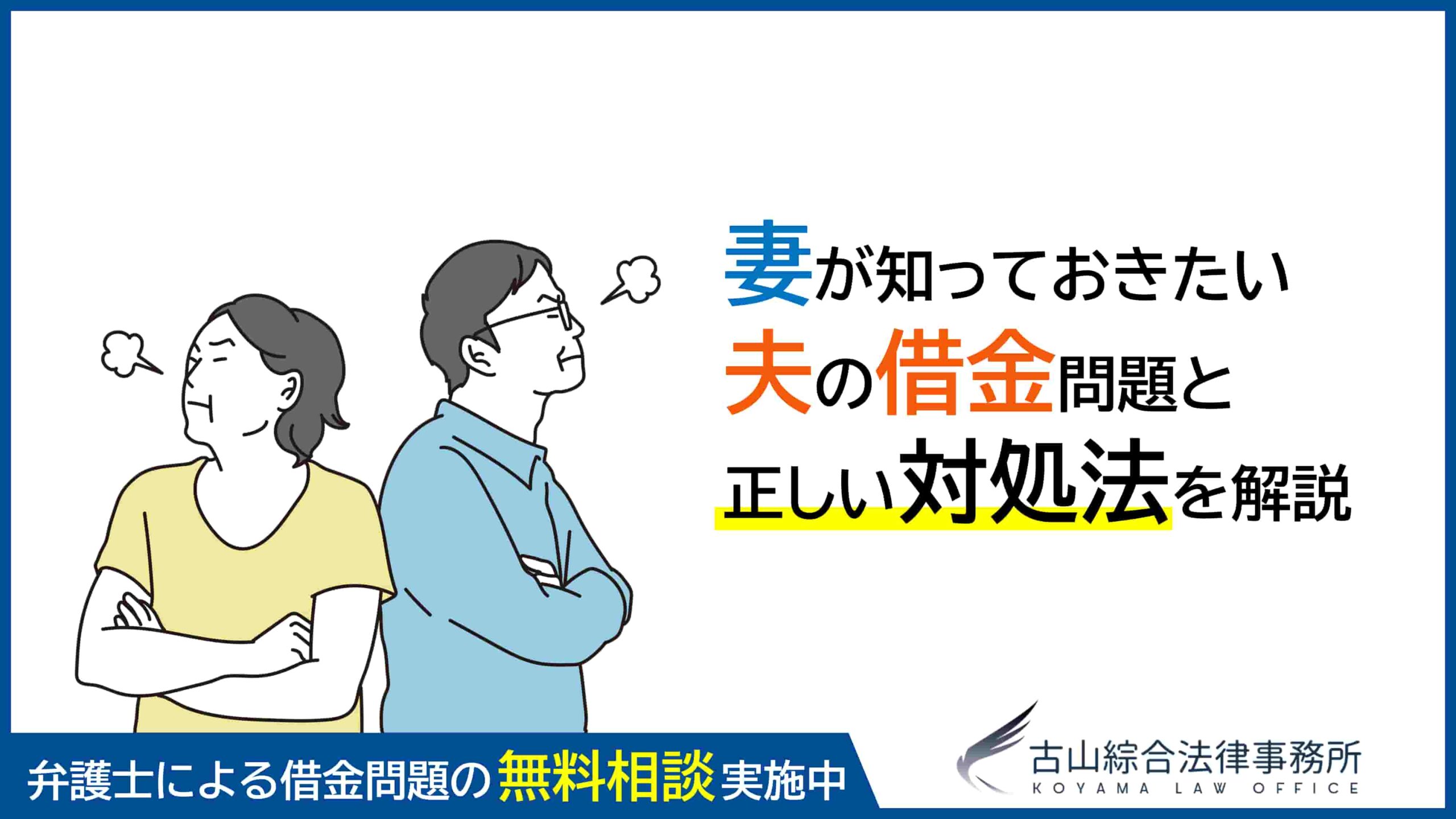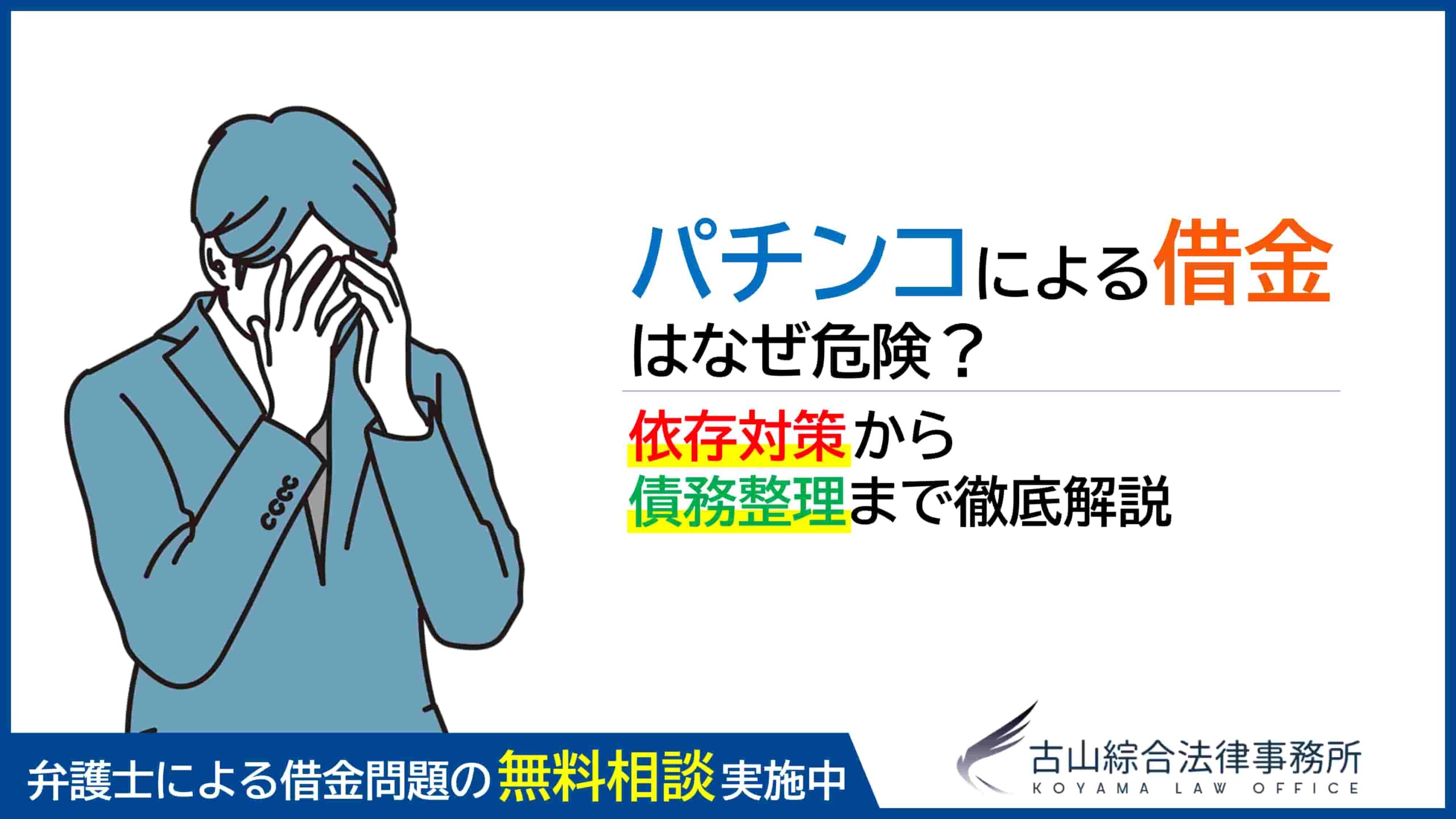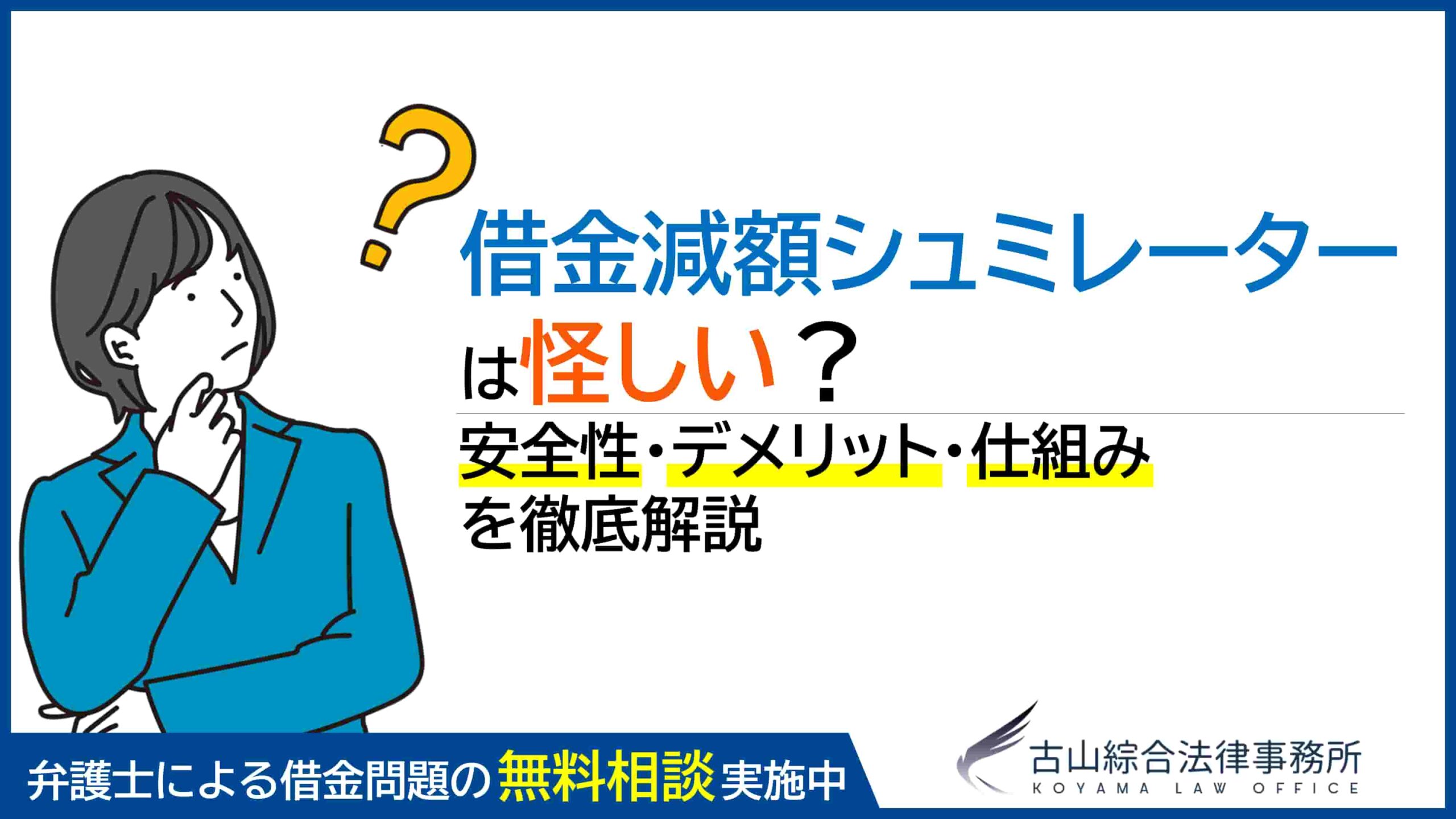自己破産で奨学金はどうなる?返済義務と保証人への影響を徹底解説
借金問題
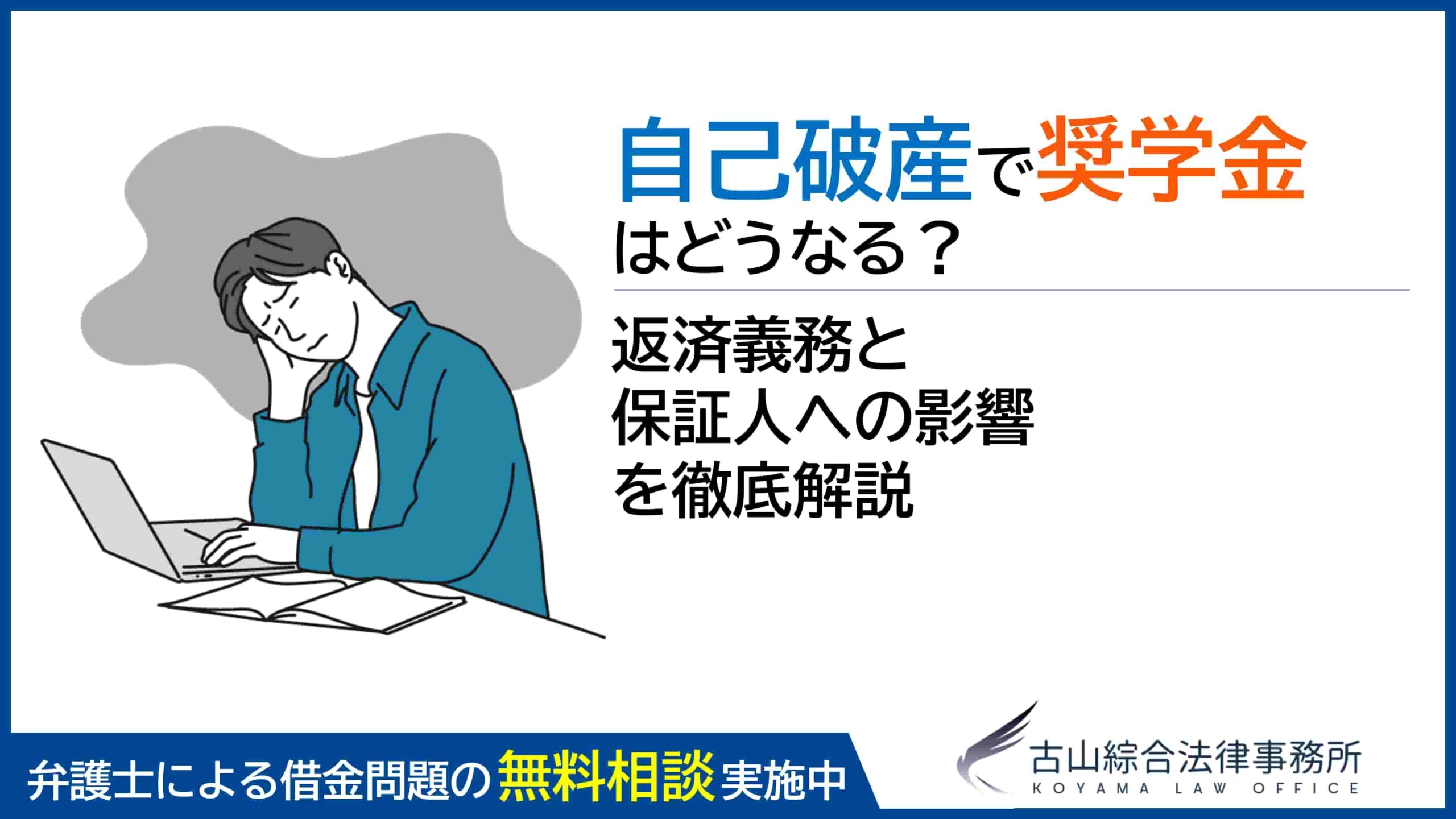
この記事の目次(クリックで開閉)
自己破産で奨学金はどうなる?返済義務と保証人への影響を徹底解説
奨学金の返済が難しくなったとき、自己破産という選択肢を考える方も少なくありません。
本記事では、自己破産によって奨学金がどのように扱われるのか、連帯保証人・保証人への影響、事前に利用できる救済制度、そして自己破産の手続きの流れやデメリットまで詳しく解説します。
多額の借金問題を抱え、一度債務整理を検討する際には奨学金の取り扱いが大きなポイントとなります。
特に保証人がいる場合は、自分は免責されても、自己破産によってその負担(多くの場合、残りの金額の全部)が移るリスクがあるため、細心の注意が必要です。
1. 自己破産すると奨学金は免除される?基本的な仕組み
自己破産は、多額の負債を抱えて返済ができなくなった人を救済するための法的手続きです(破産法第1条 参照)。
奨学金も、貸金業者からの借金と同じ債務(借金)です。
原則として、自己破産による「借金返済の免除(免責)」の対象となります。
裁判所に自己破産の申立てをおこない、最終的に「免責許可決定」(破産法第252条1項)が確定すれば、奨学金を含むほとんどの債務の支払義務が法的に免除されます。
しかし、連帯保証人や保証人が設定されている場合、免責されるのは申立人本人だけで、保証人には返済義務が残る点に注意が必要です。
裁判所に免責を認めてもらうためには、主に次の2つの条件を満たす必要があります。
1-1. 返済が困難とみなされる支払不能の条件
自己破産手続き自体が裁判所に認められるためには、「支払不能」(破産法第15条1項)状態であることが必要です。
支払不能とは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態」(破産法第2条11項)を指します。
単に「今月のお金が足りない」といった一時的な資金繰りの問題ではありません。
ご自身の年収や給与などの収入、保有資産、社会的信用(新たに借入ができるか)、年齢などを総合的に考慮しても、将来にわたって継続的に返済していく見込みが立たない状態を意味します。
奨学金のみならず、クレジットカードのリボ払いや他のローン、家賃の延滞なども含め、全部の負債総額とご自身の給与所得(手取り収入)を比較して判断されます。
奨学金の月々の返済が重荷となり、最低限の生活費(家賃、食費、光熱費など)をまかなえない場合も支払不能に当たる可能性があります。
支払不能の判断は、最終的には裁判所が客観的な証拠(家計簿、財産目録、給与明細、負債一覧など)にもとづいておこないます。
1-2. 免責不許可事由に当てはまるかどうか
免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)とは、自己破産の手続きにおいて、裁判所が借金の返済義務を免除する「免責許可」を出さない(不許可とする)と判断する原因となる「特定の事情」を指します。
免責不許可事由にあたる事情がある場合、裁判所による審査が厳しくなるケースもあります。
参照 免責不許可事由
- 財産の隠匿(財産隠し)
債権者に配当されるべき財産を隠したり、意図的に価値を下げたりする行為。 - 不当な財産処分
破産手続きの開始を遅らせる目的で、不利益な条件で財産を処分(安売り)したり、換金(クレジットカードのショッピング枠の現金化など)したりする行為。 - 偏頗弁済(へんぱべんさい)
特定の債権者(友人、親族など)にだけ優先的に返済する行為。
すべての債権者は平等に扱われなければならない(債権者平等の原則)ためです。 - 浪費または賭博(ギャンブル)
収入に見合わない過度な浪費(高級品の購入、飲食)や、ギャンブル(パチンコ、競馬、FX取引など)によって著しく財産を減少させ、または多額の借金を作ったこと。
奨学金の自己破産でも、奨学金以外の借金の理由がこれに該当すると問題になります。 - 詐術による信用取引
返済能力がないことを知りながら、詐欺的な手段(収入を偽るなど)を使ってお金を借り入れた行為。
(奨学金の場合の例)
・ 収入や家庭状況を偽って不正に受給した場合
・ 学費に充てると偽り、実際はギャンブル等に費消した場合 - 裁判所への説明義務違反・虚偽の説明
破産管財人や裁判所が行う調査に協力しなかったり、嘘の説明をしたりする行為。 - 過去7年以内の免責
過去に自己破産で免責許可を受けている場合、そこから7年が経過していない。
このような場合、免責不許可事由(破産法第252条1項)に該当する、または非免責債権(同法第253条1項2号)と認定され、免責が認められない可能性があります。
2. 連帯保証人・保証人にはどんな影響がある?
奨学金の契約時、例えば「日本学生支援機構(JASSO)」の奨学金で「人的保証」を選択している場合、連帯保証人(通常は親)や保証人(通常は4親等以内の親族)を立てていることが一般的です。
ご自身(主債務者)が自己破産して免責許可を受けても、連帯保証人・保証人の返済義務はなくなりません。
債権者(日本学生支援機構など)は、主債務者が破産したことを知ると、直ちに連帯保証人・保証人に対して、残っている奨学金の全額(元金+利息+延滞金)の一括返済を請求してきます。
特に連帯保証人の場合は、主債務者と同等の返済義務を負うため、甚大な影響があります(民法第454条)。
そのため、家族や親族に多大な迷惑をかけることになります。
奨学金の返済を求められた結果、家族の家計を圧迫し、最悪の場合、連帯保証人である親や親族自身も自己破産や個人再生などの債務整理を選択せざるを得なくなるケースもあります。
こうした最悪の事態を避けるためには、自己破産手続きに入る前に、必ず連帯保証人・保証人となっている家族や親族と十分に話し合い、状況を誠実に説明することが大切です。
一方で、「機関保証」を利用していれば、保証会社が返済を肩代わり(代位弁済)するため、ご家族や親族である保証人には請求が及びません。
まずは破産を検討する際、ご自身の奨学金契約が「人的保証」か「機関保証」かを確認することが極めて重要です。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
3. 自己破産する前に検討できる奨学金返還の救済制度
奨学金を返済できないからといって、すぐに自己破産を選択するのではなく、まずは日本学生支援機構(JASSO)が設けている公式の救済制度を利用可能か確認しましょう。
日本学生支援機構では、返済が困難な人のために複数の救済制度を用意しています。
3-1. 減額返還制度:月々の返還額を抑える方法
減額返還制度とは、所得が一定基準(例:給与所得者の場合、年間収入325万円以下。給与所得以外の所得を含む場合は年間所得金額225万円以下)を下回るなどの条件を満たす場合に、奨学金の毎月の返済額を2分の1、3分の1、4分の1、3分の2に減額できる制度です。
失業、病気(傷病)、災害、その他経済的に困難な事情がある場合には、減額返還制度を検討することで家計の安定を図ることが可能です。
ただし、減額した分だけ返済期間が延長されます。
そのため返済総額(特に利息)は変わらない(または利息分が増える)点に注意が必要です。
あくまで一時的な負担軽減策です。
3-2. 返還期限猶予制度:返済を一時的に止める仕組み
失業、病気、災害、経済困難などで収入が著しく減少し、返済そのものが困難になった場合、返還期限猶予制度を利用すると、一定期間(1年ごとに申請、通算10年まで)奨学金の返済を停止できます。
利用条件は、給与所得者の場合、税込み年間収入300万円以下(給与所得者以外は所得200万円以下)です。
猶予期間中は返済が不要となります。
3-3. 返還免除制度:特定の条件で支払いを免れる
以下の非常に限られたケースでは、返還免除制度により奨学金の返済そのもの(全部または一部)が免除されるます。
- 本人が死亡した場合
- 精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失、または労働能力に高度の制限を有し、返還ができなくなった場合
条件を満たすかどうかの判断には、医師の診断書などの書類が必要です。
4. 自己破産以外の債務整理方法と奨学金の扱い
自己破産以外にも、任意整理や個人再生といった債務整理の方法が存在します。
奨学金(特に保証人がいる場合)の扱いは、それぞれの手続きで大きく異なります。
制度の特徴をよく理解し、弁護士など専門家と相談の上で最適な解決策についてアドバイスを受けることをお勧めします。
4-1. 任意整理でのリスクと可能性
任意整理では、裁判所を通さずに債権者(貸金業者など)との交渉により和解を目指すため、手続きが比較的簡便な点がメリットです。
主に将来利息のカットや、長期の分割返済(例:3年〜5年)により月々の返済額を減らすことで負担を軽減します。
しかし、奨学金はもともと低金利または無利子であり、日本学生支援機構(JASSO)と任意整理をおこなうことのメリットは低いのが実情です。
減額や猶予については前述の「救済制度」を利用するのが一般的です。
4-2. 個人再生で返済を圧縮する方法
個人再生は、裁判所に再生計画の認可を受けることで負債の元本を大幅に圧縮できる制度で、特に住宅ローンのある持ち家を手元に残せる点が最大のメリットです。
個人再生は、自己破産と同様に奨学金も圧縮の対象に含めることができます。
ただし、個人再生も自己破産と同様に、連帯保証人・保証人の債務は圧縮されません。
手続きを開始すると、債権者(JASSO)は連帯保証人に対し、圧縮される前の全額(または保証契約に基づく金額)の返済を請求します。
特定の債権者のみを個人再生手続きの対象とすることはできません。
そのため、主債務者が個人再生手続きをおこなうことで、連帯保証人に対して一括請求がされるといった迷惑がかかることがあります。
5. 自己破産の手続きと流れ
自己破産を決意した場合、どのような流れで手続きが進むのか、概要を説明します。
実際の申立て手続きは非常に専門的であり、多くの書類作成が必要となるため、通常は弁護士に依頼して進めます。
弁護士への相談・依頼
弁護士に借金や収入の状況(借入先、金額、理由など)を相談します。
自己破産が最善の方法か、他の方法がないかを検討します。
依頼が決定すると、弁護士から各債権者(JASSO含む)へ「受任通知」が送付され、本人への直接の取り立てが停止します。
裁判所への申立て準備
弁護士と協力し、自己破産の申立てに必要な書類(申立書、債権者一覧表、資産目録、家計簿など)を作成・収集します。
裁判所への申立て・破産手続開始決定
書類が揃ったら、管轄の地方裁判所に自己破産の申立てをおこないます。
裁判所が書類を審査し、支払不能状態であると認めると「破産手続開始決定」が出されます。
破産管財人による調査 または 同時廃止
裁判所の判断により、下記のいずれかの手続きに進みます。
申立人にめぼしい財産(目安として20万円以上)がなく、免責不許可事由(浪費やギャンブルなど)の疑いもない場合に、破産手続の開始と同時に手続きが終了(廃止)する最も簡易な流れです。
・管財事件(かんざいじけん)一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由の調査が必要な場合に「破産管財人」(基本的に弁護士)が選任されます。
管財人は財産の換価・配当や、免責を許可すべきかの調査をおこないます。
免責審尋(めんせきしんじん)
裁判官が申立人と面談し、自己破産に至った事情や反省の意などを直接確認する手続きです(同時廃止の場合は省略されることもあります)。
免責許可決定・確定
免責審尋を経て、特に問題(重大な免責不許可事由など)がなければ、裁判所から「免責許可決定」が出されます。
この決定が官報に公告され、約1ヶ月後に確定すると、正式に奨学金を含む借金の返済義務が免除されます。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
6. 自己破産のデメリットと注意点
自己破産によって奨学金の返済負担が免除されますが、以下のようなデメリットや社会生活上の注意点があります。
6-1. クレジットカードやローンの利用制限
自己破産をすると、その情報が個人の信用情報を管理する「個人信用情報機関」に「事故情報」として登録されます(いわゆるブラックリスト状態)。
この状態は一般的に5年〜7年ほど続きます。
参照 個人信用情報登録機関における登録機関(自己破産の場合)
- CIC (株式会社シー・アイ・シー)
「破産の場合は免責許可決定が確認できた会員会社によるコメントが登録された報告日が起算点」であり、そこから5年間。 - JICC (株式会社日本信用情報機構)
「免責確定の日付でJICCに完済の登録」がされてから5年以内。 - KSC (全国銀行個人信用情報センター)
「官報に公告された破産・民事再生手続開始決定」から7年を超えない期間。
なお、日本学生支援機構は当センターに加入しています。
そのため、奨学金の返済滞納があれば、金融機関にバレる可能性があります。
事故情報の登録期間中は、次のことが難しくなります。
そのため、日常生活において不便を感じる場面も出てきます。
- 新規のクレジットカード作成
- 住宅ローン、自動車ローン、カードローンなどの新規借入
- スマートフォンの本体代金の分割払い
6-2. 就職や資格への影響はあるか
「自己破産をすると仕事をクビになるのではないか」
「就職活動に不利になるのではないか」という不安を持つ方も多いです。
ただし、自己破産を理由に解雇することは不当解雇にあたる可能性が極めて高く、法的に認められません。
また、就職活動においても、履歴書に自己破産の事実を書く必要はなく、一般企業が個人の破産情報を調査することも通常はありません。
ただし、一部の職業や資格については、破産手続開始決定から免責許可決定(復権)までの間、法律上の「資格制限」を受けます。
参照 制限を受ける主な職業・資格の例
- 弁護士、司法書士、税理士、公認会計士などの士業
- 警備員
- 生命保険募集人
- 貸金業者
- 旅行業務取扱管理者
これらの仕事に就いている場合、手続き中は業務ができません(一時的に休職や異動などが必要な場合があります)。
ただし、免責許可決定が確定すれば「復権」し、資格制限は解除され、再び業務に従事できます。
公務員への就職や勤務する上で不利になることは原則ありません(資格制限の対象職種を除く)。
6-3. 官報掲載とプライバシーの問題
自己破産手続き(開始決定時と免責許可決定時)が完了すると、国の広報誌である「官報」に氏名や住所などの情報が掲載されます。
官報は、政府刊行物センターや一部の大きな図書館で閲覧できるほか、インターネット(直近30日分は無料、それ以降は有料データベース)でも検索が可能です。
一般の人が日常的に官報をチェックする機会はまずありません。
そのため、官報に掲載されたことで、周囲にバレる可能性は低いと言えます。
しかし、金融機関や信用情報機関、一部の企業(不動産業、金融業など)や、いわゆる「闇金業者」などは官報の情報をチェックしている場合があります。
近年では官報情報をまとめたサイトなども存在し、ネット上で名前が検索される可能性はゼロではありません。
こうした点も踏まえると、プライバシーリスクを完全に避けるのは困難です。
7. 機関保証制度と人的保証制度の違い
奨学金の申し込み時に選ぶ保証制度によって、自己破産時や返済トラブルの影響範囲が大きく異なります。
奨学金の申し込み時に選ぶ保証制度によって、自己破産時の影響範囲が大きく異なります。
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金には、主に「人的保証制度」と「機関保証制度」があります。
人的保証制度
親や親族に「連帯保証人」「保証人」になってもらう方法です。
保証料はかかりません。
機関保証制度
JASSOが指定する保証機関(公益財団法人日本国際教育支援協会(JEES))に保証人になってもらう方法です。
毎月の奨学金から一定の保証料が天引きされます。
自己破産をした場合の影響は、この2つの制度で全く異なります。
人的保証の場合
前述(「2. 連帯保証人・保証人にはどんな影響がある?」)の通り、本人が免責されても、連帯保証人・保証人に一括請求がおこなわれます。
機関保証の場合
本人が返済できなくなると(自己破産含む)、保証機関(JEES)がJASSOに残額をまとめて返済します(これを「代位弁済」と言います)。
その後、債権(返済を求める権利)がJASSOから保証機関に移り、保証機関が本人に対して「あなた(本人)の代わりに払ったお金を返してください」という請求(求償権)を行使してきます。
しかし、本人が自己破産の手続きをしていれば、この保証機関からの求償権も免責の対象となります。
したがって、機関保証制度を利用していれば、自己破産をしても、保証機関が返済を肩代わりするため、家族や親族に返済請求がいくことはありません。
連帯保証人を確保できない人や、家族への負担・迷惑を避けたい人は、機関保証制度の利用を検討するケースが増えています。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
8. 奨学金だけを返済することはできる?部分的免責の可能性
自己破産において、「他の借金は免責したいが、保証人に迷惑をかけたくないので奨学金だけは返済を続けたい」といった、特定の債務だけを対象から除外することは認められません。
自己破産制度は、「債権者平等の原則」に基づいています。
これは、すべての債権者(お金を貸した側)を平等に扱わなければならないというルールです。
奨学金(JASSO)だけを除外して他の債務だけを免責しようとすることは、この原則に反します。
また、自己破産の申立て直前に、連帯保証人のある借り入れだけを優先して返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」(特定の債権者だけに返済すること)とみなされます。
この行為は、破産管財人による否認の対象となり、免責不許可事由(破産法第252条1項3号)に該当したりする可能性が非常に高く、極めて危険です。
奨学金をどうしても残したい(=保証人に迷惑をかけたくない)場合は、自己破産ではなく、奨学金以外の債務だけを対象とする「任意整理」を検討するか、日本学生支援機構の救済制度を利用する方法を考える必要があります。
9. よくあるQ&A
自己破産と奨学金に関して、よくある質問に回答します。
ただし、制度の細部は個人の状況により大きく異なるため、最終的な判断は弁護士など専門家にご相談ください。
9-1.奨学金の 連帯保証人・保証人が自己破産したらどうなる?
連帯保証人・保証人自身の「奨学金の返済義務」は免責(免除)されます。
主債務者の奨学金の返済義務は消滅しません。
また、債権者から主債務者に対して一括返済を求められることもありません。
ただし、連帯保証人の自己破産により保証能力を失ったと判断された場合、債権者から新たに保証人を追加するよう求められることがあります。
9-2. 保証人が死亡している場合はどうなる?
保証人がすでに亡くなっているときは、その保証債務(奨学金の返済義務)は相続人に引き継がれます(民法第896条)。
つまり、本人の自己破産とは別に、保証人の相続人(例えば、もう一方の親や兄弟姉妹など)が返済を請求されるケースが生じます。
相続人が保証債務を引き継ぎたくない場合は、家庭裁判所で「相続放棄」(民法第939条)の手続き(原則として相続開始を知った時から3ヶ月以内)をおこなう必要があります。
この手続きを怠ると、保証債務を含めた全ての遺産を相続したものとみなされ(単純承認)、返済義務を負うことになります。
こうした複雑なケースでは、法律の専門家に相談して相続手続きの状況や連帯保証の有無を早めに確認することが重要です。
10. まとめ
奨学金の返済が困難に陥った際には、自己破産という選択肢だけでなく、日本学生支援機構が用意する各種救済制度(減額・猶予)まで、幅広い選択肢を検討することがポイントです。
自己破産によって奨学金は免除されますが、ご自身の奨学金契約が「人的保証」である場合、連帯保証人・保証人に一括請求がいくという最大のリスクを理解する必要があります。
「機関保証」であれば、家族に迷惑はかかりません。
また、信用情報への登録(5年〜7年)や、一部の仕事での資格制限、官報掲載といったデメリットも考慮する必要があります。
まずはご自身の契約内容を確認し、JASSOの「減額返還制度」や「返還期限猶予制度」を活用できないか検討しましょう。
それも難しい場合は、自己破産や個人再生といった法的手続きが必要になります。
奨学金の扱いは、借金問題の整理において最も複雑な部分の一つです。
ご自身の精神的な負担を減らし、法的に安全な解決策を見つけるためにも、延滞してしまう前に、できるだけ早く弁護士などの専門家に相談し、最適な方法を選ぶのが重要です。
古山綜合法律事務所では、自己破産手続きのサポートをおこなっています。
初回無料の法律相談では事情を丁寧にお伺いし、① 解決策のアドバイス、② 解決の見通し、③ 不安・疑問について個別のご質問に回答いたします。
借金問題の悩みは、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
なお、法律相談は事前予約制です。
電話、LINE、メールフォームからご予約・お問い合わせください。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。