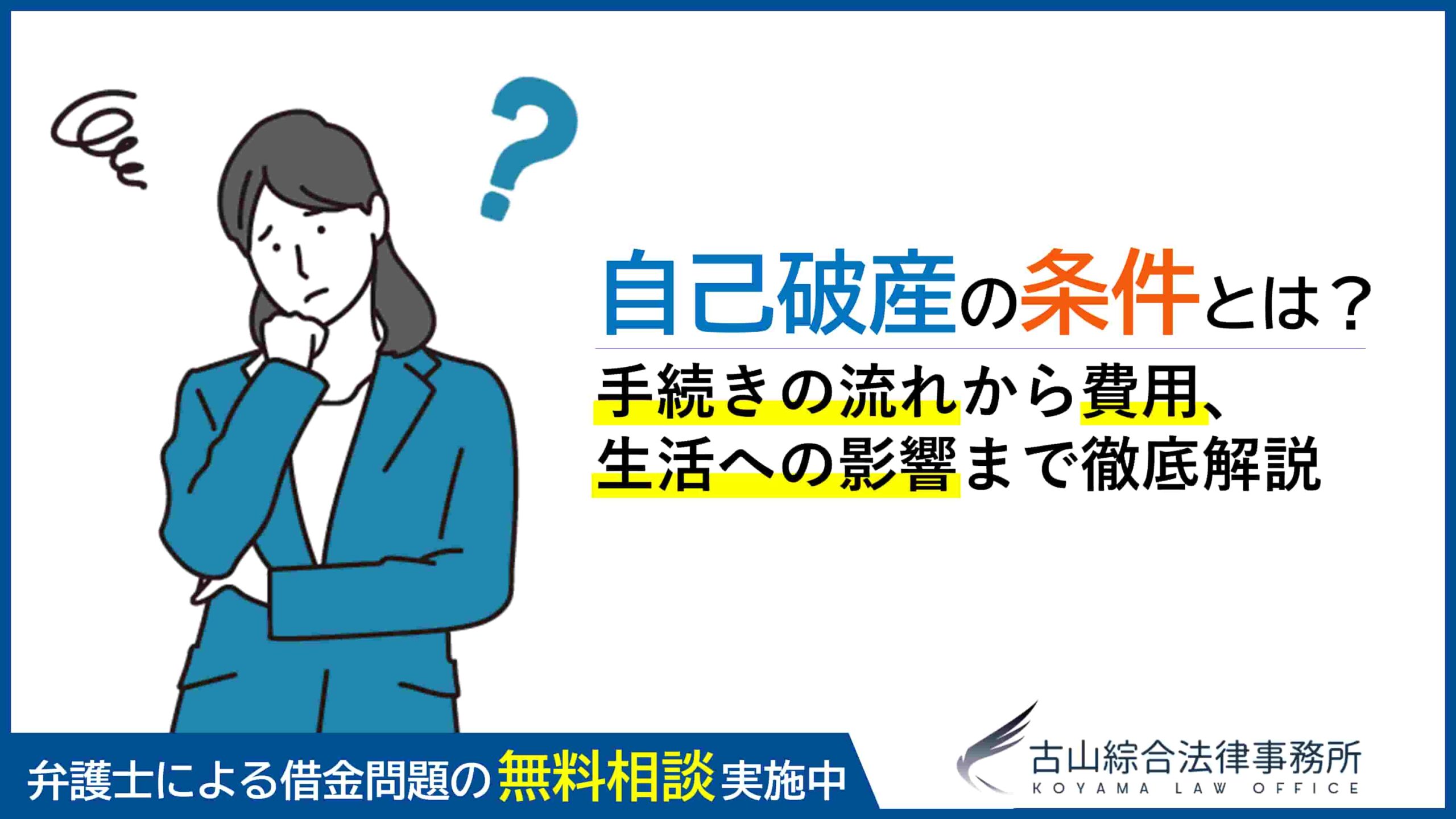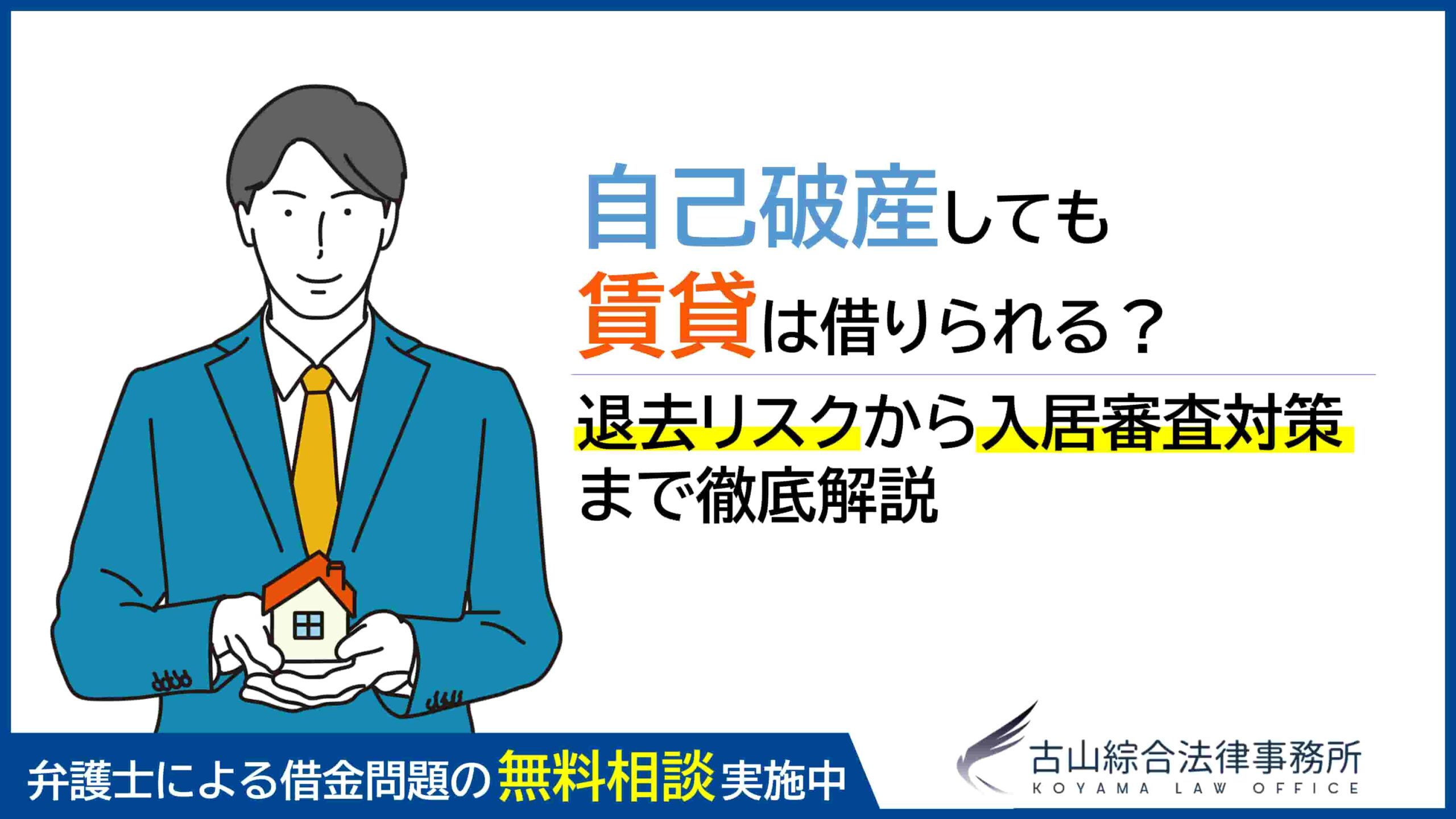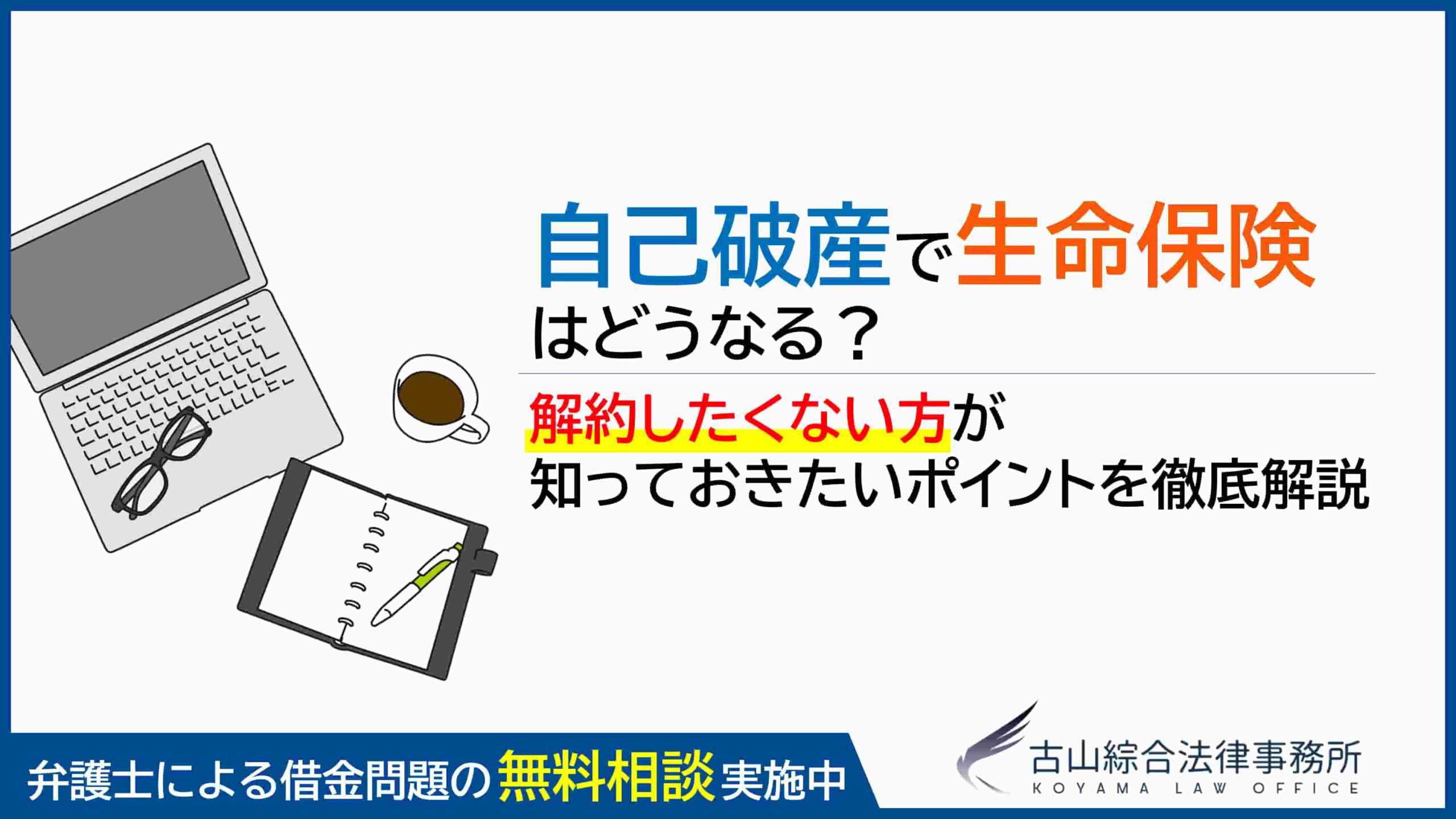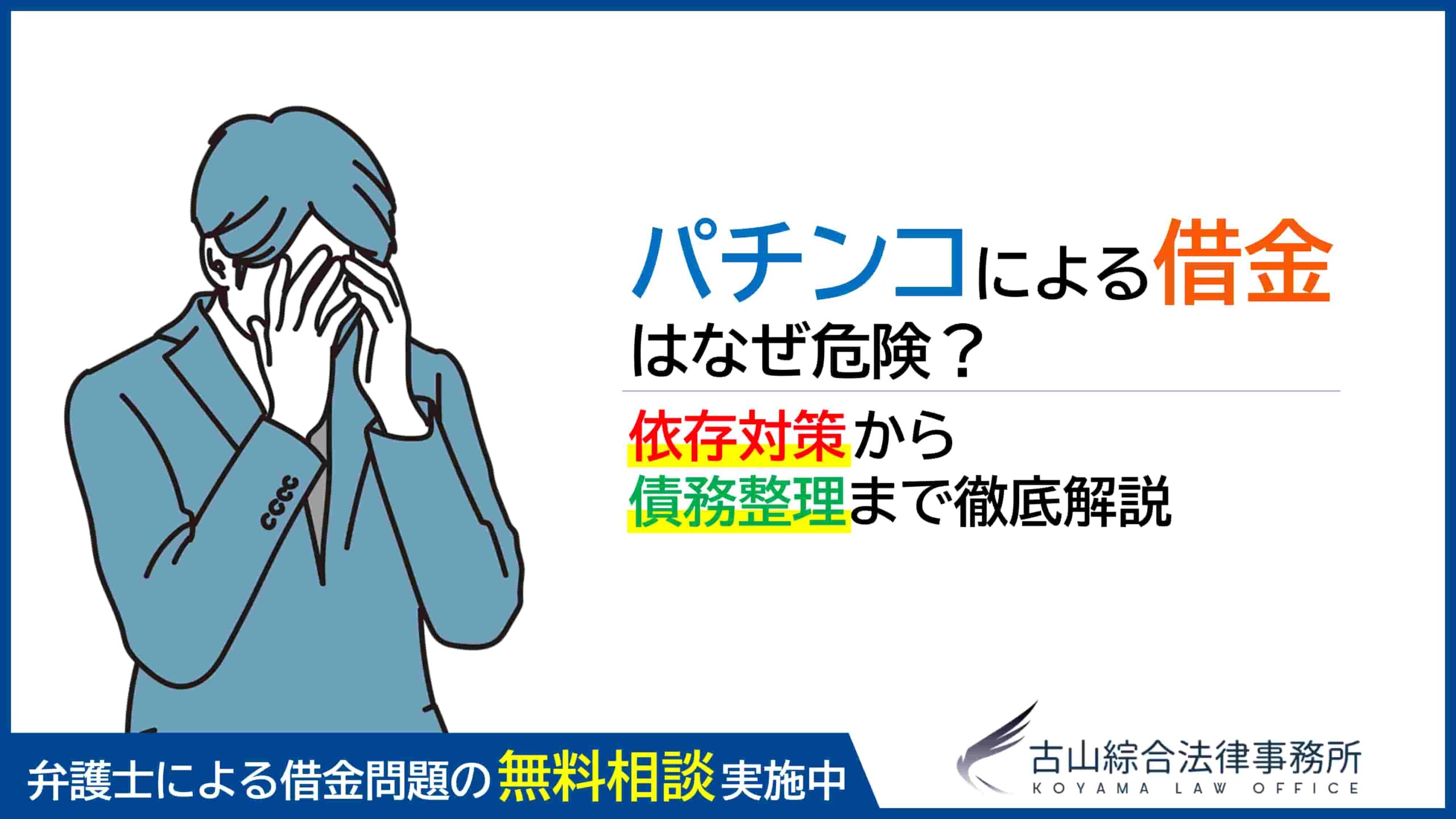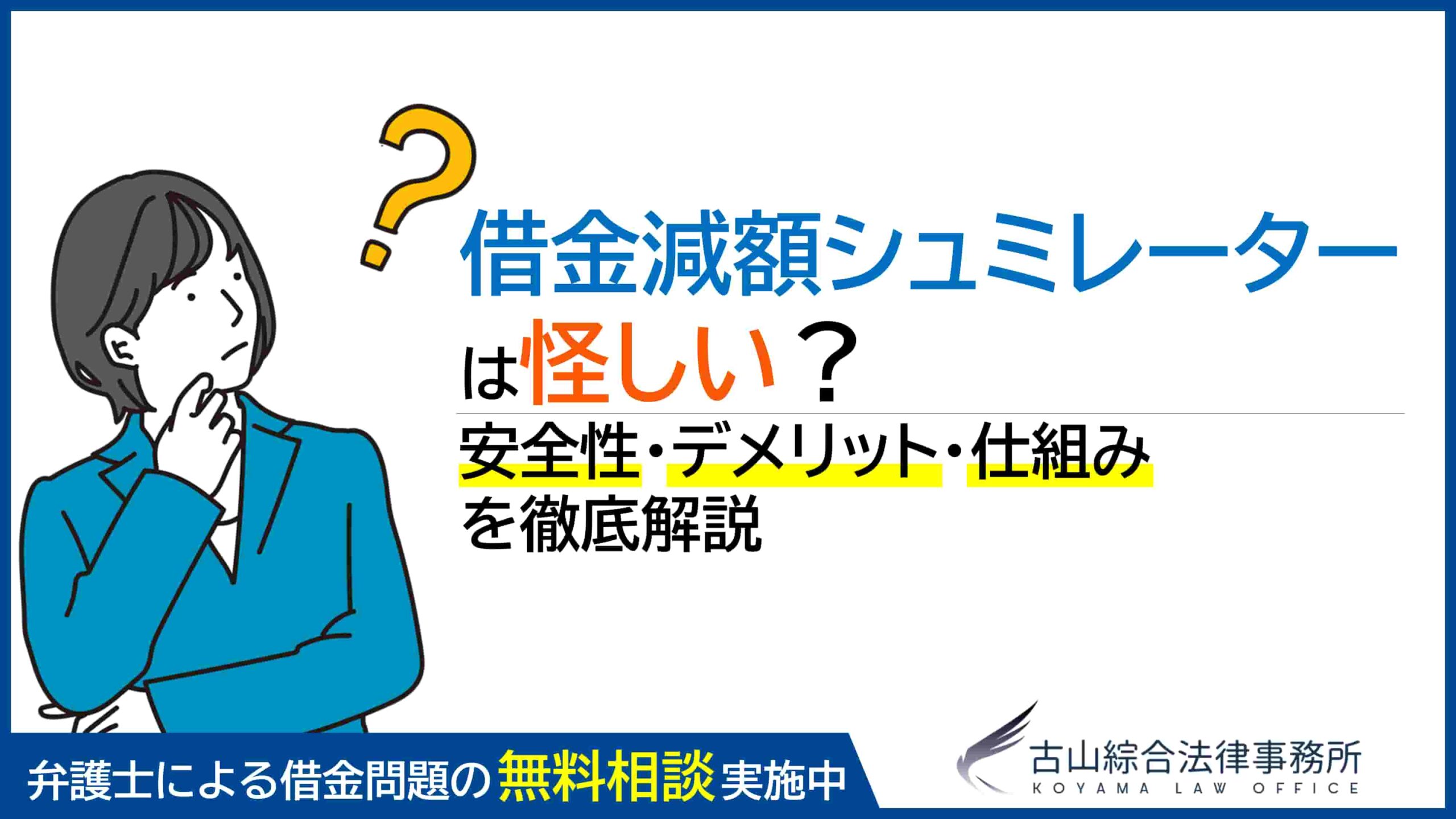免責不許可事由とは?自己破産で借金が帳消しにならないケースを徹底解説
借金問題
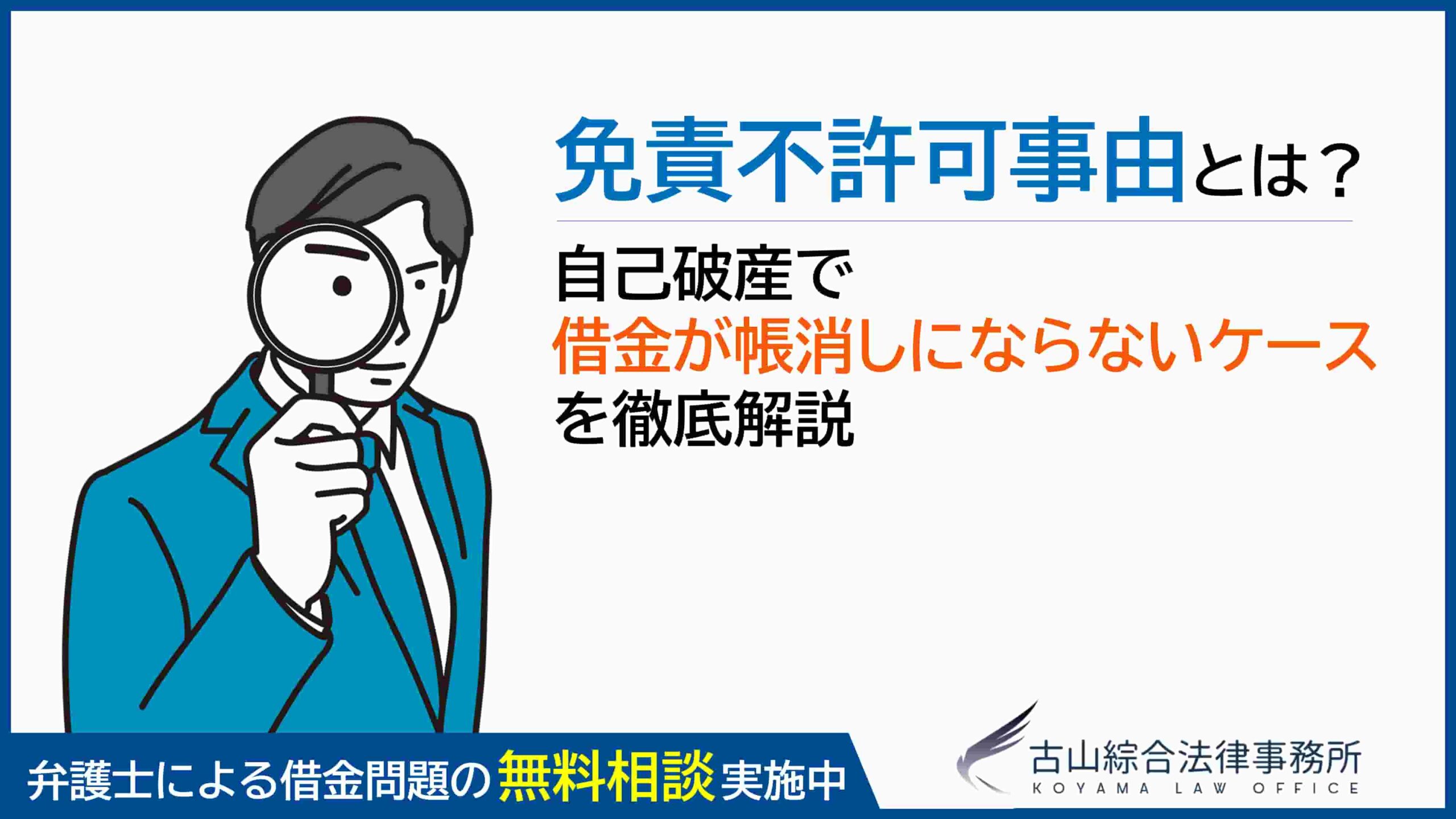
この記事の目次(クリックで開閉)
免責不許可事由とは?自己破産で借金が帳消しにならないケースを徹底解説
自己破産手続きの最終的な目的は、支払い義務が免除される「免責許可決定」が認められることです。
しかし、特定の行為や状態があると、裁判所が免責を許可しない可能性が出てきます。
その理由となるのが「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」です。
本記事では、自己破産と免責の仕組みから、どのような行為が免責不許可事由に該当するのか、そして万が一該当しそうな場合の対処法まで、借金問題の解決に向けて詳しく解説します。
1. 自己破産と免責の基本:なぜ免責不許可事由が問題になるのか
自己破産とは、債務者が経済的に立ち行かなくなった(=支払不能状態にある)際、裁判所に申し立てることで、法律に基づき借金を整理する手続きです。
手続きの最終段階で「免責許可決定」が下りれば、税金など一部を除いて、原則として残った借金の支払い義務は免除されます。
これが最大のメリットです。
しかし、すべての場合において無条件で免責が認められるわけではありません。
免責不許可事由が定められている理由は、債権者間の公平を保つためです。
自己破産制度は、債権者にとっては「貸したお金が返ってこない」という大きな不利益を受け入れてもらう制度です。
そのため、債務者が財産を隠すなどの不誠実な行為をしたり、制度を悪用したりすることを防ぐ必要があります。
こうした違法・不誠実な行為が「免責を許可しない理由」として、法律(破産法第252条第1項)に具体的に定められています。
免責不許可事由に該当する疑いがある場合、原則として裁判所は「破産管財人」を選任します。
破産管財人とは、裁判所に代わって債務者(破産者)の財産を管理・換金し、債権者に公平に分配する役割を担う弁護士です。
また、債務者に免責不許可事由がないか、借入の経緯や財産状況について詳細な調査をおこないます。
この調査の結果、免責不許可事由が悪質であると判断されると、免責は認められず借金は帳消しになりません。
2. 免責不許可事由の重要ポイント
免責不許可事由は、破産法第252条第1項に明確に定められています。
これらの事由に該当する行為や状態があると、原則として裁判所は免責を許可しません。
ただし、免責不許可事由に該当しても、必ず免責が不許可になるわけではありません。
破産法には「裁量免責」という救済措置が定められています(破産法第252条第2項)。
これは、裁判所が諸般の事情を考慮し、「免責を許可するのが相当」と判断すれば、免責を許可する制度です。
しかし、「どうせ裁量免責があるから」と安易に考えるのは非常に危険です。
裁量免責はあくまで例外的な救済措置であり、その判断は裁判所と破産管財人の調査にゆだねられます。
免責不許可事由に共通しているのは、「債権者の立場を不当に害する行為」や「破産制度を悪用するような不誠実な行為」である点です。
たとえば、財産隠しや、破産手続きに必要な書類(財産目録など)への虚偽記載といった誠実性を欠く行動が該当します。
参照 免責不許可事由(破産法第252条第1項)の概要と具体例
| 号数 | 概要(法律上の主な内容) | 主な具体例 |
|---|---|---|
| 第1号 | 財産を不当に減らす行為 | 財産隠し、財産の意図的な破壊、不当に安い価格での財産処分 |
| 第2号 | 不当な債務負担・処分 | クレジットカードの現金化(換金行為)、ヤミ金からの高金利での借入 |
| 第3号 | 特定の債権者への返済 | 偏頗弁済(へんぱべんさい。友人・親族・勤務先など一部の人にだけ返済する) |
| 第4号 | 浪費やギャンブルによる借金 | 浪費(過度な飲食・ショッピング)、ギャンブル(パチンコ・競馬)、FXや株取引 |
| 第5号 | 嘘(詐術)による信用取引 | 収入や借入額を偽ってローンを組む、返済不能と知りながら借金する |
| 第6号 | 帳簿などを隠す行為 | 個人事業主が業務や財産の帳簿・書類を隠したり、偽造したりする |
| 第7号 | 虚偽の債権者名簿の提出 | 裁判所に提出する債権者一覧表(名簿)に、意図的に一部の債権者を載せない |
| 第8号 | 裁判所への虚偽説明 | 裁判所が行う調査(免責審尋など)に対し、説明を拒んだり嘘の説明をしたりする |
| 第9号 | 管財業務の妨害 | 破産管財人の調査や財産管理・換価といった業務を妨害する |
| 第10号 | 過去7年以内の免責 | 過去7年以内に、自己破産などで免責許可決定を受けている |
| 第11号 | その他、義務違反 | 破産者としての説明義務や、裁判所への協力義務などに違反する |
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
3. 免責不許可事由の種類
免責不許可事由は、破産財産の隠匿や偏頗弁済など多岐にわたります。
これらの行為は、債権者が受けるはずだった配当や権利を著しく損なうため、自己破産手続きに重大な影響を及ぼします。
3-1. 破産財団の価値を不当に減少させる行為(第1号)
債権者の利益を害する「財産隠し」や、財産を故意に壊したり、不当に安く処分したりする行為は、免責不許可事由のひとつです(第1号)。
破産手続きでは、債務者の財産は「破産財団」として管理され、処分の上でお金に換えたうえで各債権者に平等に配分されます。
破産財団の価値を不当に減少させる行為は、この債権者の利益を直接害するためです。
- 財産隠し
預金口座の存在を隠す、解約返戻金のある生命保険を申告しない、他人名義の口座に現金を送金し隠す。 - 財産の損壊
資産価値のある自宅や車などを故意に壊す。 - 不当な処分
車や不動産を、適正価格より著しく低い金額で友人や家族に売却する。偽装離婚により財産分与として、所有財産を分けるなど。
こうした行為が発覚した場合、免責が認められない可能性は極めて高いです。
3-2. 著しく不利益な債務負担行為や処分行為(第2号)
破産手続きの開始を目前にして、債権者を害することを知りながら、不利益な条件で財産を処分したり、新たな債務を負担したりする行為も該当します。
財産の売買や取引などを行う場合、通常であれば正当な価格・条件で実施するのが原則です。
- クレジットカードの換金行為
クレジットカードのショッピング枠でブランド品や新幹線の回数券などの商品を購入し、それをすぐに買い取り業者や金券ショップで換金して現金を得る行為。 - 高利での借り入れ
ヤミ金など、法外な高金利の業者から借り入れをし、その返済のために財産を処分する行為。 - 不当な価格での財産処分
生活費や返済資金を得るために、所有する財産を相場より極端に安く売却すること。
こうした行為は、結果的に破産財団の価値を毀損し、債権者に不利益をもたらすため、免責不許可事由とされます。
3-3. 特定の債権者のみを優先して返済する偏頗弁済(第3号)
特定の債権者だけを優先して返済する行為は「偏頗行為(へんぱこうい)」(一般に「偏頗弁済」とも呼ばれます)といい、免責不許可事由に該当します。
自己破産は、すべての債権者を平等に扱わなければならない「債権者平等の原則」にもとづいて手続きを進めます。
経済的に支払不能となった後や、破産申立てを弁護士に依頼した後に、一部の債権者にだけ返済することは、この原則に反します。
ただし、水道光熱費や家賃など、生活維持のために必要な支出の支払いは、一般的に偏頗弁済とはみなされません。
- 家族、友人、勤務先からの借入金だけを「迷惑をかけたくないから」と優先して返済する。
- 特定の金融機関(例:給与振込口座がある銀行のカードローン)にだけ、返済時期を繰り上げて返済する。
こうした行為は、他の債権者への分配を減らすため、免責が認められない原因となります。
3-4. 浪費・賭博などの射幸行為による借金(第4号)
ギャンブルや過度な浪費、投機的な取引などによって多額の借金を作り、財産を著しく減少させたり、過大な債務を負担したりした場合も、免責不許可事由です。
これらは自ら招いたものであり、こうした原因の借金を安易に免除することは、破産制度の趣旨に反するためです。
- パチンコ、スロット、競馬などのギャンブル。
- FX、株式、仮想通貨などの投資(投機的な取引)。
- 収入や生活状況に見合わない高額なショッピング(ブランド品の購入など)。
- 高級な飲食、旅行、風俗通いなどの過度な支出。
実際には、これらの行為があっても「4. 裁量免責」によって免責許可となるケースは多いです。
しかし、金額や期間、借入全体の経緯から悪質だと判断されると、不許可となる場合もあります。
3-5. 詐術による信用取引(第5号)
「詐術(さじゅつ)」を用いて信用取引(借入や商品の後払い購入)を行った場合、免責不許可事由に該当します(第6号)。
詐術とは、簡単に言えば「嘘をついて相手を騙すこと」であり、詐欺的な手法で他人を欺く行為を指します。
- 返済する意思も能力もないのに、それを隠して金融機関や友人からお金を借りる。
- クレジットカードやローンを申し込む際に、年収、勤務先、他の借入状況などについて虚偽の申告をする。
- すでに支払不能状態にあることを自覚しながら、あるいは弁護士に自己破産を依頼した後で、新たに借入を行うこと。
こうした不正行為は、債権者を害する悪意のある行為とみなされ、厳しく取り扱われます。
3-6. 帳簿隠しや虚偽の債権者名簿の提出(第7号)
自己破産手続きでは、正確な債権者名簿や財産状況(財産目録)を裁判所や管財人に提出し報告する義務があります。
帳簿(個人事業主の場合など)を隠したり、損壊したり、債権者名簿に意図的な虚偽記載をすれば、破産手続きの公正性・正確性が失われます。
- 特定の財産(例:他人名義にしている不動産、へそくり口座)を財産目録に記載しない。
- 一部の債権者(特に友人や家族、勤務先など)を、迷惑をかけたくないという理由で意図的に債権者一覧表から除外する。
- 個人事業主が、売上を隠蔽したり、帳簿や領収書を破棄したりする。
これらの行為は、裁判所や破産管財人に対する重大な背信行為であり、厳しく追及されます。
3-7. 裁判所への説明義務違反や管財業務の妨害行為(第8号、第9号、第11号)
裁判所への説明義務に違反したり、破産管財人の業務(管財業務)を妨害したりする行為は、それ自体が免責不許可事由です。
破産手続きにおいて、破産者には裁判所や破産管財人の求めに応じて財産や借金についての説明義務があります。
これに協力しなかったり、虚偽の説明を繰り返したりする行為が該当します。
- 裁判所からの呼び出し(免責審尋など)や、破産管財人との面談に正当な理由なく応じない。
- 破産管財人の調査(例:通帳の提出、資産状況の説明)に対し、虚偽の説明をする、または協力を拒否する。
- 正当な理由なく住所を変更し、裁判所や管財人と連絡が取れなくなる。
3-8. 過去7年以内に免責を受けている場合(第10号)
自己破産によって免責許可決定が確定した事実がある場合、その免責許可決定の確定日から7年以内に再度、免責の申立てをすると、原則として免責不許可となります。
これは、同じ人が短期間に繰り返し自己破産を利用する(制度を濫用する)のを防ぐためのルールです。
ただし、前回の破産がやむを得ない事情(病気やリストラなど)によるもので、今回の破産も同様にやむを得ない事情がある場合などには、裁量免責が適用されるケースもあります。
3-9. その他の免責不許可事由(第11号など)
破産法第252条第1項には、上記以外に第11号として「破産者が…破産法に定める義務に違反したこと」という包括的な規定があります。
これは、上記1号から10号までに具体的に該当しなくても、破産手続きにおける破産者の義務(誠実な説明義務、財産開示義務、裁判所への協力義務など)に違反した場合に、免責を不許可にできる規定です。
免責不許可のリスクを回避するには、裁判所や破産管財人からの指示には誠実に対応することが重要です。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
4. 裁量免責とは?免責不許可事由に該当しても認められる可能性
免責不許可事由に該当しても、裁判所の判断で免責が認められることがあり、これを「裁量免責」といいます(破産法第252条第2項)。
裁量免責は、破産法上厳しく規定されている免責不許可事由がある場合でも、「破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して」裁判所が免責を認める制度です。
裁量免責が認められるかどうかの最大の鍵は、「破産管財人」と「反省の態度」です。
免責不許可事由が疑われる場合、破産管財人が選任されます。
破産管財人は、債務者の財産調査と並行して、免責不許可事由の有無や程度、債務者が真摯に反省しているか、経済的に更生する意欲があるかを調査します。
そして、裁判所に対して「免責を許可すべきか(免責許可相当)」あるいは「不許可とすべきか(免責不許可相当)」という意見書を提出します。
裁判所はこの破産管財人の意見を非常に重視します。
たとえば、浪費(第5号)による借金があったとしても、以下のような事情があれば、最終的に裁量免責が許可される可能性はあります。
- 弁護士や破産管財人に、浪費の事実を正直にすべて話している。
- 破産管財人の調査や指示(例:家計簿の作成・提出)に誠実に協力している。
- 裁判所や破産管財人に対し、深く反省している態度が伝わっている(例:反省文の提出)。
- 現在は支出を見直し、堅実な生活を送ろうと努力している。
- ギャンブル依存症の場合、治療をおこない、家族の支援がある。
ただし、財産隠しや虚偽説明など、破産制度の根幹を揺るがすような悪意のある不誠実な行為が発覚した場合は、裁量免責が認められないケースもあります。
免責不許可事由がある場合でも、弁護士に手続きの代行を依頼することで、こうした裁量免責の可能性を探り、裁判所や破産管財人との対応もサポートを受けることができます。
5. 免責不許可事由に該当した際の主な対処法
免責不許可事由に当たる行為があったとしても、適切な対処により裁量免責を得られる可能性は高まります。
最も重要なのは、自己判断で諦めたり隠したりせず、弁護士などの専門家に依頼して、正直に対応を相談することです。
具体的な対処法は以下の通りです。
5-1. 反省文や誠実な対応を行う
裁量免責を得るためには、誠実で反省のある態度を示すことが最も重要です。
具体的には、以下の点が求められます。
- 弁護士への正直な申告
弁護士には守秘義務があります。
依頼する弁護士に対し、不利な情報(浪費、偏頗弁済、隠したい財産など)も含めて、包み隠さず正直に話してください。 - 裁判所・管財人への誠実な協力
裁判所への提出書類(財産目録など)や面談(審尋)で自分の行為や経緯を正直に説明し、これまでの行動の誤りを指摘された場合には反省の姿勢が必要です。
嘘をついたり、事実をごまかしたりすれば逆効果です。
破産管財人の調査にも誠実に応じてください。 - 反省文の作成
裁判所や破産管財人から指示された場合、なぜそのような行為(浪費など)に至ったのか、現在どう反省しているのか、今後はどう生活を立て直すのか、を具体的に記した反省文を提出します。
弁護士に依頼すれば、問題点や具体的な対応(反省文の書き方、管財人面談での想定問答など)を事前にしっかり打ち合わせられます。
これが専門家に依頼する大きなメリットです。
5-2. 即時抗告の手続きで争う
万が一、地方裁判所で免責不許可の決定が下された場合、「即時抗告(そくじこうこく)」により高等裁判所で争うことができます。
即時抗告では、第一審(地方裁判所)の判断が適正に行われたかを再度審理してもらえます。
ただし、手続きには「決定書を受け取ってから1週間以内」という非常に短い期限があるため、早急な対応が必要です。
また、第一審の不許可の決定がくつがえるケースは一般的にまれで、ハードルは非常に高いです。
そのため、不許可の決定が出る前に、自己破産手続きの中でいかに対応するかが極めて重要です。
5-3. 個人再生や任意整理など他の債務整理手段を検討する
免責不許可リスクが非常に高い場合や、不許可が確定した場合は、自己破産以外の債務整理(個人再生・任意整理)を検討します。
ただし、いずれも返済を前提とした方法であるため、安定した収入が必要になります。
個人再生
裁判所を通じて、借金を大幅に減額(例:5分の1程度)してもらい、残りを原則3〜5年で分割返済する手続きです。
個人再生には免責不許可事由の規定がないため、浪費やギャンブルが原因でも利用可能です。持ち家を残せる場合もあります。
任意整理
裁判所を通さず、債権者(金融機関など)と直接交渉し、将来利息のカットや分割返済の合意を目指す手続きです。
交渉相手を選べるため、保証人がついている債務や、家族・友人からの借入を除外して手続きすることができます。
ただし、元金の大幅な減額は難しいです。
どの手続きが最適かは、借金の総額、原因、財産状況によって異なります。
自己破産が難しいと感じても、他の道が残されている可能性があるので、専門家にご相談ください。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
6. 免責不許可とされた事例から学ぶ留意点
免責不許可となった多くの事例では、財産隠しや嘘の申告、偏頗行為などが原因で裁判所や破産管財人の信頼を損なう行為が原因となっています。
たとえ金額が小さくても、わざとその事実を隠したと判断されると、不誠実な行為を理由に免責不許可となる可能性があります。
また、ギャンブルや過度な浪費により多額の借金を抱えていたケースでも、破産管財人の調査に協力的でなかったり、手続き中も支出を改めなかったりした結果、反省の態度が見られないとして裁量免責が認められず、免責不許可と判断された例もあります。
裁判所は借金の原因と、それに対する破産者の現在の態度を厳しく見ています。
7. 免責不許可事由と非免責債権の違い
自己破産において混同しやすい「免責不許可事由」と「非免責債権(ひめんせきさいけん)」は、明確に異なるものです。
免責不許可事由
自己破産手続きで免責不許可となるケースのことです。
影響これに該当すると、借金全体の免責が許可されない(=借金がゼロにならない)可能性があります。
対象破産者の「行為」や「態度」に対するペナルティです。
非免責債権
自己破産手続きで免責の対象とならない負債のことです。
影響免責不許可事由がなく、無事に「免責許可決定」が出たとしても、例外的に支払い義務が免除されない(=返済し続けなければならない)特定の債権のことです。(破産法第253条第1項)
対象借金の「種類」による区別です。
代表的な非免責債権には、以下のような公的性質の強いものや、倫理的に免除すべきでないものが挙げられます。
(非免責債権の例)
• 税金、国民健康保険料、年金保険料など
• 養育費、婚姻費用(生活費)
• 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償金
• 故意または重過失で加えた生命・身体への不法行為に基づく損害賠償金(例:飲酒運転による事故の慰謝料など)
• 罰金、科料など
• 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権
このように、免責不許可事由は「借金全体の免責」に関わる問題であり、非免責債権は「免責許可後も残る特定の債務」を指すという違いがあります。
8. 免責不許可事由に該当しても破産を成功させるためのポイント
免責不許可事由に当てはまっていても、「破産を成功させる(=裁量免責を得る)」ためのポイントは、「正直さ」と「誠実な協力」に尽きます。
まずは、自らの行為(浪費、偏頗弁済、財産隠しの疑いなど)について、早い段階で弁護士などの専門家へ正直に相談してください。
弁護士には守秘義務があります。
「こんなことを話したら怒られるのではないか」「不利になるのではないか」と恐れず、すべてを話してください。
弁護士は、その不利な情報を前提として、どうすれば裁量免責を得られるか、破産管財人にどう説明すべきか、という最善の対策を一緒に考えます。
特に、裁量免責を狙う場合は、反省や謝罪だけでなく、家計簿をつけるなど、経済的更生に向けた具体的な行動と再発防止策を示すことが極めて効果的です。
9. まとめ:免責不許可事由のリスクを避け、最善の債務整理を選択するために
免責不許可事由に該当する行為があると、自己破産をしても借金が免除されない可能性があります。
しかし、法律には「裁量免責」という救済の道も残されています。
重要なのは、破産法が求める誠実さと情報開示の原則をしっかり守り、反省と再発防止策を示すことです。
過去に破産したことがある場合や、浪費・賭博による借金など悪質性が疑われる場合でも、真摯な態度をとることで結果が変わる可能性は十分にあります。
万が一不許可となっても、即時抗告や個人再生、任意整理など別の選択肢があります。
免責不許可事由に該当するかもしれないと不安に思っている方ほど、自己判断で手続きを進めたり、あきらめたりするのは危険です。
スムーズな手続きと最善の解決のために、まずは弁護士にご相談ください。
古山綜合法律事務所では、自己破産手続きのサポートをおこなっています。
初回無料の法律相談では事情を丁寧にお伺いし、① 解決策のアドバイス、② 解決の見通し、③ 不安・疑問について個別のご質問に回答いたします。
借金問題の悩みは、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
なお、法律相談は事前予約制です。
電話、LINE、メールフォームからご予約・お問い合わせください。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。