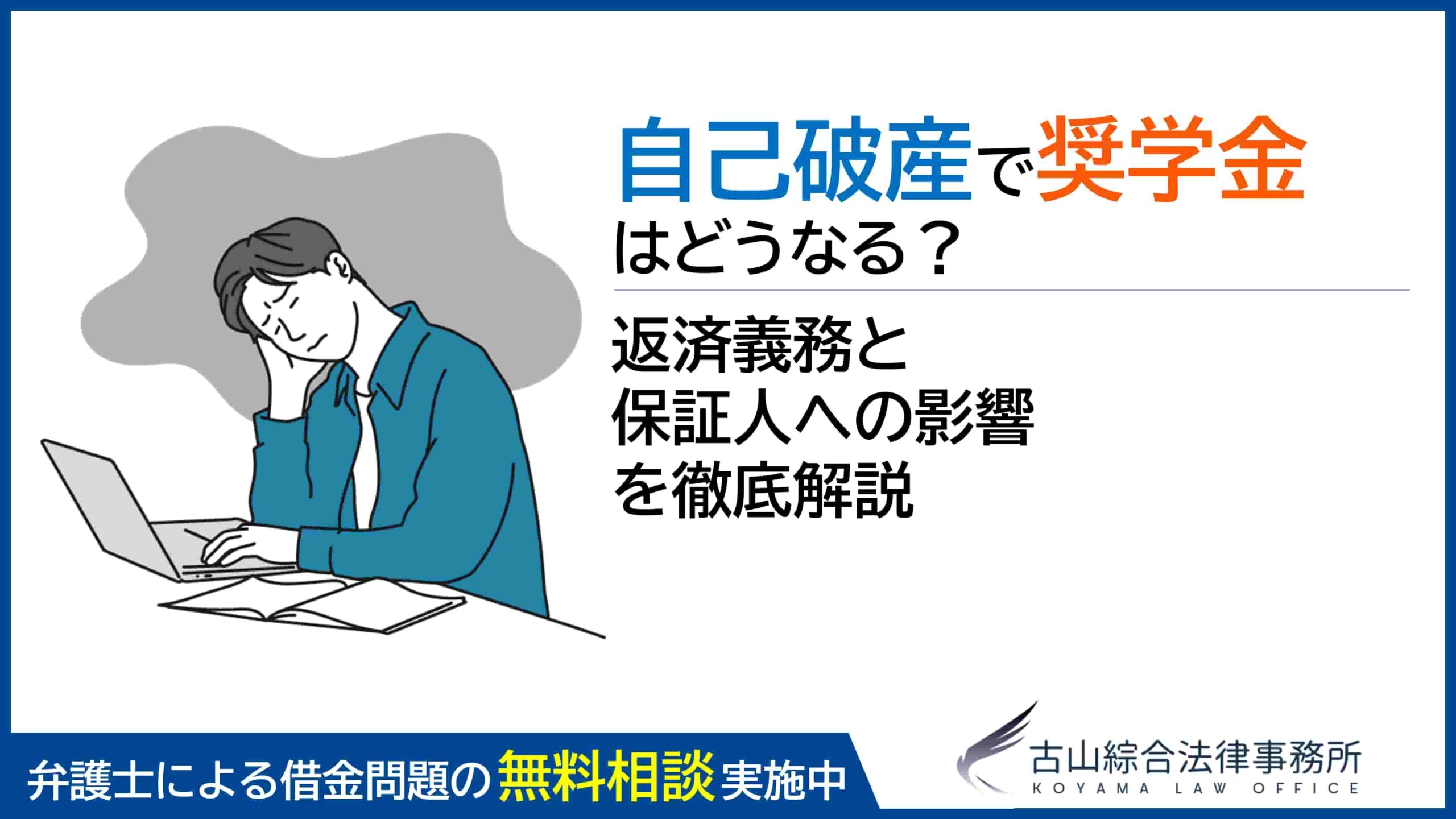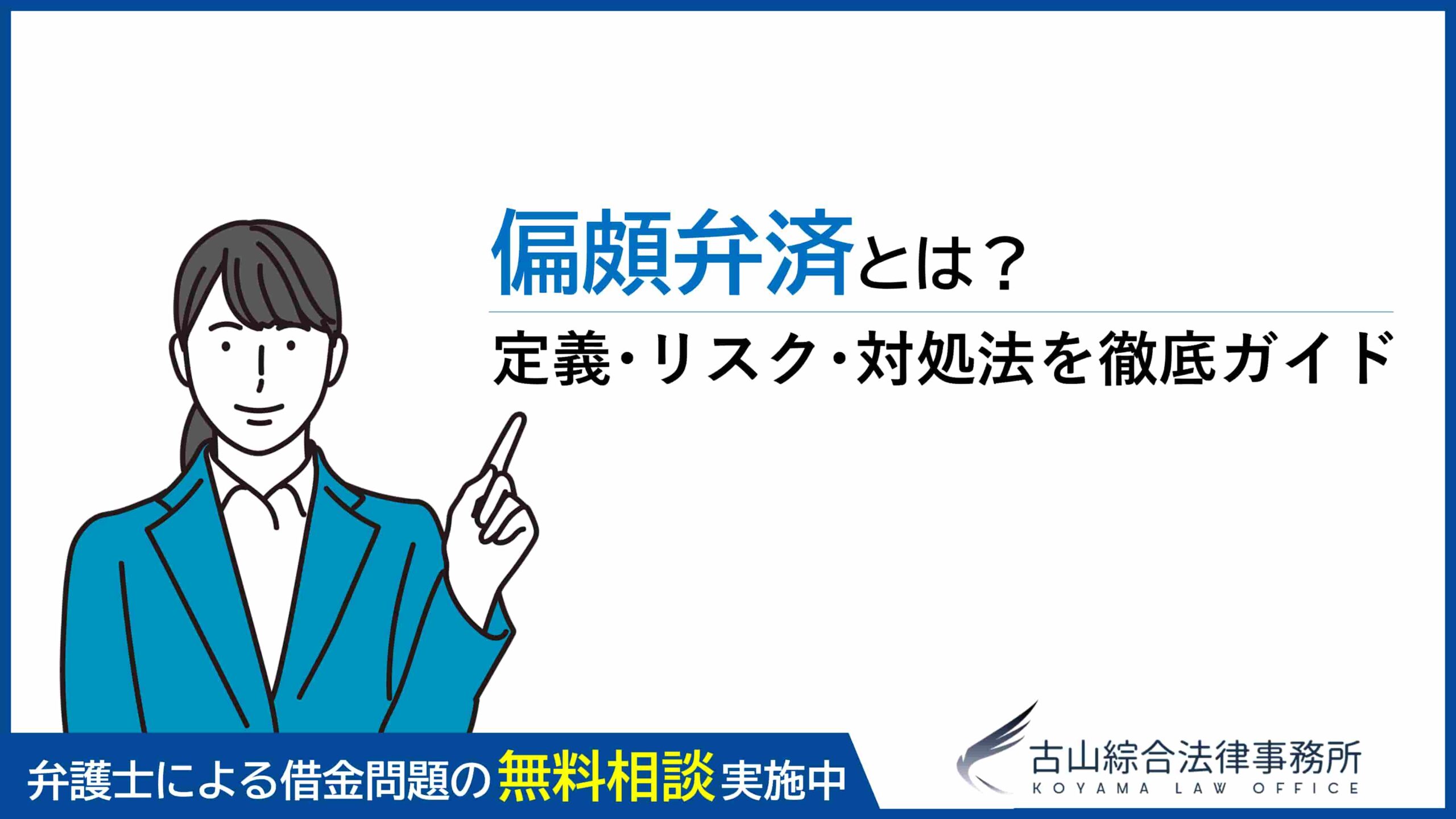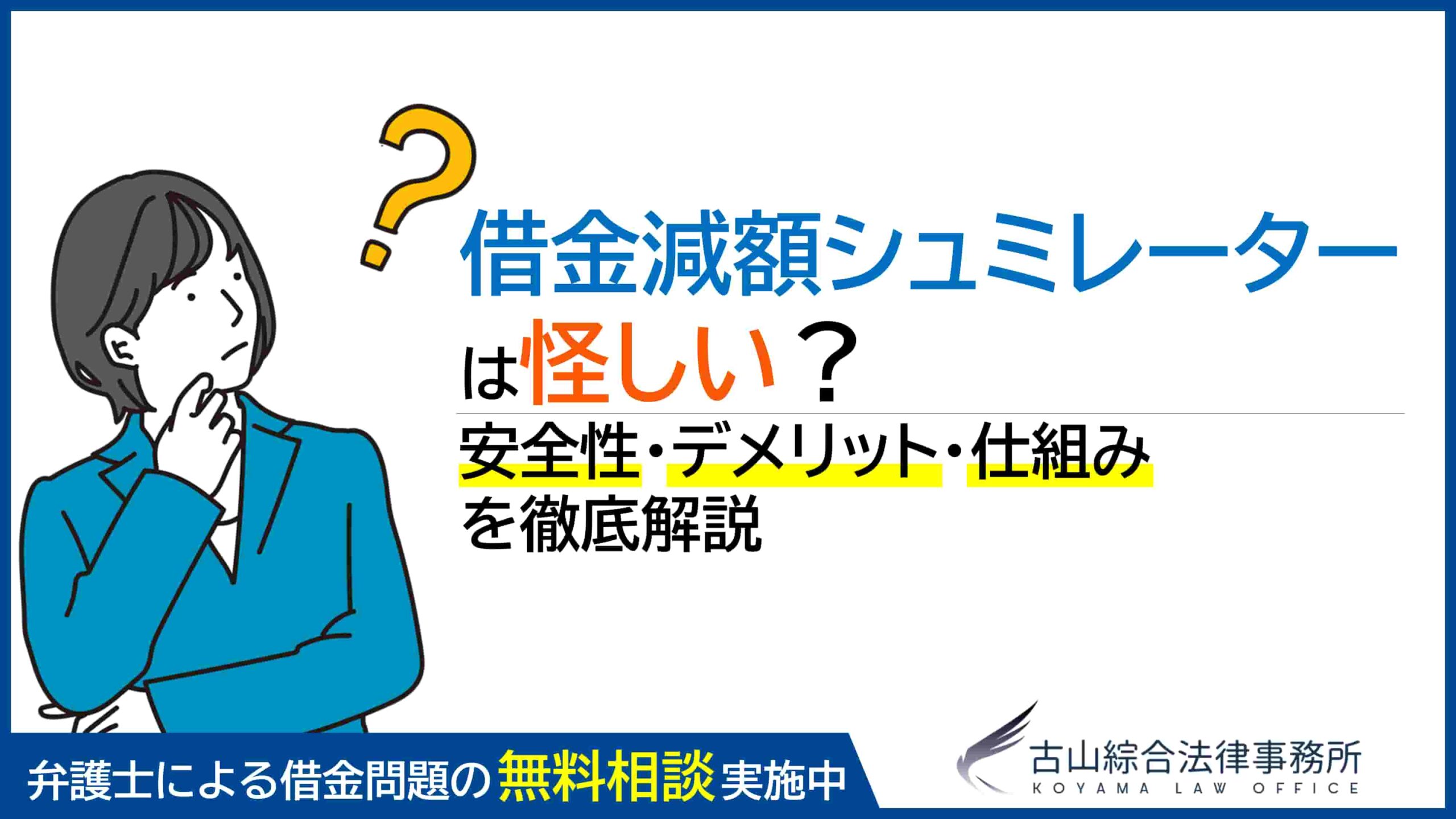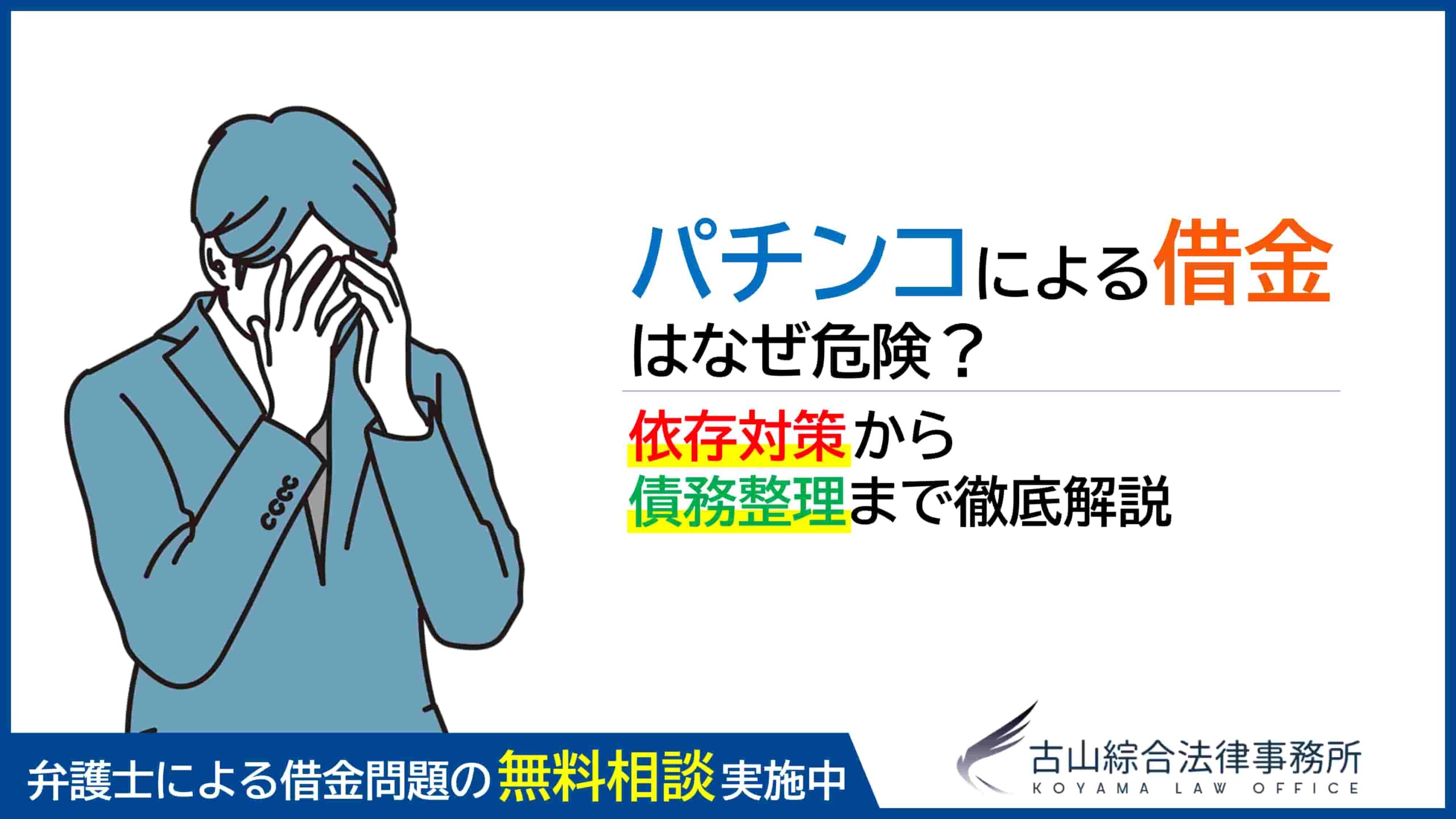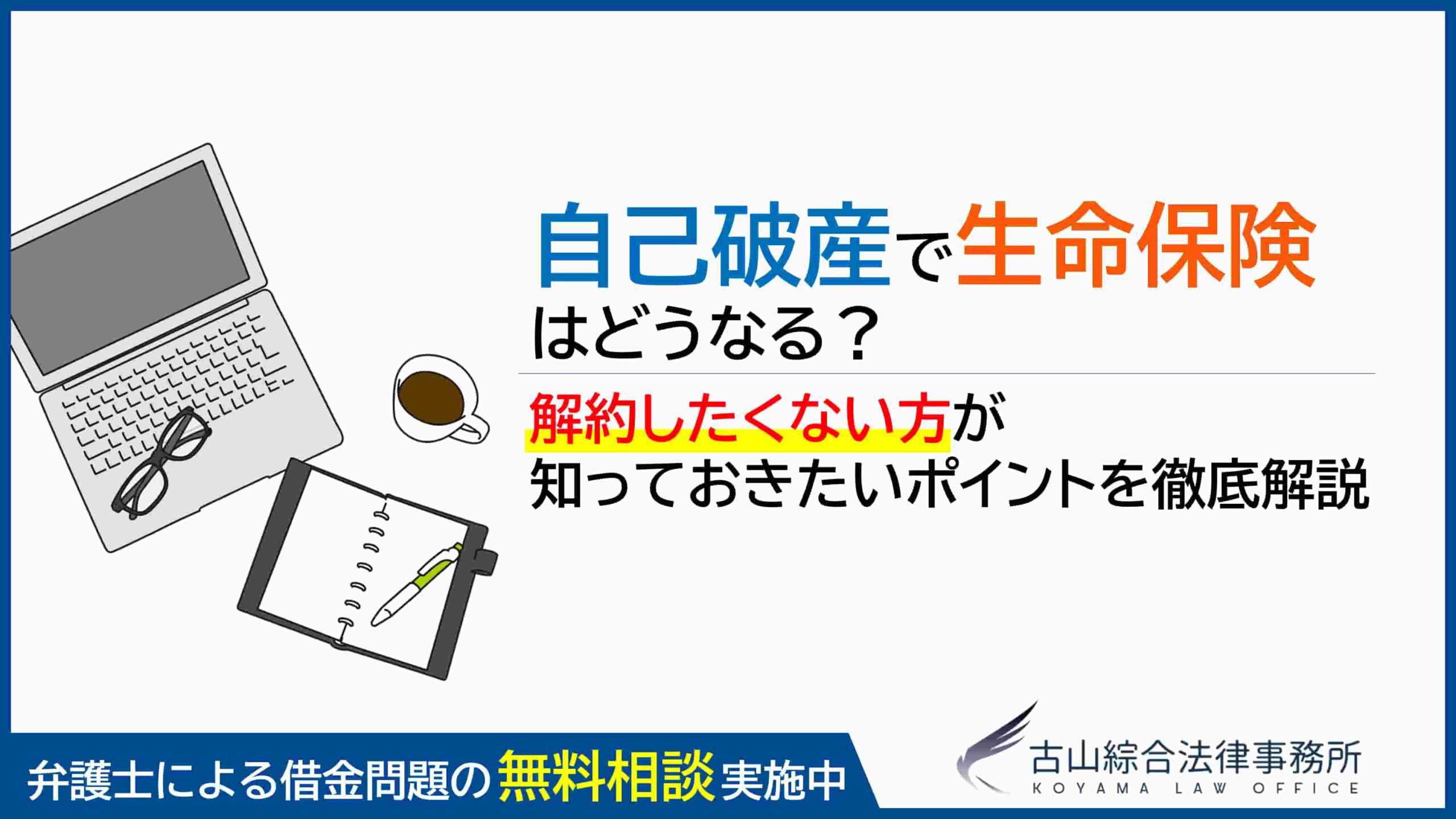自己破産の条件とは?手続きの流れから費用、生活への影響まで徹底解説
借金問題
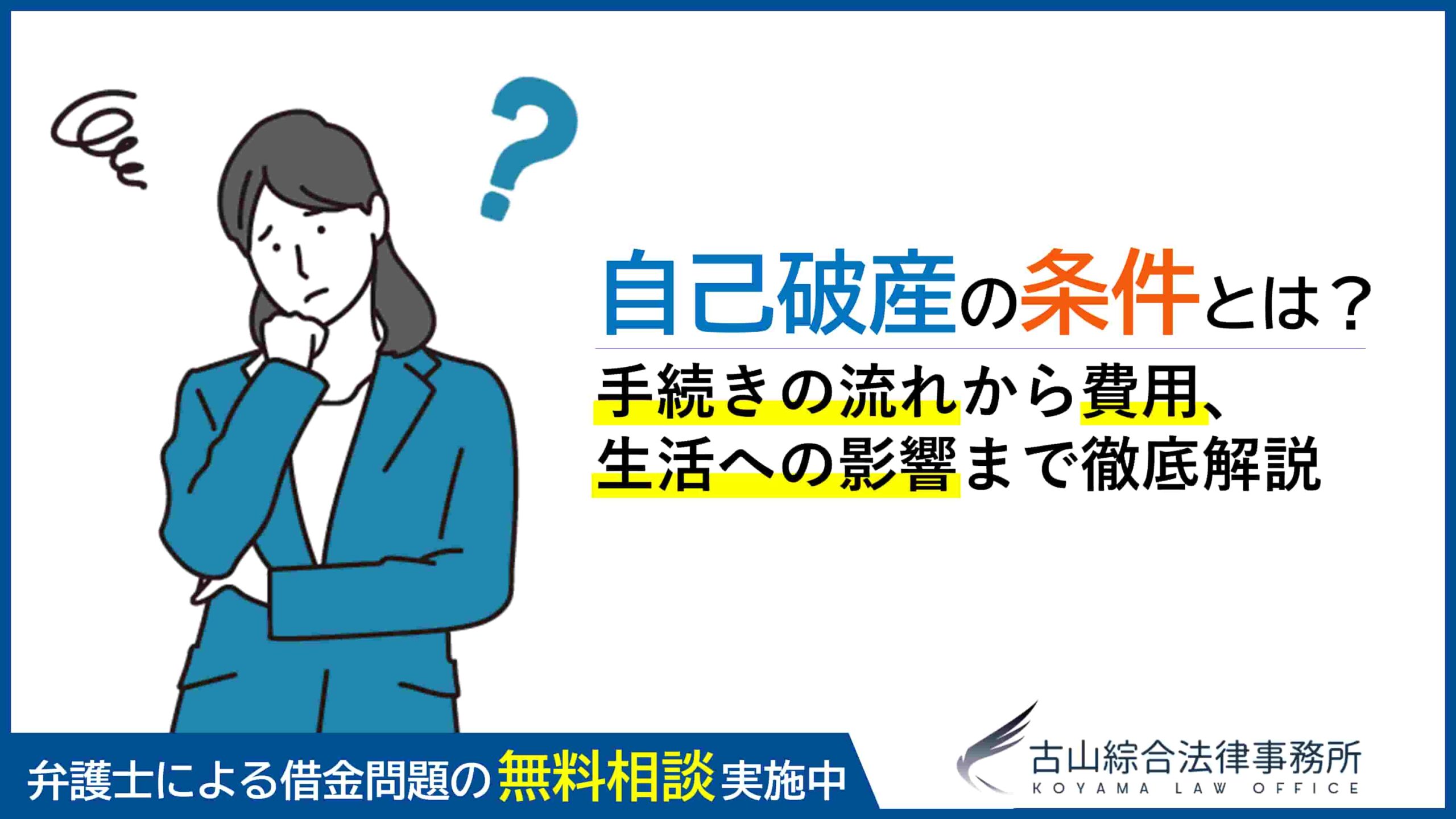
この記事の目次(クリックで開閉)
自己破産の条件とは?手続きの流れから費用、生活への影響まで徹底解説
多額の借金を抱え、「返済の目処が立たない…」「この苦しい状況から抜け出したい…」と深刻に悩んでいませんか?
法的に借金の支払義務を免除してもらうことで、人生の再スタートを可能にする制度が「自己破産」です。
この記事では、自己破産を検討しているあなたが適切な判断を下せるよう、以下の点について、わかりやすく解説します。
- 自己破産が認められるための具体的な「条件」
- 自己破産できないケースや、その場合の対処法
- 自己破産で免除されないもの
借金問題の解決には、まず正確な知識を得ることが第一歩です。
この記事を最後までお読みいただくことで、自己破産に関する漠然とした不安が解消され、ご自身の状況を把握し、生活を立て直すための一歩を踏み出すことができるはずです。
1. 自己破産の基本知識
自己破産とは、裁判所に申し立てて「免責許可決定」を受けることで、原則としてすべての借金の支払い義務を免除してもらう法的な手続きです。
これは、破産法という法律で認められた、債務に苦しむ個人の経済生活の再生を図るための正当な権利(破産法第1条参照)であり、決して特別なことではありません。
申立後、債権者に対して、債務者の財産を公平に分配する手続き(破産手続)を経た上で、生活再建の機会を与えることになります。
ただし、生活再建に必要な範囲での財産は保有することができ、処分の対象にはなりません。
裁判所から免責許可決定が確定すれば、消費者金融からの借入れやクレジットカードの支払い、銀行のローンなどの借金は、返済義務がなくなります。
これにより、債権者からの厳しい取り立ては止まり、精神的なプレッシャーから解放され、収入を生活の再建のために使えるようになります。
ただし、自己破産には財産の処分や一定期間の職業制限、新たな借り入れやクレジットカードの契約が困難になるといったデメリットも伴います。
また、税金や養育費など、一部免除されない債務(非免責債権)も存在するため、制度を正しく理解することが極めて重要です。
こうした自己破産によるメリット、デメリットについては次の関連記事でくわしく解説しています。
1-1. 手続の種類(同時廃止・管財手続)
自己破産の手続きは、申立人の財産状況によって主に以下の3つの種類に分けられます。
どの手続きになるかによって、費用や期間が大きく異なるため、非常に重要なポイントです。
自己破産の手続き種類の比較
| 手続きの種類 | 対象となるケース | 期間の目安 | 費用の目安 (予納金) |
特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 同時廃止事件 | 債権者に分配できるほどの財産(目安として20万円以上の価値がある財産)がない場合 | 約3〜6ヶ月 | 1〜3万円程度 | 最もシンプルで、費用・期間の負担が少ない。 個人の自己破産では、この手続きが適用されることが多いです。 |
| 少額管財事件 | 一定の財産がある場合、弁護士が代理人になっている場合、または免責不許可事由の調査が必要な場合(※個人の場合) | 約6ヶ月〜1年 | 20万円〜 | 裁判所が選任した破産管財人が財産の調査・管理・処分をおこないます。同時廃止より手続きは複雑です。 |
| 通常管財事件 | 債務額が大きい、財産関係が複雑など、調査に時間と手間がかかる場合(※主に法人の破産) | 1年以上 | 50万円〜 | 最も複雑で、費用・期間の負担が大きい。個人の申立てで適用されることはほとんどありません。 |
「同時廃止」とは、破産手続の開始決定と同時に、財産を換価・配当する手続きをおこなわずに破産手続を終了(廃止)させる手続きです。
これは、そもそも配当する財産がない場合に、無駄な手続きを省くためのものです。
一方、「管財手続」は、破産管財人が選任され、債務者の財産を調査・管理し、現金化(処分)して債権者に公平に分配(配当)する手続きです。
一定以上の価値がある財産を所有している場合や、借金の原因がギャンブルや浪費であるため免責を認めてよいか調査が必要な場合(免責不許可事由の調査)などに適用されます。
どちらの手続きになるかは、最終的に裁判所が申立書や添付書類の内容を審査して判断します。
2. 自己破産ができる4つの条件
自己破産は、単に「借金が返せない」という自己申告だけで認められるものではありません。
法律(破産法)に基づき、裁判所が客観的な基準で判断するための、大きく分けて2つの段階の「条件」があります。
- 破産手続を開始してもらうための条件
- 最終的に借金の支払義務を免除(免責)してもらうための条件
これらを総合的に満たして初めて、自己破産という目的を達成できます。
ここでは、この2つの条件を満たすために重要な4つのポイントについて詳しく解説します。
2-1. ポイント1:支払不能状態であること
自己破産手続きを開始するための最も重要な条件は、「支払不能」であることです(破産法第15条1項)。
支払不能とは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態」を指します(破産法第2条11項)。
簡単に言えば、「財産、収入のいずれをもってしても、すべての借金を返済し続けることが客観的に見て不可能な状態」ということです。
裁判所は、以下の要素を総合的にふまえて支払不能かどうかを判断します。
- 債務の総額と内容
- 収入(月収、年収、安定性など)
- 保有している財産の価値(預貯金、不動産、生命保険など)
- 今後の収入見込み
法律上、明確に「借金がいくら以上なら支払不能」という基準はありません。
実務上は「債務総額を3年(36回)で分割返済できない」ことが一つの目安とされています。
例えば、借金が300万円ある場合、月々約8万円の返済を3年間継続できなければ、支払不能と判断される可能性が高いでしょう。
この状態を裁判所に認めてもらうためには、給与明細、預金通帳、家計簿、債権者一覧表などの客観的な資料を提出し、支払能力がないことを具体的に説明する必要があります。
2-2. ポイント2:免責不許可事由に該当しないこと
自己破産を申し立てる最終目的は、借金の支払義務を免除してもらう「免責許可決定」を得ることです。
しかし、破産法には「免責不許可事由」が定められています。
これに該当する行為があると、原則として免責は認められません(破産法第252条1項)。
これは、不誠実な債務者まで安易に救済することを防ぎ、制度の公正さを保つための規定です。
代表的な免責不許可事由には、以下のようなものがあります。
参照 免責不許可事由の例
- ギャンブルや浪費(過度な買い物、飲食など)が原因で多額の借金を作った場合
- 財産を意図的に隠したり、壊したり、不当に安く処分した場合
- 特定の債権者だけにかたよって返済した場合(偏頗弁済:へんぱべんさい)
- クレジットカードで商品を購入し、すぐに現金化する行為(換金行為)
- 裁判所に虚偽の書類を提出したり、嘘の説明をしたりした場合
ただし、これらの事由に該当したからといって直ちに自己破産が不可能になるわけではありません。
裁判所の裁量(判断)によって免責が許可される「裁量免責(さいりょうめんせき)」という制度があります。
これについては後でくわしく解説します。
2-3. ポイント3:債務の大部分が非免責債権ではないこと
自己破産をしても、その性質上、支払義務が免除されない債務があります。
これを「非免責債権(ひめんせきさいけん)」と呼びます(破産法第253条1項)。
代表的な非免責債権は以下の通りです。
参照 非免責債権の例
- 税金、国民健康保険料、年金保険料など
- 養育費や婚姻費用
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
(例:お金をだまし取ったことに対する賠償金の支払い) - 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
(例:飲酒運転による人身事故の賠償金) - 罰金、科料など
もし、抱えている債務のほとんどがこれらの非免責債権である場合、自己破産をしても借金問題は解決しません。
そのため、裁判所は申立ての目的がないとして、手続きを認めない可能性があります。
2-4. ポイント4:予納金や手数料を納付できること
自己破産の申立てには、裁判所に予納金(手続きを進めるための実費)や手数料(収入印紙代、郵便切手代など)を納付する必要があります。
これらの費用を支払えなければ、手続きを開始することができません。
費用の金額は、先述した手続きの種類(同時廃止か管財事件か)によって大きく異なります。
参照 裁判所の予納金の目安
- 同時廃止事件の場合
合計で1〜5万円程度 - 管財事件の場合
20万円以上(破産管財人への報酬が含まれるため高額になる)
「自己破産を考えるほどお金に困っているのに、費用を払えるのか」と不安に思うかもしれません。
しかし、弁護士に依頼した場合、弁護士費用の分割払いに応じてくれる事務所がほとんどです。
また、弁護士が債権者に受任通知を送付すると借金の返済や取り立てが一旦ストップするため、その間に返済にあてていた金額を費用の積み立てにあてることが可能になります。
資力がない場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで弁護士費用を立て替えてもらう方法もあります。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
3. 自己破産できないケースとその理由
「自己破産ができる4つの条件」を満たさない場合、手続きを進めることができません。
ここでは、具体的にどのような場合に自己破産が認められにくいのか、その理由と対処法を見ていきましょう。
3-1. 借金が少額で支払不能と認められない場合
債務総額が比較的少なく、あなたの収入や資産状況からみて「分割すれば返済可能」と裁判所に判断された場合、「支払不能」とは認められず、自己破産の申立てが棄却されることがあります。
このようなケースでは、自己破産ではなく、将来の利息をカットしてもらい元本を3〜5年で分割返済していく「任意整理」といった、他の債務整理手続きが適切な解決策となる場合があります。
ご自身にとって最適な解決方法を、事前に弁護士に相談をして確認しておくとよいでしょう。
3-2. ギャンブルや浪費による多額の債務
パチンコや競馬などのギャンブル、あるいは収入に見合わないブランド品の購入や高額な飲食といった浪費が原因で多額の借金を作った場合は、免責不許可事由(破産法第252条1項4号)に該当します。
自己破産は経済的に破綻した人の救済が目的ですが、自ら招いた側面が強い原因については厳しい判断がなされます。
ただし、前述の通り、これが原因だからといって即座に免責が不許可になるわけではありません。
裁判所は、借金に至った経緯や本人の反省の程度、更生の意欲などを考慮し、破産管財人の調査を経た上で「裁量免責」を認めることがあります。
手続きや裁判所への誠実な対応が極めて重要になります。
3-3. 過去7年以内に自己破産における免責を受けている場合
過去に自己破産をして免責許可決定を受けている場合、そこから7年間は、原則として再び免責許可を得ることはできません(破産法第252条1項10号イ)。
これは、自己破産制度の濫用を防ぐための規定です。
ただし、2回目の破産がやむを得ない事情(病気や失業、災害など)によるものであると裁判所が判断した場合には、7年以内であっても例外的に裁量免責が認められる可能性はあります。
3-4. 予納金の未納や不誠実な申立て
裁判所に納める予納金が支払えなければ、手続きは開始されません。
また、手続きの過程で、財産を隠したり(財産隠匿;ざいさんいんとく)、借金の状況について虚偽の説明をしたり、特定の債権者にだけ返済したりといった不誠実な行為が発覚した場合も、免責不許可事由に該当し、免責が認められない可能性が非常に高くなります。
不誠実な態度は、経済的再生の意思がないとみなされ、厳しい結果を招くことになります。
4. 免責不許可事由の具体例と裁量免責
免責不許可事由に該当する行為があっても、「裁量免責」により最終的には免責が許可されるケースがあります。
ここでは、免責不許可事由の具体的な内容と、裁量免責を得るためのポイントを解説します。
4-1. 主な免責不許可事由の事例(浪費・ギャンブル・財産隠匿など)
破産法第252条1項には、11項目の免責不許可事由が定められています。
ここで少しまとめて確認しておきましょう。
参照 免責不許可事由(破産法252条)
- 財産隠匿・不利益処分(1号)
財産を隠したり、不当に安く売り払ったりする行為。 - 換金行為(2号)
クレジットカードのショッピング枠で商品を購入し、それをすぐに業者に売却して現金を得る行為。 - 偏頗弁済(へんぱべんさい)(3号)
親族や友人など、特定の債権者にだけ優先的に返済する行為。 - 浪費・賭博(4号)
ギャンブルや過度なショッピング、飲食などが原因で著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担した行為。 - 詐術による信用取引(5号)
返済能力がないことを隠して新たに借り入れをおこなったり、クレジットカードで商品を購入したりした場合。 - 説明義務違反・虚偽説明(8号)
裁判所や破産管財人からの調査に対し、説明を拒んだり、虚偽の説明をしたりする行為。 - 7年以内の再度の免責申立て(10号)
4-2. 裁量免責が認められるためのポイント
免責不許可事由がある場合、手続きは「管財事件」となり、破産管財人が選任されます。
裁量免責を得るためには、この破産管財人と裁判所に対して、いかに誠実に対応し、反省の態度を示すかが鍵となります。
- 事実を正直に話す
借金の原因や財産状況について、隠したり嘘をついたりせず、全て正直に説明する。 - 破産管財人の調査に全面的に協力する
管財人からの指示や要請には迅速かつ誠実に応じる。
財産に関する資料の提出や面談には真摯な態度で臨む。
例えば、浪費が原因の場合には、一定の金額を積み立てて債権者への配当をするように破産管財人から指示を受けることがあります。
きちんと対応することが、免責を得るための好材料の一つとなります。 - 深く反省し、更生の意欲を示す
なぜ借金が増えてしまったのかを真摯に反省し、今後は家計をきちんと管理し、経済的に再生していくという強い意欲を態度や書面(反省文など)で示す。
例えば、ギャンブル依存症による借金は、治療に通っていることなど更生に向けた行動をとることなどが挙げられます。 - 手続きを弁護士に依頼する
弁護士は、破産管財人や裁判所とのやり取りを円滑に進め、どのように対応すれば裁量免責を得やすいかを熟知しています。
専門家のサポートは極めて有効です。
5. 自己破産で免除されない債務(非免責債権)
自己破産で免責許可決定が確定しても、支払義務がなくならない「非免責債権」が存在します。
これらを滞納している場合、自己破産後も支払いを続けなければならないため、注意が必要です。
5-1. 税金・養育費・罰金など免責されない例
破産法第253条1項で定められている主な非免責債権は以下の通りです。
これらは、公益性や人道的な観点から、個人の経済状況とは別に支払うべき義務とされています。
参照 非免責債権(破産法第253条)
- 租税等の請求権(1号)
所得税、住民税、固定資産税などの税金、国民健康保険料、年金保険料など。 - 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(2号)
他人を害する意図をもって行った行為(暴力、窃盗、詐欺など)による損害賠償金。 - 故意または重過失による生命・身体の侵害に対する損害賠償請求権(3号)
飲酒運転や危険運転による人身事故の慰謝料など、重大な過失による損害賠償金。 - 養育費など扶養義務に関する請求権(4号)
親族間の扶養義務(子の養育費、夫婦間の婚姻費用など)に関するもの。 - 雇用関係に基づく使用人の請求権など(5号)
従業員の給料など。 - 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(6号)
意図的に申告しなかった債権者への借金。 - 罰金等の請求権(7号)
交通違反の反則金や刑事事件の罰金など。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
6. 自己破産後の生活に関するよくある質問
自己破産の手続きが無事に終わった後、生活はどう変わるのか、多くの方が不安に感じています。ここでは、よくある質問にお答えします。
Q1. クレジットカードはいつから作れますか?
A1. 信用情報機関から事故情報が削除された後であれば、新たに作成できる可能性があります。
事故情報の登録期間は機関によって異なりますが、免責許可決定の確定からおおむね5年〜10年が目安です。
ただし、最終的な審査はカード会社の判断によります。
自己破産時に借り入れの無かった銀行や信販会社、カード会社でも審査が通らない可能性はあります。
例えば、自己破産後にクレジットカードやローンを一度も利用することができないため、信用情報機関に利用履歴(クレジットヒストリー)がまったくない状態(スーパーホワイト)になります。
クレジットカード会社や金融機関が審査を行う際、信用情報機関に照会して申込者の情報を確認します。
この時、情報が全くない「スーパーホワイト」の人と、金融事故を起こした後に期間が経過して情報が消えた「ホワイト」の人を、信用情報上では区別することができません。
そのため、年齢が高いにもかかわらず信用情報がまっさらな場合、「過去に金融事故を起こしたのではないか?」と疑われ、審査に不利になる可能性があります。
なお、これらの審査基準は公開されていないため、弁護士にお問い合わせいただいても、審査に通らない具体的な理由を解明することはできません。
Q2. 賃貸アパートの契約はできますか?
A2. 基本的に可能です。
ただし、家賃保証会社が信販系(クレジットカード会社など)の場合、信用情報を照会するため審査に通らないことがあります。
物件を探す際に、信販系以外の保証会社を利用できるか不動産会社に確認すると良いでしょう。
Q3. 携帯電話の分割購入はできますか?
A3. 携帯電話本体の分割払いはローン契約の一種であるため、信用情報に事故情報が載っている期間は審査に通らない可能性が高いです。
現金一括払いでの購入を検討しましょう。
Q4. 家族に影響はありますか?離婚の原因になりますか?
A4. 法的には、自己破産が直接家族(配偶者や子供)に影響することはありません。
ただし、持ち家を失う、保証人に迷惑をかけるといった事態が、家族関係に影響を及ぼす可能性は否定できません。
借金問題を正直に話し合い、一緒に乗り越えていく姿勢が大切です。
自己破産そのものが法的な離婚事由になることはありません。
Q5. 選挙権はなくなりますか?
A5. なくなりません。
自己破産をしても、選挙権や被選挙権といった公民権が制限されることは一切ありません。
7. 自己破産を考えたら、まずは弁護士に相談
借金問題は一人で抱え込んでいると、精神的にも追い詰められ、正常な判断が難しくなってしまいます。
自己破産を少しでも検討しているのであれば、できるだけ早く債務整理を専門とする弁護士に相談することをおすすめします。
参照 弁護士に相談・依頼するメリット
- 最適な解決策を提案してくれる
あなたの状況をくわしく聞いた上で、自己破産がベストなのか、あるいは個人再生や任意整理といった他の方法が良いのか、専門的な視点からアドバイスしてくれます。 - 面倒で複雑な手続きを全て任せられる
大量の書類作成や裁判所とのやり取りなど、専門知識が必要な手続きを全て代行してくれます。 - 債権者からの取り立てが即日ストップする
弁護士が受任通知を送付した時点で、精神的な負担の大きい取り立てから解放されます。 - 裁量免責を得られる可能性が高まる
免責不許可事由がある場合でも、裁判所や破産管財人へ適切に説明し、円滑に手続きを進めることで、裁量免責を得られるよう最大限サポートしてくれます。
多くの法律事務所では、借金問題に関する相談は初回無料で行っています。
まずは相談するだけでも、現状を整理し、解決への道筋を見つける大きな一歩になります。
8. まとめ
自己破産は、返済不能な多額の借金を法的に解決し、人生を再スタートさせるための極めて有効な債務整理の手段です。
しかし、その利用には法律で定められた条件があり、メリットだけでなく、あなたの財産や家族、保証人に影響が及ぶデメリットも存在します。
本記事で解説した内容を参考に、ご自身の状況が自己破産の条件に当てはまるのか、そして自己破産という選択が本当にご自身にとって最善なのかを冷静に検討することが重要です。
借金問題の解決策は、自己破産だけではありません。
あなたの状況によっては、任意整理や個人再生といった他の方法が適している場合もあります。
どの手続きが最適かを個人で判断するのは非常に困難です。
一人で悩まず、まずは借金問題の専門家である弁護士にご相談ください。
専門家と共に、あなたの経済的な再生に向けた最も良い一歩を踏み出しましょう。
古山綜合法律事務所では、借金問題の初回無料相談をおこなっています。
ご事情を丁寧にお聞きし、あなたの状況に合わせた具体的な解決策をアドバイスいたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。