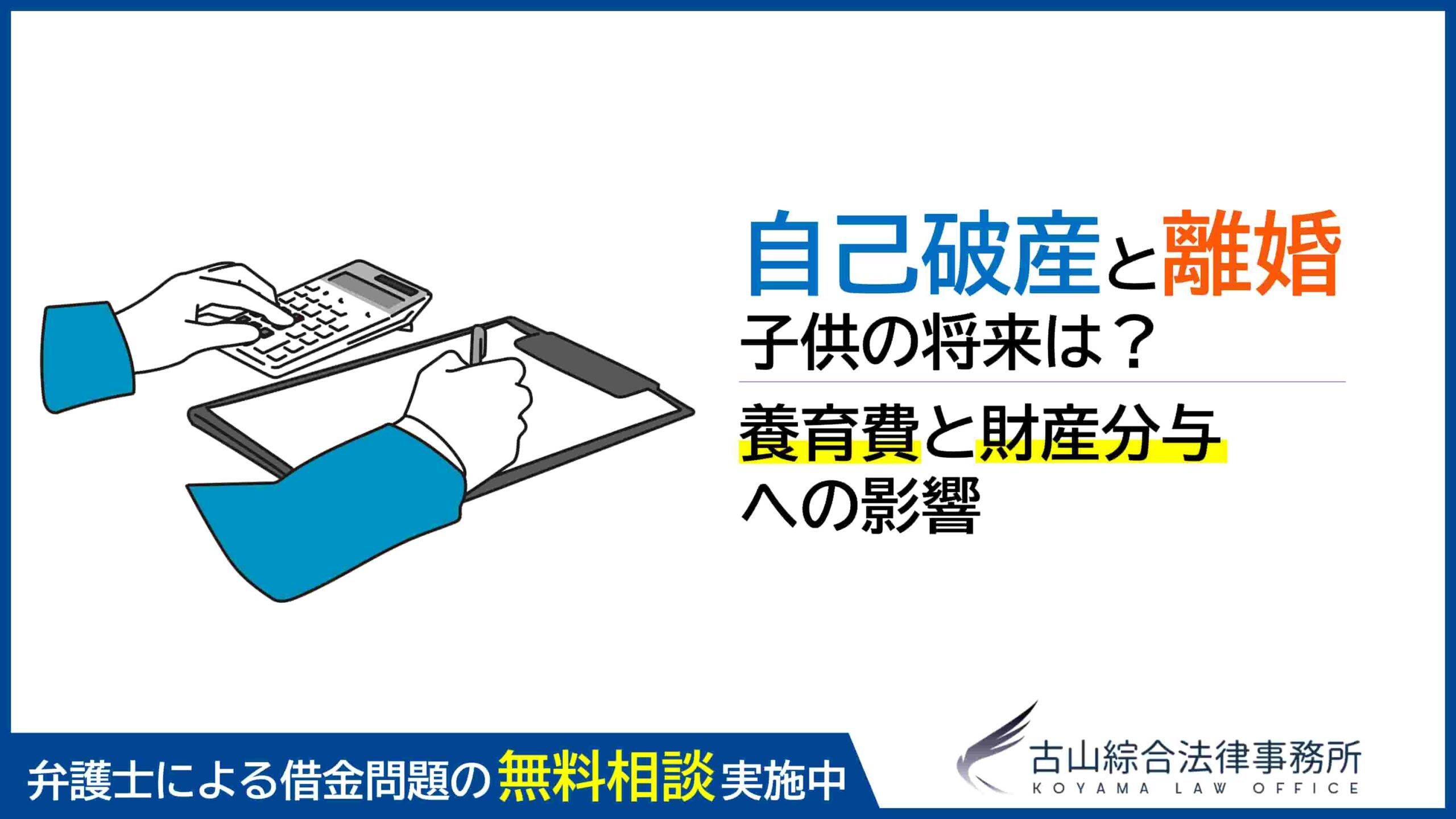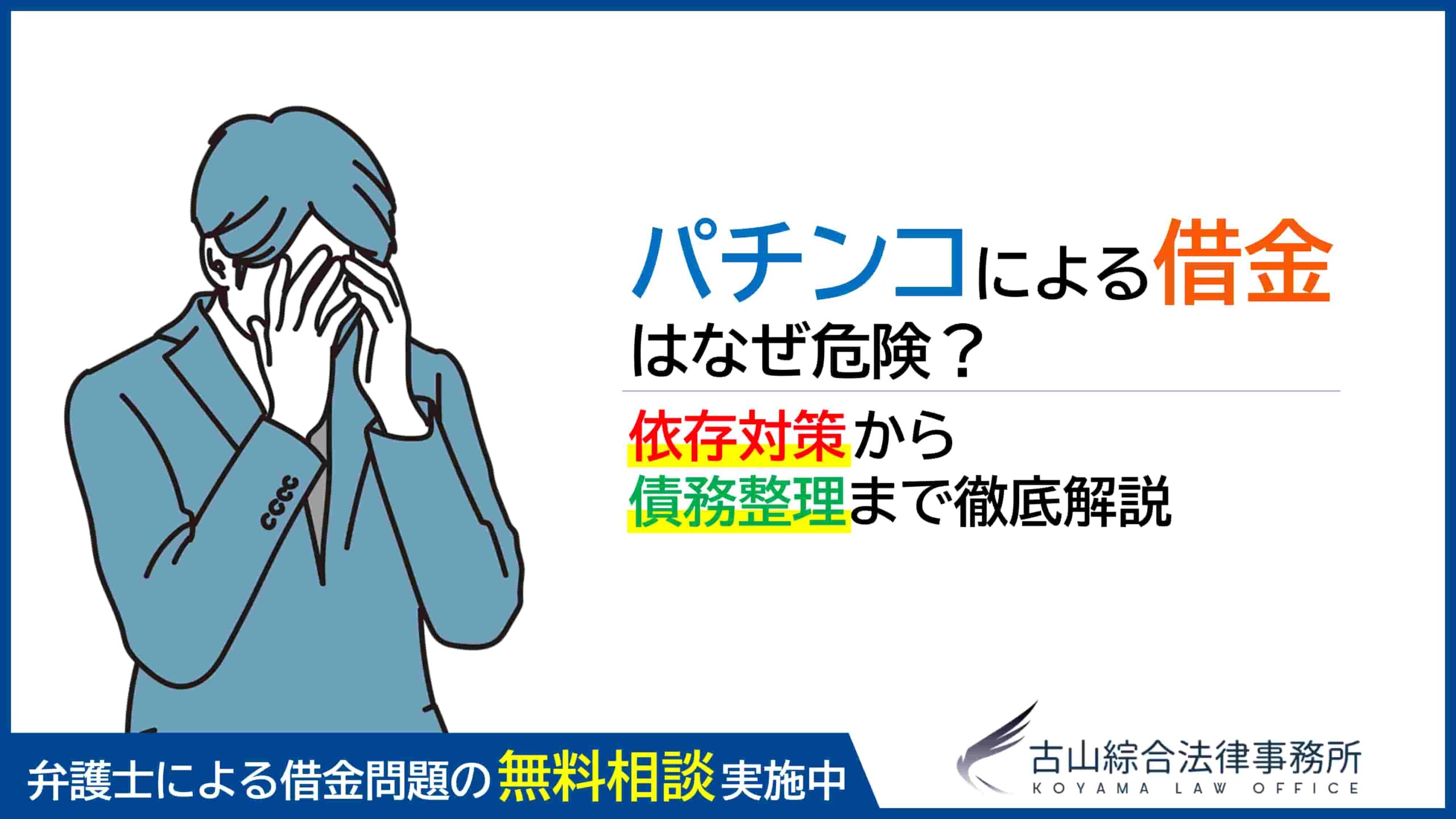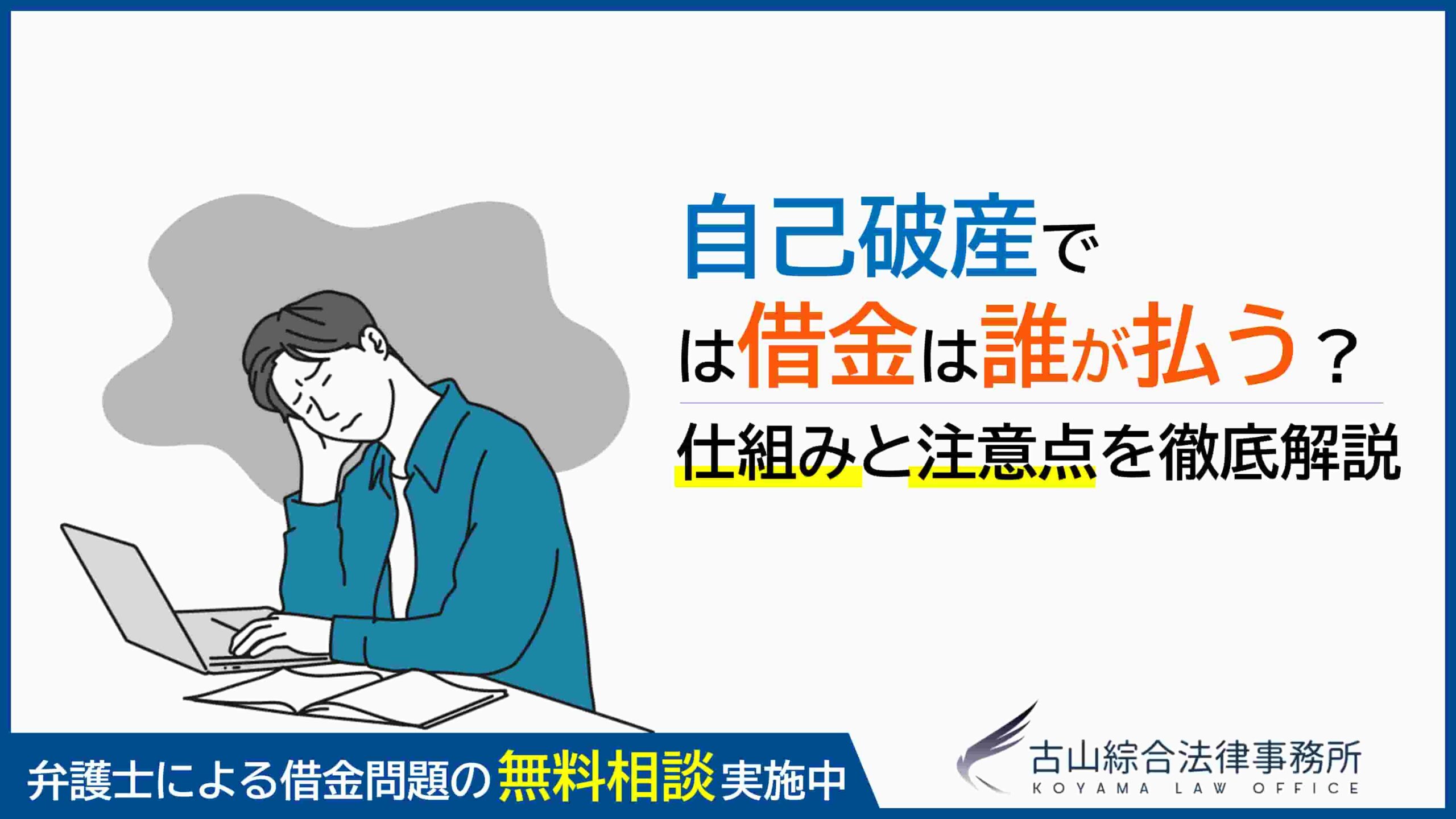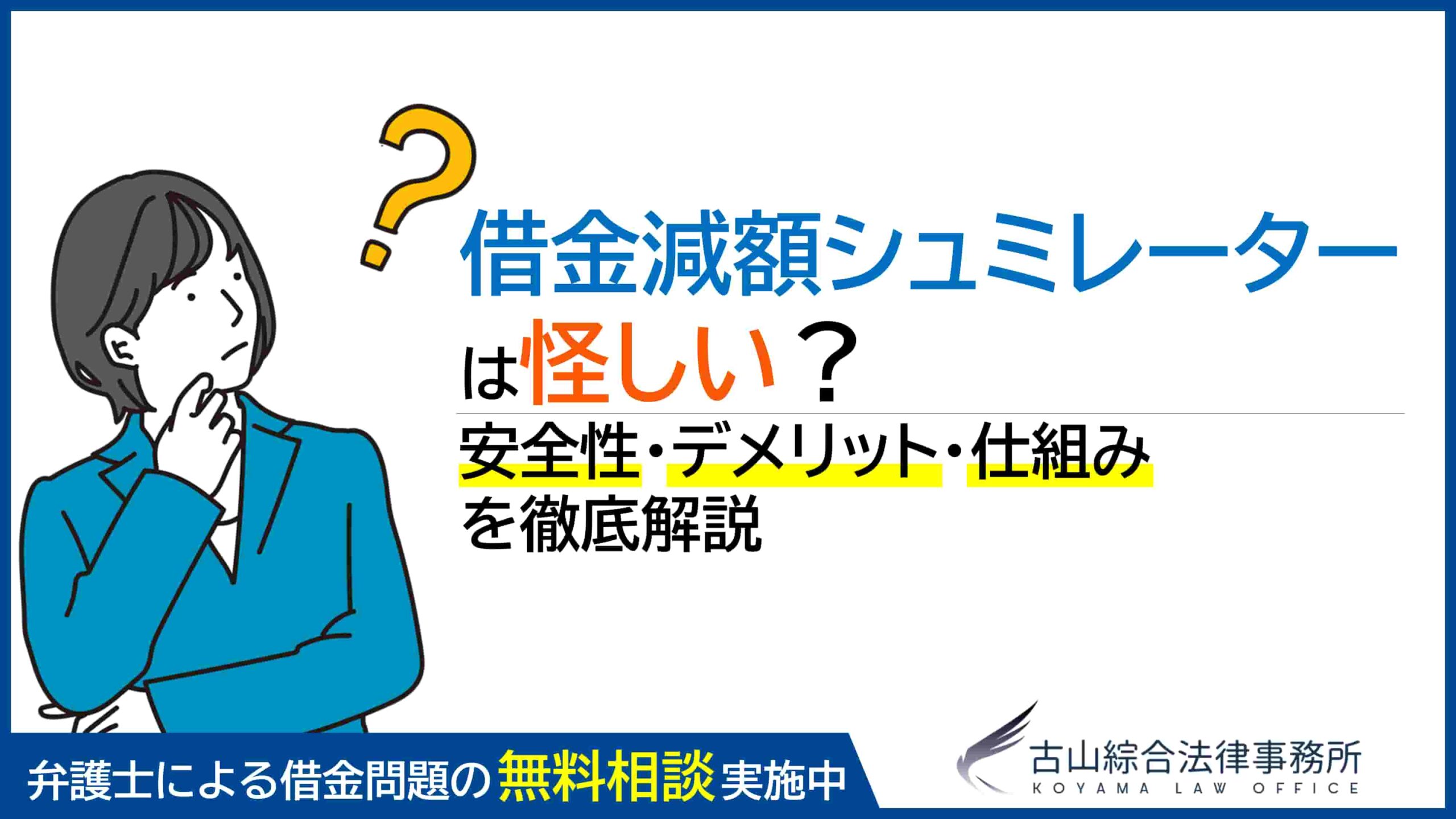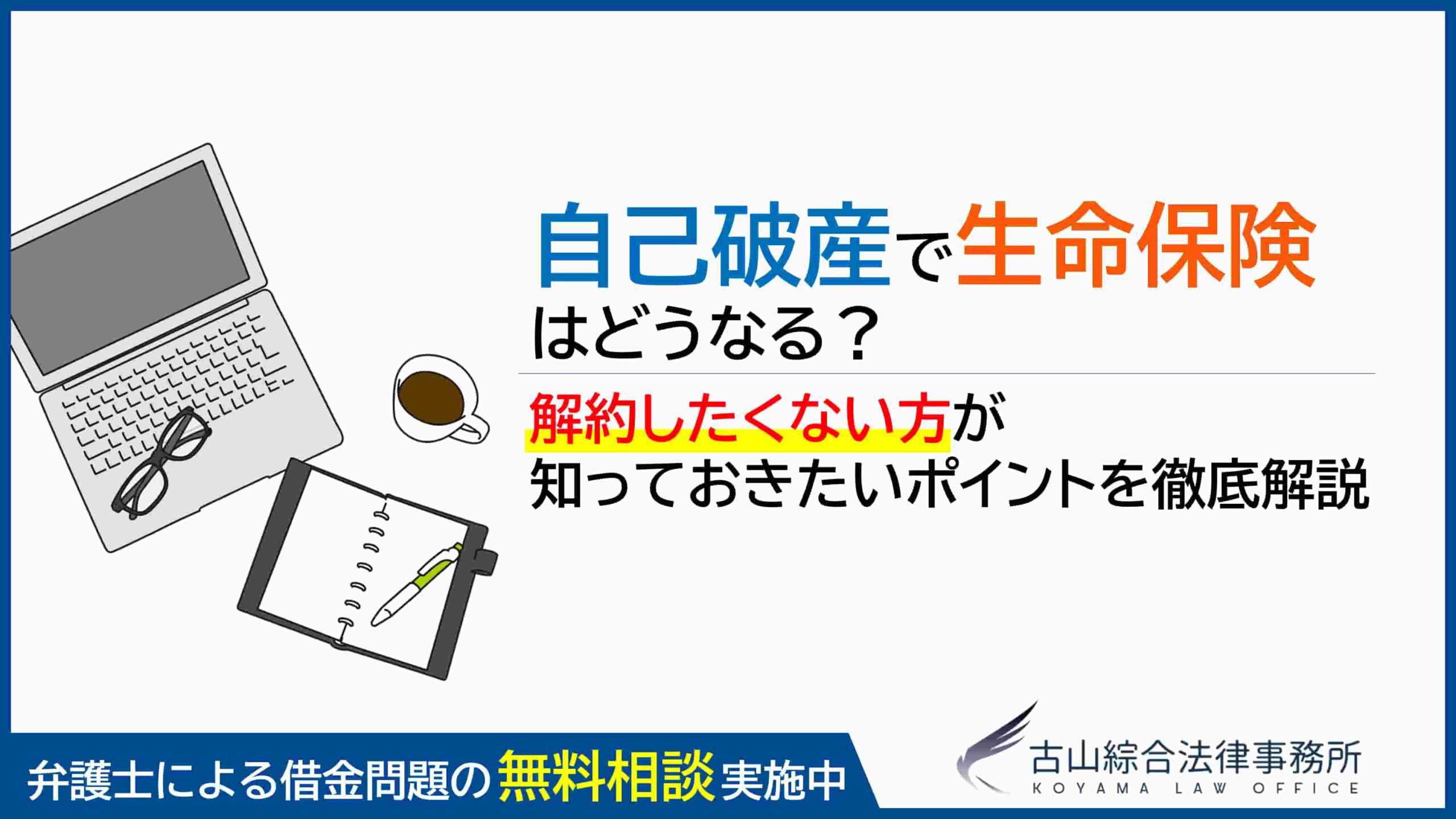自己破産で持ち家はどうなる?持ち家に住み続けるための対処法と基礎知識
借金問題
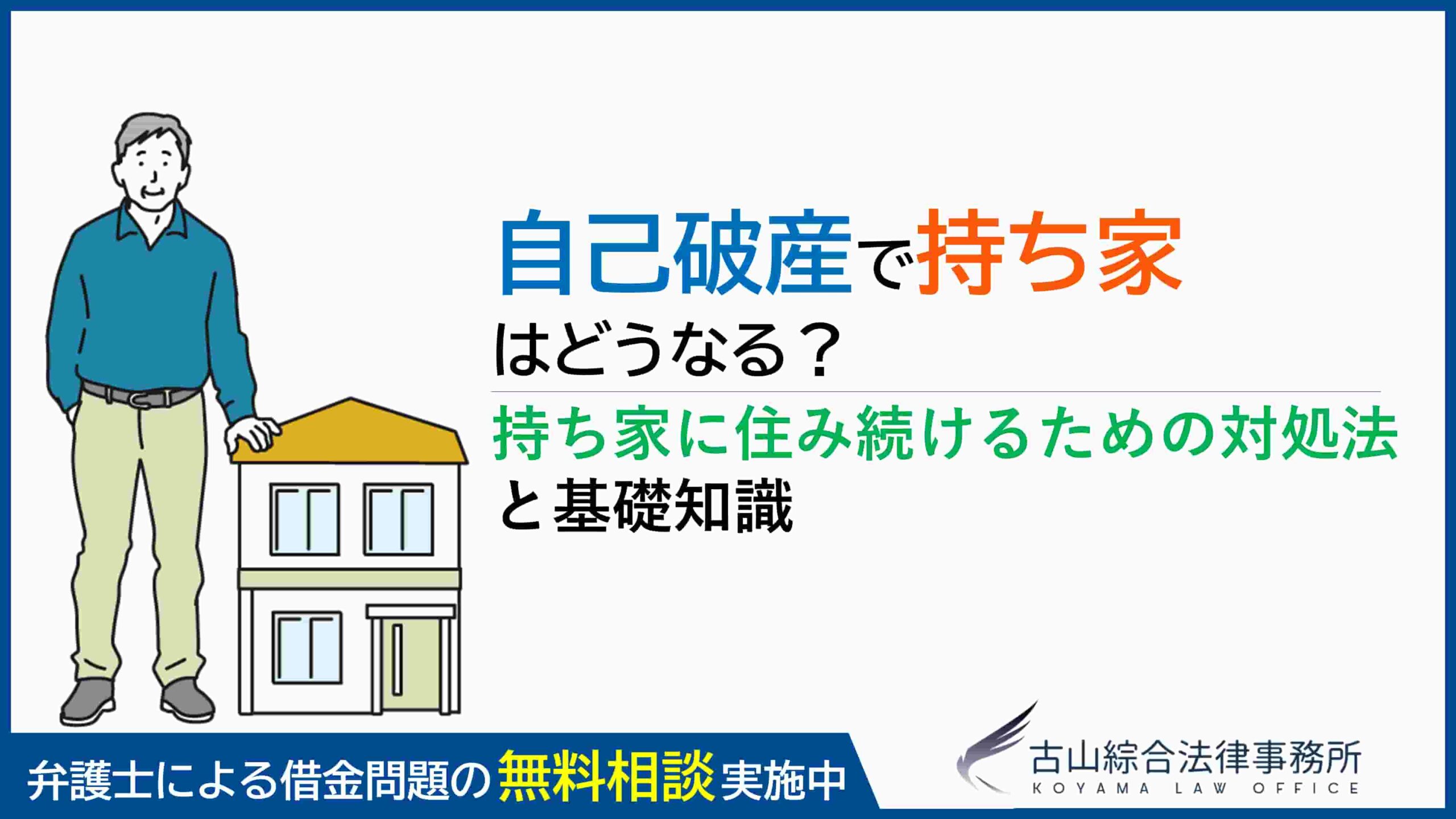
この記事の目次(クリックで開閉)
- 自己破産で持ち家はどうなる?持ち家に住み続けるための対処法と基礎知識
- 1. 自己破産で持ち家はどうなる?基本的な仕組み
- 1-1. 住宅ローンや抵当権との関係
- 1-2. 任意売却による処分
- 2. 競売と任意売却の流れ:自己破産後の持ち家の処分方法
- 2-1. 競売の手続きと注意点
- 2-2. 任意売却のメリット・デメリット
- 2-3. いつまで持ち家に住める?退去の時期の目安
- 借金問題の無料相談を実施中
- 3. 住宅ローンが残っている場合に押さえるポイント
- 3-1. アンダーローンとオーバーローンの違い
- 3-2. ペアローン・連帯保証人がいる場合の注意点
- 関連記事
- 4. 名義による扱いの違い:家族名義・共有名義・親族名義
- 4-1. 親や配偶者名義の持ち家に住み続けられるのか
- 4-2. 夫婦共有名義の場合の対処法
- 4-3. 離婚・相続時に名義変更を行う場合のリスク
- 5. 自己破産後も持ち家を残すための具体的な方法
- 5-1. 家族や親族が買い取るケース
- 5-2. リースバックを利用するメリットと注意点
- 5-3. 自由財産の拡張は使える?要件と手続き
- 借金問題の無料相談を実施中
- 6. 自己破産以外の債務整理:個人再生や任意整理を選ぶメリット
- 6-1. 個人再生の住宅ローン特則で持ち家を守る
- 関連記事
- 6-2. 任意整理で住宅ローンを対象外にする方法
- 7.自己破産後の住まい探し:賃貸契約や引っ越しのポイント
- 7-1.自己破産後でも賃貸物件は借りられる?
- 関連記事
- 7-2.保証会社の審査をクリアするための注意点
- 参照 保証会社の審査をクリアするためのポイント
- 8.まとめ
- 借金問題の無料相談を実施中
自己破産で持ち家はどうなる?持ち家に住み続けるための対処法と基礎知識
結論として、自己破産をすると、原則として持ち家は処分の対象となります。
しかし、正しい知識とタイミングで行動することで、「引越し費用の確保」や「住み続けられる可能性(リースバックなど)」、あるいは「自己破産以外の選択肢(個人再生)」といった生活再建の方法が見えてきます。
本記事では、自己破産における持ち家の扱いや、競売・任意売却の違い、家族への影響、家を守るための法的手段を説明します。
1. 自己破産で持ち家はどうなる?基本的な仕組み
自己破産を申し立て、免責(借金の返済義務の免除)を得るためには、原則として所有する一定以上の価値がある財産を処分し、債権者に配当する必要があります。
基本的に持ち家は高額な資産であり、処分の対象となります。
自己破産手続きにおいて、持ち家がある場合は原則として「管財事件」となり、裁判所から選任された破産管財人(弁護士)が財産の調査・管理・処分を行います。
ただし、家の処分方法は「住宅ローンの残額」や「抵当権の有無」によって異なります。
1-1. 住宅ローンや抵当権との関係
住宅ローンを借り入れしている場合、不動産には金融機関(銀行や保証会社)による担保権(抵当権など)が設定されているのが一般的です。
返済の滞納があったり、自己破産を申し立てると、住宅ローン会社は契約に基づき、残ったローンを回収するために競売手続の準備に入ります(別除権の実行;破産手続きによらず優先的に弁済を受ける権利を行使すること)。
1-2. 任意売却による処分
抵当権者である住宅ローン会社は、裁判所の競売手続きによらず、不動産を売却することがあります。
これを任意売却といいます。
債務者自身で買主を探して、住宅ローン会社の承諾を得て、売却をおこなうこともできます。
そのため、親族による買取り、不動産会社によるリースバック等の方法により、今の持ち家にそのまま住み続けられる可能性があります。
2. 競売と任意売却の流れ:自己破産後の持ち家の処分方法
自己破産に伴い家を手放す方法は、大きく分けて「競売(けいばい)」と「任意売却」の2つです。
両者には売却価格や退去条件において、以下のような大きな違いがあります。
| 項目 | 競売(けいばい) | 任意売却 |
|---|---|---|
| 主導者 | 裁判所・執行官 | 破産管財人・不動産業者 |
| 売却価格 | 市場価格の5〜7割程度 | 市場価格に近い金額 |
| プライバシー | インターネットや新聞で公開される | 通常の不動産売買と同様 |
| 引越し費用 | 原則出ない | 交渉次第で控除される可能性がある |
| 退去時期 | 落札後、強制執行の可能性あり | 買主との調整が可能 |
2-1. 競売の手続きと注意点
競売とは、債権者が裁判所に申し立て、強制的に不動産を売却する手続きです(民事執行法)。
競売が開始されると、「競売開始決定」の通知が届き、裁判所の執行官や不動産鑑定士による現況調査が行われます。
その後、物件情報がインターネット(BITなど)で公開され、入札が行われます。
自宅の外観写真や室内状況が公開されるため、近隣住民に事情を知られる可能性があります。
落札者(買受人)が決まり代金が納付されると、所有権が移転します。
その後も居座ると、最終的には強制執行により鍵を変えられ、荷物を運び出されてしまいます。
2-2. 任意売却のメリット・デメリット
任意売却とは、破産管財人(または債権者)の合意を得て、一般的な不動産市場で家を売却する方法です。
競売より高く売れるため、残る借金を減らせる可能性があります。
一般の物件として売りに出すため、周囲に「破産による売却」とはバレにくいです。
売却代金の中から、数十万円程度の引越し費用を捻出してもらえるよう管財人や債権者と交渉できる場合があります(必ずもらえるわけではありません)。
破産手続き中は管財人の業務遂行期間内に売却を完了させる必要があり、買い手が見つからなければ競売に移行します。
2-3. いつまで持ち家に住める?退去の時期の目安
一般的に、申立てから退去までの期間は半年〜1年程度が目安です。
競売の場合、入札から「売却許可決定」を経て代金納付までは数ヶ月かかります。
この期間中に少しでも現金を貯め、次の生活の準備をすることが重要です。
住み続けられます。
住み続けられますが、差押債権者である住宅ローン会社から内覧の申立てがあった場合には対応などが必要になることがあります。
所有権移転の時期に合わせて退去が必要です。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
3. 住宅ローンが残っている場合に押さえるポイント
住宅ローンが残っている場合、その残債額と家の価値のバランスが重要になります。
また、自分以外の誰かが契約に関わっている場合(連帯保証人など)、その人への影響も避けられません。
3-1. アンダーローンとオーバーローンの違い
アンダーローンとオーバーローンにより、自己破産手続きにおける対応が変わります。
所有財産として不動産がある場合、管財予納金(裁判所に納める費用)が高くなるため、不動産を任意売却で処分のうえ、破産申立てをおこなうことがあります。
ただし、適正価格で売却することや、住宅ローン会社との合意の取り付けなど、売却処分を進める上で注意すべき点があります。
なお、弁護士に自己破産手続きを依頼する場合、住宅ローン会社との交渉から、任意売却までを代行してもらうことができます。
持ち家がある場合の自己破産申立てを検討している場合、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
3-2. ペアローン・連帯保証人がいる場合の注意点
住宅ローンを組む際に配偶者が連帯保証人になっていたり、夫婦でペアローンを組んでいる場合、主債務者(あなた)が自己破産をすると、銀行は保証人に対して残債の一括請求を行います。
結果として、連帯保証人である配偶者や親族も返済不能となり、連鎖的に自己破産せざるを得ない状況に陥るリスクがあります。
このような場合、自分一人で判断せず、必ず家族を含めて弁護士に相談し、「夫婦同時に自己破産申し立て」を行うか、他の債務整理方法(個人再生など)を検討する必要があります。
4. 名義による扱いの違い:家族名義・共有名義・親族名義
「自分名義ではないから大丈夫」とは限りません。
自己破産では、名義だけでなく「実質的な所有者は誰か」も調査されます。
4-1. 親や配偶者名義の持ち家に住み続けられるのか
家が親や配偶者の単独名義であり、かつ住宅ローンの債務者も名義人本人である場合、その家はあなたの財産ではないため、原則として処分の対象にはなりません。
ただし、名義は妻でも「頭金もローン返済もすべて夫(破産者)が出していた」というような場合、実質的には夫の財産とみなされ、処分の対象となる可能性があります。
4-2. 夫婦共有名義の場合の対処法
夫婦で家を共有している(例:夫50%、妻50%の持分)場合、夫が自己破産すると、夫の「共有持分(50%)」が処分の対象となります。
現実的には、家の半分だけを第三者が買い取ることは稀です。
そのため、管財人は以下の方法を検討します。
- 共有者である妻が夫の持分を買い取る(妻に資力が必要)。
- 妻と協力して、家全体を第三者に売却し、代金を分ける。
なお、競売で第三者(買受人)が購入をして共有名義となった場合、共有物分割請求訴訟や賃料相当損害金請求訴訟(共有物の全部を使用できない買受人が共有持ち分に相当する賃貸料の支払いを求める裁判)を提起されるリスクがあります。
4-3. 離婚・相続時に名義変更を行う場合のリスク
「破産する前に、家を親族や他人の名義に変えてしまえばいいのでは?」と考える方がいますが、これは絶対にやってはいけません。
破産直前の名義変更(贈与や格安での売却)は、財産隠し(詐害行為)とみなされます。
否認権を行使されて登記名義を戻されるだけでなく、最悪の場合、免責不許可事由に当たるため借金がゼロにならず、さらに詐欺破産罪に問われる可能性があります。
また、相続放棄をして不動産を取得しないようにする場合も、タイミングによっては限定承認の意思表示とみなされるなど法的論点が発生するため、必ず弁護士の指示に従ってください。
5. 自己破産後も持ち家を残すための具体的な方法
原則は処分ですが、例外的に今の家に住み続けられる方法も存在します。
ただし、これらはすべてのケースで使えるわけではなく、協力者や資金力が必要です。
5-1. 家族や親族が買い取るケース
親族(親や兄弟など)に家を適正価格(市場価格)で購入してもらい、その親族から家を借りて住み続ける方法です。
この場合、売却代金は住宅ローン会社への返済、債権者への配当に回されます。
家族や親族が買い取ってもらい済み続けるためには、次の条件が必要です。
- 親族に、家を一括で購入できる現金、またはローンを組める信用力があること。
- 適正価格での売買であること(安すぎると否認されます)。
5-2. リースバックを利用するメリットと注意点
リースバック業者(不動産会社など)に家を売却し、賃貸契約を結んで住み続ける方法です。
売却価格に応じた家賃設定となるため、周辺相場より高くなることが多く、生活を圧迫する恐れがあります。
将来買い戻す際の価格は、売却時より高くなることが一般的です。
破産申立て後におこなう場合、管財人の許可が必要であり、競売の方が高く売れると判断されれば認められないこともあります。
5-3. 自由財産の拡張は使える?要件と手続き
自己破産では、99万円以下の現金などは「自由財産」として手元に残せます。
さらに、裁判所に申し立てて認められれば、これ以外の財産も残せる「自由財産の拡張」という制度があります。
しかし、持ち家が自由財産の拡張として認められることは極めて稀です。
なぜなら、不動産は価値が高すぎるためです。
ただし、田舎の山林や老朽化して価値がつかない建物など、処分しても債権者への配当が見込めない不動産については、管財人が「財団放棄」をし、結果として手元に残るケースはあります。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
6. 自己破産以外の債務整理:個人再生や任意整理を選ぶメリット
「どうしても家を手放したくない」場合は、自己破産以外の選択肢を検討すべきです。
6-1. 個人再生の住宅ローン特則で持ち家を守る
個人再生(民事再生)には、「住宅資金貸付債権に関する特則(住宅ローン特則)」という制度があります。
住宅ローンはこれまで通り(またはリスケジュールして)支払い続け、それ以外の借金(カードローンなど)を大幅に(最大1/5〜1/10程度)減額するという手続きです。
これにより、マイホームを守りながら、無理のない範囲で借金を返済していくことが可能になります。
ただし、個人再生を利用するには「安定した継続的な収入があること」などが条件となります。
6-2. 任意整理で住宅ローンを対象外にする方法
任意整理は、裁判所を通さずに、各債権者と個別に交渉する方法です。
この場合、住宅ローンは整理の対象から外し(これまで通り支払い)、他の高金利な借金だけを整理できます。
借金の減額幅は「将来利息のカット」程度にとどまるため、借金総額が大きい場合には毎月の返済の負担は大幅に減りません。
ただ、返済回数を増やすことも合わせて交渉することで、毎月の返済額を減らせる可能性があります。
7.自己破産後の住まい探し:賃貸契約や引っ越しのポイント
家を手放すことになった場合、次の住まい(賃貸物件)の確保が急務となります。
7-1.自己破産後でも賃貸物件は借りられる?
結論として、自己破産をしても賃貸物件は借りられます。
ただし、入居審査の際に「信販系」の家賃保証会社(クレジットカード会社系の保証会社)を利用する物件の入居が難しい場合があります。
家賃保証会社は信用情報機関(いわゆるブラックリスト)のデータを参照できるため、自己破産の事実が分かり、与信の問題から審査に落ちる可能性が高くなります。
| 信用情報機関 | 登録期間 | 起算点 (期間のカウント開始日) |
備考 (法的・実務的留意点) |
|---|---|---|---|
|
CIC
(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)
|
5年 | 会員会社が報告した日 (免責許可決定が確認できた日) |
CICは「破産」という事実そのものではなく、個別の契約情報に「異動(法的手続き)」というコメントが登録されます。 起算点は「免責決定日」そのものではなく、カード会社等がそれを確認してCICにデータを送った日となるため、実際の免責日より数ヶ月ズレる場合があります。 |
|
JICC
(日本信用情報機構)
|
5年 | 当該事実の発生日 (破産申立日 または 免責許可決定日) |
「破産申立」の情報は発生日から5年、「免責許可決定」による契約終了(完済扱い)の情報も発生日から5年です。 CIC同様、業者からの報告ベースですが、JICCは「申立」の段階でも情報が登録されるのが特徴です。 |
|
KSC
(全国銀行個人信用情報センター)
|
7年 (※以前は10年) |
破産手続開始決定の日 (官報情報の官報公告区分発生日) |
以前は「10年」でしたが、2022年11月4日より「7年」に短縮されました。 官報に掲載された「破産手続開始決定」の情報(官報情報)に基づき登録されます。銀行でのローン審査等に影響します。 |
なお、上記の期間はあくまで「登録される期間」であり、期間経過後に自動的に審査に通ることを保証するものではありません。
各金融機関やカード会社は、独自の社内ブラックと呼ばれるリストを保有していることもあるため、審査に落ちる理由は信用情報機関の登録だけが原因ではありません。
7-2.保証会社の審査をクリアするための注意点
審査を通過するためのポイントは以下の通りです。
参照 保証会社の審査をクリアするためのポイント
- 独立系の保証会社を選ぶ
信用情報を参照しない独自の審査基準を持つ保証会社を利用している物件を不動産屋に紹介してもらう。 - 公営住宅(市営・県営住宅)
収入要件を満たせば、信用情報は問われません。 - 連帯保証人を立てる
保証会社を使わず、親族などの連帯保証人で契約できる物件を探す。 - UR賃貸住宅
礼金・仲介手数料・保証人が不要で、一定の収入基準があれば借りられます。
8.まとめ
自己破産と持ち家の問題は、個々の状況により対処法が異なります。
- 自己破産では原則として持ち家は処分される(競売または任意売却)。
- 住宅ローン特則のある「個人再生」なら、家を守れる可能性がある。
- 処分となる場合でも、半年〜1年程度の猶予期間がある。
- 賃貸への住み替えは、保証会社選びが鍵となる。
「もう手放すしかない」と諦める前に、まずは弁護士や司法書士に相談してください。
専門家がローンの残債や家計を分析することで、家を残す道や、生活再建のための最適な戦略が見つかります。
古山綜合法律事務所では、借金問題の初回無料相談をおこなっています。
借り入れや家計の状況を丁寧にお伺いし、ご希望を踏まえた解決策をご提案いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
相談のご予約は、電話、WEBフォーム、LINE、チャットで受付中です。
ご都合の良い方法で、お問い合わせください。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。