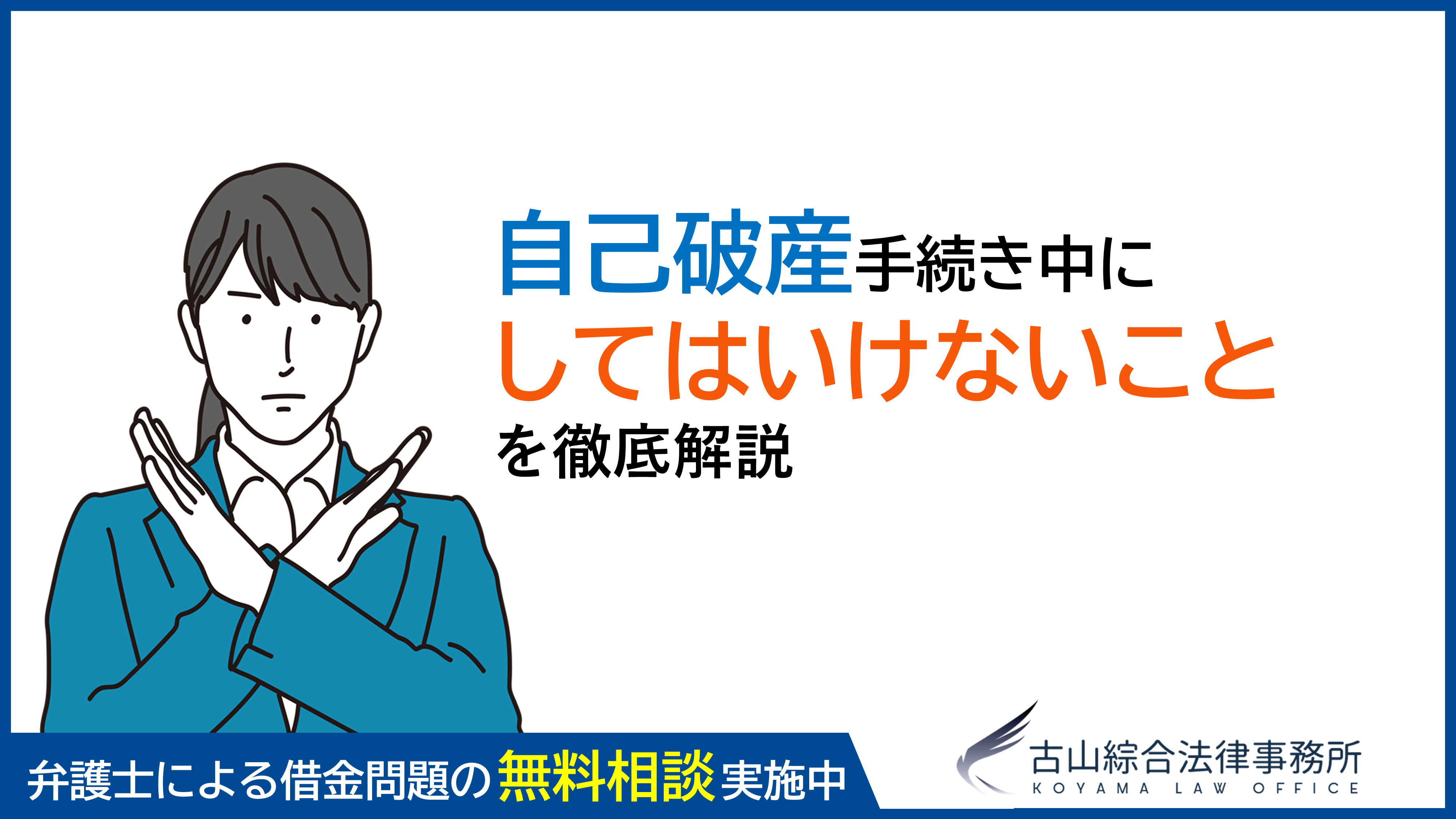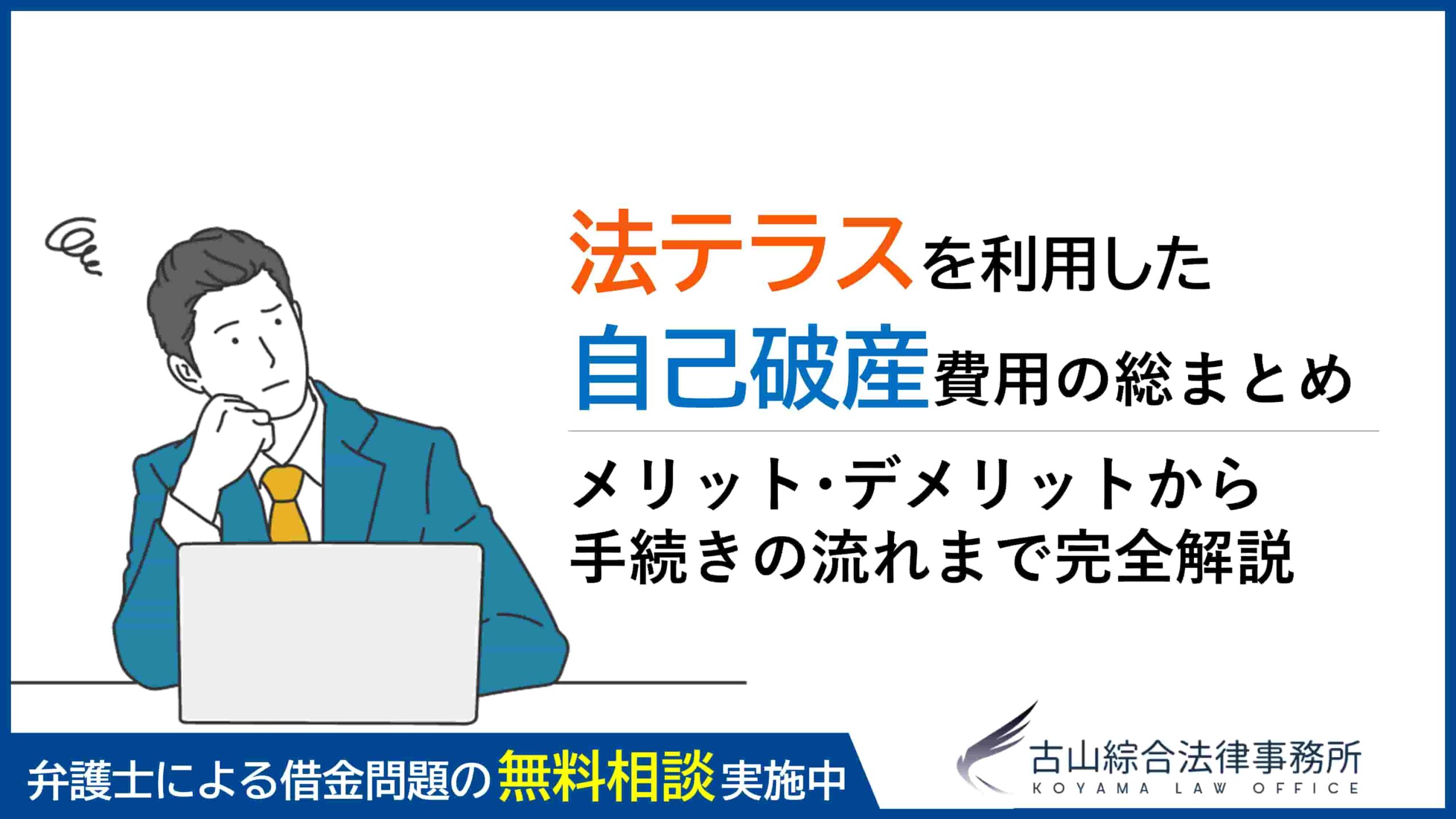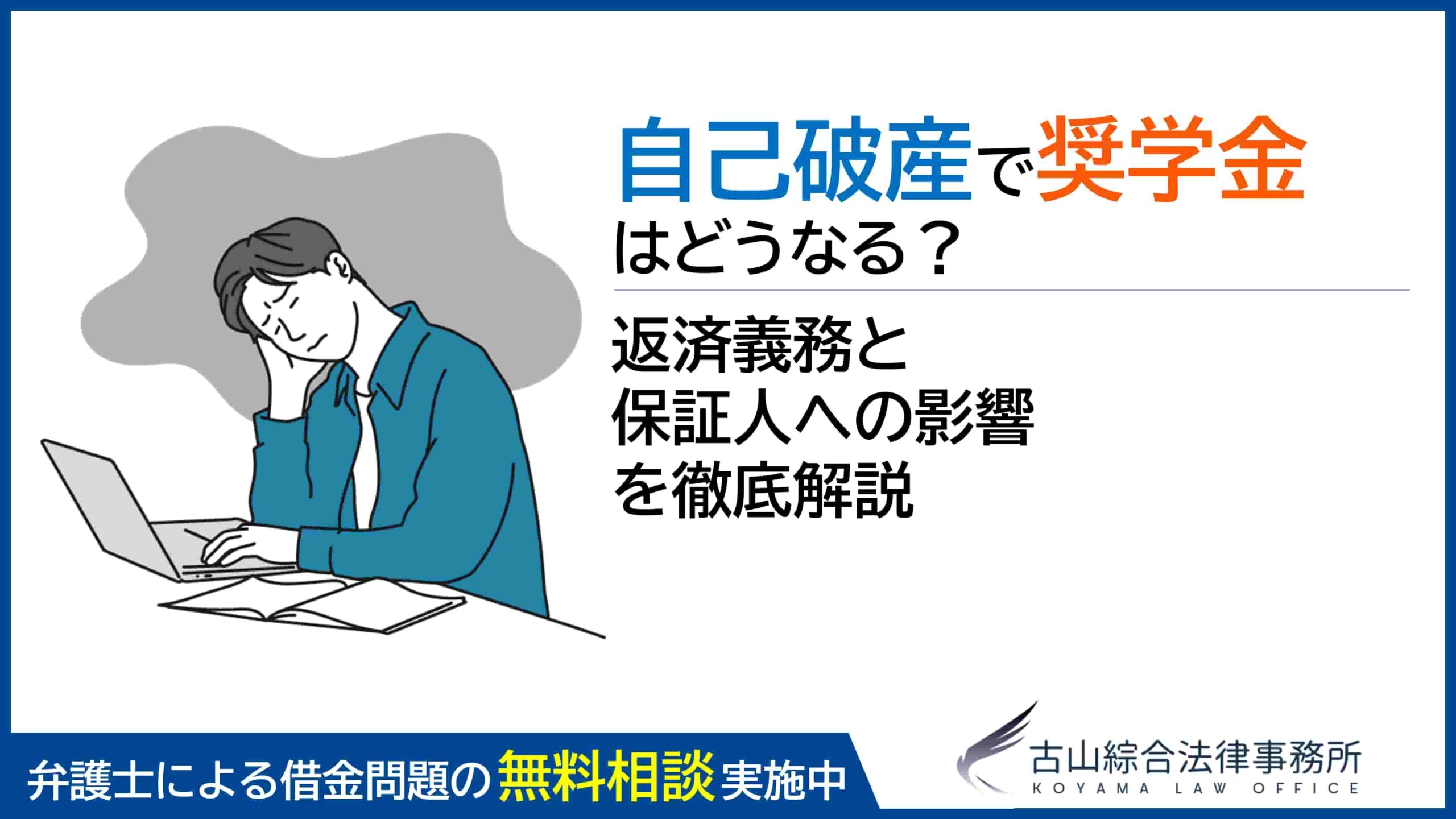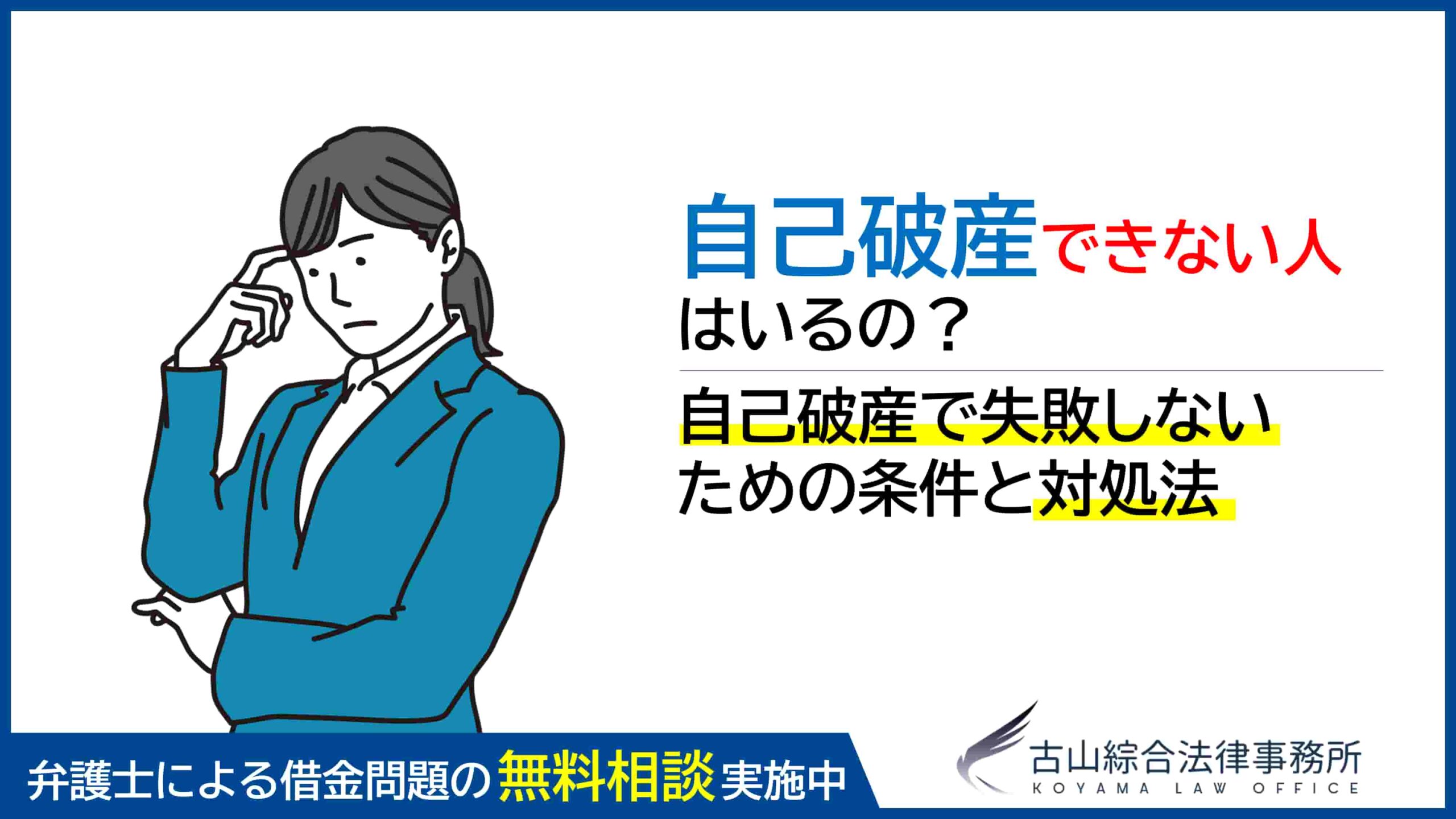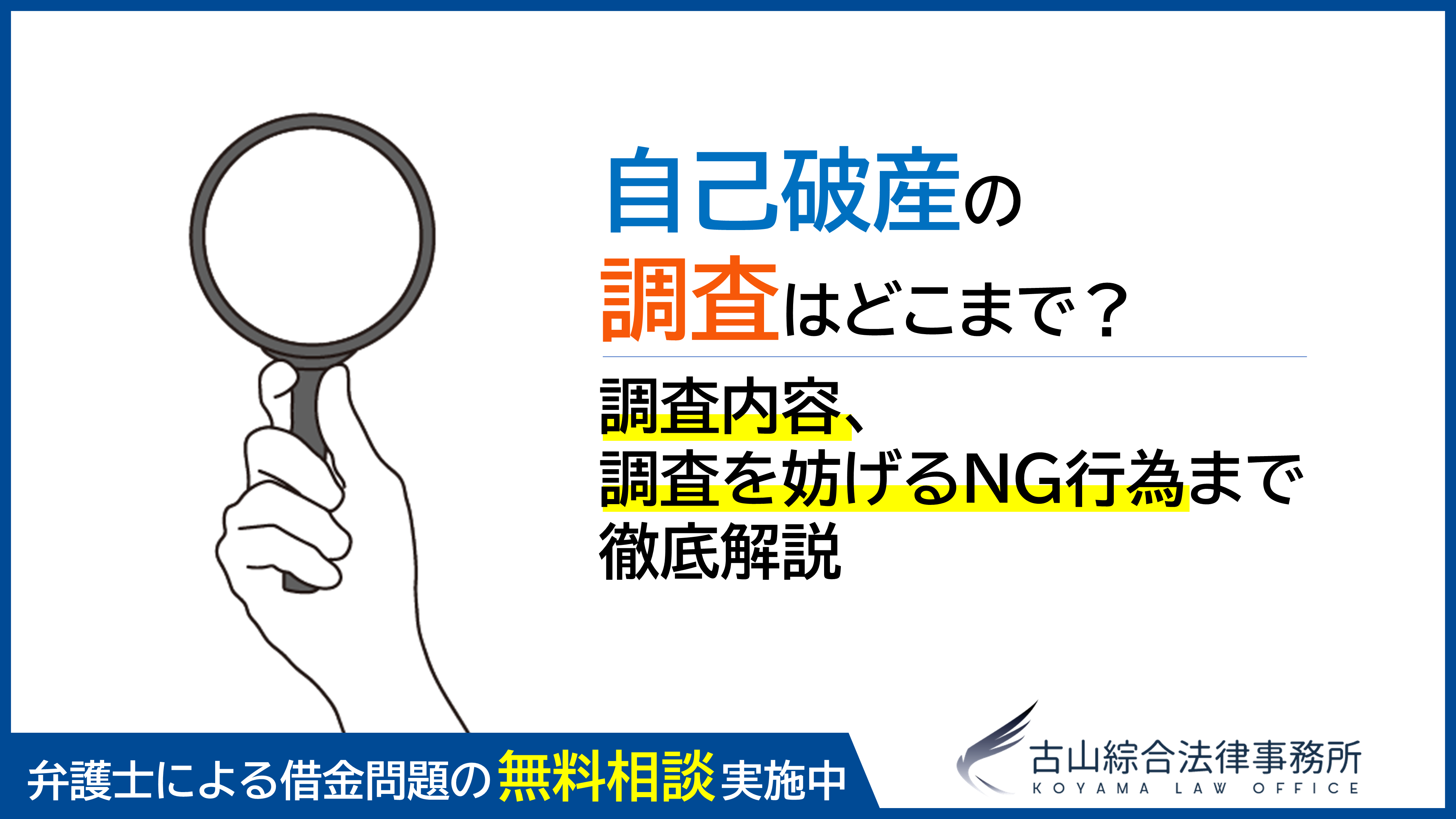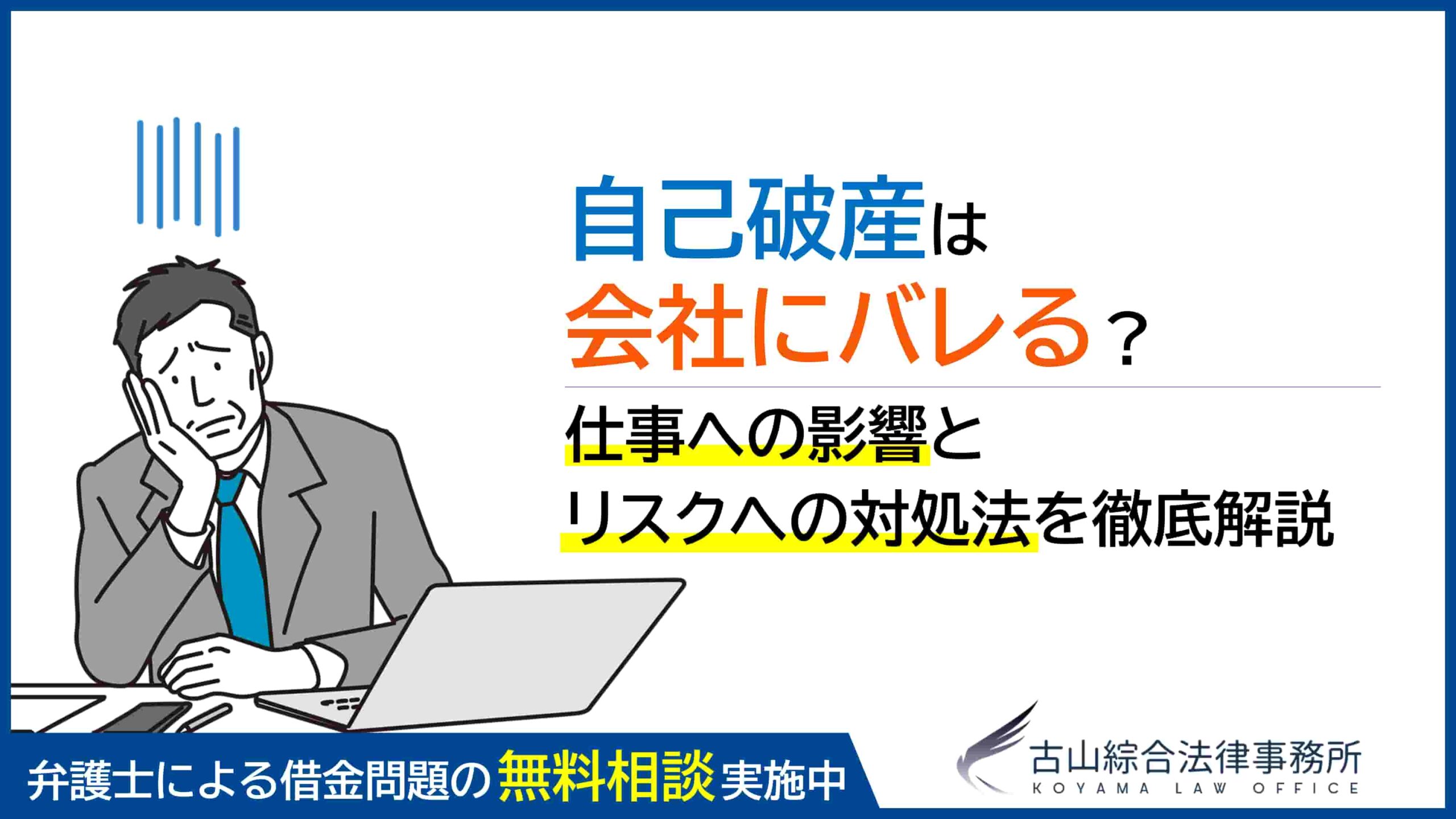自己破産すると住宅ローンはどうなる?家を残す方法や再びローンが組めるかについて解説
借金問題
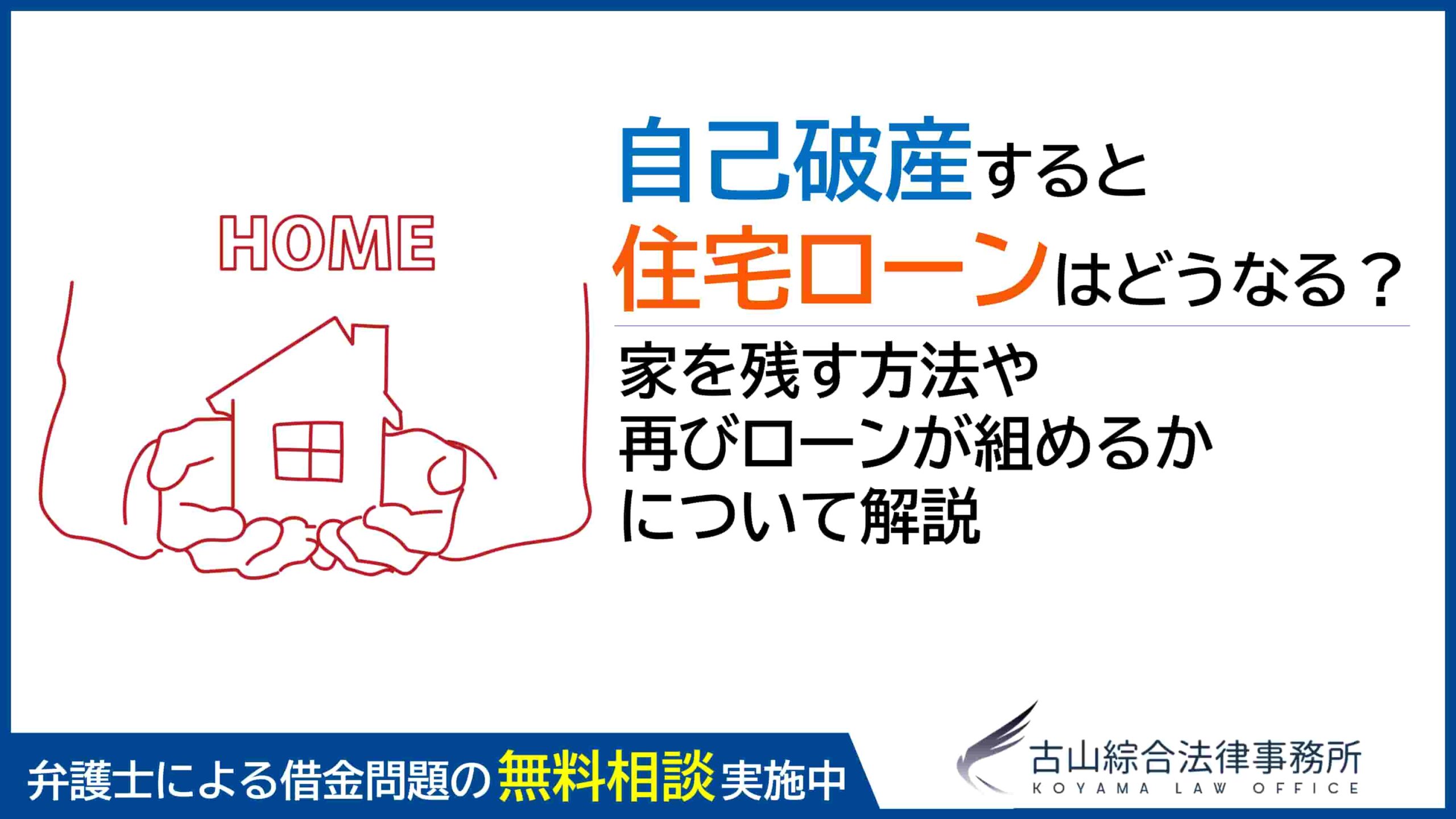
この記事の目次(クリックで開閉)
自己破産すると住宅ローンはどうなる?家を残す方法や再びローンが組めるかについて解説
住宅ローンの返済が苦しくなり、多額の借金を抱えてしまったとき、「自己破産」という選択肢が頭をよぎるかもしれません。
しかし、同時に「長年住み慣れた家だけは手放したくない」「家族を路頭に迷わせるわけにはいかない」という強い不安をお持ちではないでしょうか。
自己破産は、借金の支払義務を免除(免責)してもらうための法的な救済手続きですが、住宅ローンが残っている場合、その影響は非常に複雑です。
この記事では、住宅ローンの返済に悩み、自己破産を検討しているあなたが、正しい知識を持って最善の選択をするために、以下の点を分かりやすく解説します。
- 自己破産をすると、住宅ローンと持ち家は具体的にどうなるのか
- 家に住み続けながら借金問題を解決する方法
- 連帯保証人やペアローンを組んでいる家族への影響
- 自己破産後に、再び住宅ローンを組むことはできるのか
- 自己破産手続きを進める上での注意点と絶対にやってはいけないこと
この記事を最後まで読めば、あなたの状況で取りうる選択肢が明確になり、不安を解消して生活再建への第一歩を踏み出すための道筋が見えてきます。
1. 自己破産をすると住宅ローンと持ち家はどうなる?
自己破産をすると、原則としてすべての借金の支払いが免除されます。
しかし、その代償として、一定額以上の価値がある財産は処分され、債権者への配当に充てられます。
特に、持ち家(自宅)のような高価な資産がある場合、自己破産の手続きは「管財事件」として扱われるのが通常です。
これは、裁判所から選任された破産管財人があなたの財産を調査・管理・換価(現金化)し、債権者に公平に分配する手続きです。
そのため、住宅ローンが残っている持ち家は、破産管財人の管理下で処分されることになり、原則として手元に残すことはできません。
家の処分方法は、主に「競売」と「任意売却」の2つです。
1-1. 自己破産の手続き|管財事件と同時廃止
個人の自己破産手続きは、財産状況や負債の内容によって「管財事件」と「同時廃止」の2種類に分かれます。
最終的にどちらの手続きで進めるかは、裁判所の判断になります。
参照 自己破産手続きの種類
- 管財事件
破産者に一定以上の財産(持ち家など)がある場合や、免責を認めるべきか慎重な調査が必要な場合におこなわれる手続きです。
裁判所が破産管財人を選任し、財産の調査や処分、債権者への配当などをおこないます。そのため費用や期間がかかります。
本来、これが自己破産の原則的な手続きです。 - 同時廃止
破産者に配当に充てるほどの財産がなく、免責不許可事由(免責が認められない理由)もないことが明らかな場合におこなわれる、簡略化された手続きです。
破産手続の開始決定と同時に手続きが終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれます。
住宅ローンが残っている持ち家がある場合は、その家が処分・換価の対象となる財産とみなされるため、原則として「管財事件」となります。
1-2. 競売と任意売却の流れを理解しよう
持ち家は、破産管財人の主導のもと、「競売」または「任意売却」によって売却されます。
参照 自己破産手続きにおける不動産の処分
- 競売(けいばい)
債権者(金融機関)が担保権(抵当権)を実行し、裁判所を通じて家を強制的に売却する手続きです。
市場価格より安くなる傾向があり、いつ誰が落札するかわからない、といったデメリットがあります。 - 任意売却(にんいばいきゃく)
債権者の同意を得て、破産管財人の監督下で、一般的な不動産市場で家を売却する方法です。
競売よりも高値で売れる可能性が高く、売却の時期や条件についてもある程度の交渉が可能です。
多くの場合、破産管財人は競売よりも高値で売却でき、債権者への配当を増やせる可能性がある任意売却を選択する傾向にあります。
競売と任意売却の比較
| 比較項目 | 競売 | 任意売却 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 市場価格の5〜7割程度になることが多い | 市場価格に近い価格での売却が期待できる |
| 手続きの主導 | 手続き:裁判所 申立て:債権者 |
手続き:破産管財人・債務者 |
| プライバシー | 情報が公開されるため、近所に知られやすい | 一般の不動産売却と同じなので、知られにくい |
| 引渡し時期 | 落札者の都合に合わせる必要があり、交渉は困難 | 買主との交渉次第で、ある程度調整可能 |
1-3. アンダーローン・オーバーローンの違い
住宅ローン残高と家の売却価格の関係によって、「アンダーローン」と「オーバーローン」に分けられます。
1-4. 自己破産手続き開始後の住宅ローン返済義務は免除になる?
自己破産の手続きが始まると、すべての借金の返済を一旦ストップしなければなりません。
そして、最終的に裁判所から免責許可決定が下りれば、住宅ローンを含む借金の支払い義務が免除されます。
ここで非常に重要な注意点があります。
「家だけは守りたいから」と、自己破産の申し立て直前に住宅ローンだけを返済し続けることは絶対にやめてください。
特定の債権者(この場合は住宅ローンを組んだ金融機関)だけに優先して返済する行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼ばれ、債権者平等の原則に反します。
これは免責不許可事由(破産法第252条1項3号)に該当し、自己破産をしても借金が免除されないという最悪の事態を招く可能性があります。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
2. 家を手放さずに済む可能性がある方法
自己破産手続きでは原則として家を失いますが、いくつかの例外的な方法で家に住み続けられる可能性があります。
ただし、いずれも破産管財人の同意や協力が不可欠であり、実現にはハードルがあります。
2-1. 親族・家族に住宅を買い取ってもらうメリットと注意点
親や兄弟など、資力のある親族に家を適正価格で買い取ってもらう(親子間売買・親族間売買)方法です。
これができれば、あなたは賃料を支払うなどして、そのまま家に住み続けることができます。
2-2. リースバックで住み続ける仕組みとは
リースバックとは、リースバック会社に家を一度売却し、その会社と賃貸契約を結ぶことで、家賃を払いながら同じ家に住み続ける方法です。
2-3. 固定資産税・管理費の負担とその扱い
自己破産をしても、税金や社会保険料などの「非免責債権」は支払い義務が免除されません。
家の所有者である限り、固定資産税やマンションの管理費・修繕積立金の支払い義務はあなたにあります。
家が競売や任意売却で処分され、所有権が他人に移るまでの期間に発生した固定資産税や管理費は、支払わなければなりません。
滞納している税金は、自己破産後も請求されますので注意が必要です。
3. 連帯保証人・ペアローンへの影響
自己破産によって免責されるのは、あくまで破産者本人の支払い義務だけです。
契約上の義務は消滅しないため、債権者は残りのローン全額を連帯保証人やペアローンのもう一方のパートナーに一括で請求してきます。
そのため、住宅ローンに連帯保証人がいる場合や、夫婦でペアローンを組んでいる場合、自己破産はあなた一人の問題では済みません。
3-1. 連帯保証人が返済義務を負うケース
あなたが自己破産した場合、債権者は直ちに連帯保証人に対して、住宅ローンの残額全額の一括返済を求めます。
連帯保証人があなたの代わりに返済できない場合、連帯保証人自身も債務整理(自己破産や個人再生など)を検討せざるを得ない状況に追い込まれる可能性があります。
3-2. ペアローンへの破産の影響と対処法
ペアローンは、夫婦などがそれぞれ債務者となり、お互いが相手のローンの連帯保証人になっているケースがほとんどです。
そのため、一方が自己破産すると、もう一方は「自分のローン」と「相手のローン(連帯保証人として)」の両方の返済義務を負うことになります。
現実的に返済は極めて困難となり、結局は家を任意売却などで手放し、それでも残った債務について、もう一方のパートナーも債務整理を検討する必要が出てくるでしょう。
ペアローンの場合は、問題を一人で抱え込まず、必ずパートナーと、そして弁護士などの専門家に一緒に相談することが大切です。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
4.自己破産以外の債務整理で住宅を守る方法
自己破産・個人再生・任意整理の比較表
| 比較項目 | 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|---|
| 家を残せるか | 〇 残せる (住宅ローンを整理対象から外すことで維持可能) |
〇 残せる可能性大 (住宅ローン特則の利用により維持可能) |
× 原則手放す (持ち家は換価処分の対象となる) |
| 借金の減額幅 | 将来利息のカット (元金は原則減らない) |
大幅に減額 (元金を1/5~1/10程度に圧縮) |
全額免除(ゼロ) (税金などを除く全ての支払い義務がなくなる) |
| 整理対象となる債務を選べるか | 選べる (保証人付きの借金やカーローンを除外可能) |
原則すべて (住宅ローン特則利用時のみ住宅ローンを除外) |
すべて (特定の借金だけを返済することは不可) |
| 手続きの対象者 | 安定した収入があり、元金を3~5年で返済できる人 | 安定した収入があり、家を残したい・借金額が大きい人 | 収入がない、または借金が多すぎて返済不能な状態の人 |
「どうしても家だけは残したい」という場合、自己破産以外の債務整理を検討することで、実現できる可能性があります。
4-1. 個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)
個人再生は、裁判所に再生計画を認めてもらい、大幅に減額された借金(住宅ローンを除く)を原則3〜5年で分割返済していく手続きです。
最大のメリットは「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という制度を使える点です。
この特則を利用すれば、住宅ローンはそのまま返済を続け、それ以外の借金だけを大幅に減額してもらうことが可能になります。
これにより、家を手放すことなく、生活の再建を図ることができます。
ただし、最長5年間は返済を続けていく必要があるため、安定した収入が見込めることが必要です。
4-2. 任意整理で住宅ローン以外の借金を軽減する
任意整理は、裁判所を通さずに、債権者(消費者金融、信販会社やクレジットカード会社など)と直接交渉し、主に将来利息のカットや分割払いの回数を調整してもらうことで、月々の返済負担を軽減する手続きです。
住宅ローン以外の借金だけを整理の対象とすることで、毎月の返済額を減らし、住宅ローンの返済を継続していく余裕を生み出すことを目指します。
ただし、元金そのものは減額されないため、大幅な借金減額は見込めません。
ただし、住宅ローン以外の借金がほとんどなく、返済が苦しい原因が住宅ローンそのものである場合、任意整理をしても状況は改善しません。
その場合は、自己破産や個人再生、または家の売却を含めた根本的な解決策を検討する必要があります。
5. 自己破産後に住宅ローンを再び組めるのか?
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が登録(いわゆるブラックリスト入り)されるため、新たな借入は極めて困難になります。
5-1. 信用情報に登録される期間は5~7年
自己破産の情報は、以下の信用情報機関に登録されます。
信用情報機関ごとの登録期間比較
| 機関名 | 主な加盟先 | 登録期間(ブラックリスト期間) |
|---|---|---|
| CIC (株式会社シー・アイ・シー) |
主にクレジット会社 | 免責許可決定から5年 |
| JICC (株式会社日本信用情報機構) |
主に消費者金融 | 免責許可決定から5年 |
| KSC (全国銀行個人信用情報センター) |
主に銀行 | 破産手続開始決定から7年 (※2022年10月まで10年でしたが短縮されました) |
銀行の住宅ローン審査では、最も登録期間の長いKSCの情報を参照するため、自己破産後、最低でも7年間は新たに住宅ローンを組むことは基本的に難しいと考えておくべきです。
自分の信用情報がどうなっているかは、各機関に開示請求をして確認することができます。
5-2. 過去利用した金融機関を避けるべき理由
信用情報機関から事故情報が抹消されたとしても、自己破産で迷惑をかけた金融機関やそのグループ会社(いわゆる「社内ブラック」)では、審査に通る可能性は限りなくゼロに近いでしょう。
過去の記録が社内に残り続けているためです。
住宅ローンを申し込む際は、過去に取引のなかった金融機関を選ぶ必要があります。
5-3. クレジットヒストリーがないため審査に通らない可能性
金融機関やローン会社が新規の融資申し込みを受けた際、個人がこれまでに利用したクレジットカードやローンなどの契約内容や支払い状況に関する記録である「クレジットヒストリー(クレヒス)」を参照することが一般的です。
年齢や職業(就職期間)があるにも関わらず、クレジットカードやローンの利用が一切ない場合(いわゆるスーパーホワイト)、「過去に破産などの事故があったのではないか?」と疑いを持たれる可能性があります。
そのため、携帯電話本体の分割払い、比較的審査が通りやすいクレジットカードを作成し、少額の利用と期日通りの返済を繰り返したりすることで、クレジットヒストリーとしての実績を築けることがあります。
自己破産後に住宅ローンを再度組むためには、信用情報を回復させた上で、安定した収入の確保や頭金を多く用意するなどの対応が必要になることもあります。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
6. 自己破産を検討する際の注意点
自己破産は人生の再スタートを切るための強力な手段です。
しかし、手続きを誤ると取り返しのつかない事態になることもあります。
6-1. 資産や住宅の名義変更はNG
自己破産直前に、家などの財産を処分から免れる目的で、妻や親族に名義変更する行為は「財産隠し(詐害行為)」とみなされます。
これは、破産管財人の否認権の対象となり、名義変更は無効とされ、財産は取り戻されてしまいます。
さらに、悪質な財産隠しは免責不許可事由に該当し、最悪の場合、詐欺破産罪(破産法第265条)という犯罪に問われる可能性もある、極めてリスクの高い行為です。
6-2. 住宅ローンのみを返済する
返済不能状態にあるにも関わらず、消費者金融などから借り入れをおこない、住宅ローンだけを返済する行為は「偏波弁済」に当たる可能性があります。
前述したとおり、偏頗弁済は「免責不許可事由」となり、せっかく自己破産を申し立てたとしても免責決定が得られず、借金が免除されないというリスクが高まります。
7. よくあるQ&A
自己破産に関するよくある疑問にお答えします。
7-1. 家族に借金支払い義務はある?連帯保証人との違い
あなたが自己破産しても、保証人になっていない限り、家族に法的な支払い義務はありません。
あなたの借金は、あくまであなたの個人の問題です。
ただし、本記事の「3-1. 連帯保証人が返済義務を負うケース」で解説した通り、家族が連帯保証人になっている場合は、その家族に請求がいくことになります。
7-2. 自己破産と税金・保険料の取り扱い
所得税、住民税、固定資産税などの税金や、国民健康保険料、年金保険料などは「非免責債権」といい、自己破産をしても支払い義務は免除されません。
滞納している場合は、自己破産後も支払う必要があります。
支払いが困難な場合は、役所の窓口で分割払いや猶予の相談をしましょう。
7-3. 住宅ローン滞納が続くと固定資産税はどうなる?
住宅ローンの返済を滞納していても、家が売却されて所有権が移転するまでは、あなたに固定資産税の納税義務があります。
自己破産の手続き中であっても同様です。
滞納すると延滞金が加算されるため、どう対処すべきか、事前に弁護士に相談しておくことが重要です。
8. まとめ
住宅ローンの返済が困難になり、自己破産を考え始めたとき、多くの方が「家を失うこと」への不安を感じるものです。
しかし、一人で悩み続けても状況は好転しません。
自己破産をすれば借金の悩みからは解放されますが、原則として自宅は失います。
一方で、個人再生という手続きを選べば、家を守りながら借金を大幅に減額できる可能性があります。
どの方法があなたとご家族にとって最善の選択なのかは、収入や資産、借金の状況によって全く異なります。
最も重要なことは、手遅れになる前に、一刻も早く専門家である弁護士に相談することです。
弁護士はあなたの代理人として、債権者からの督促を止め、法的な観点からあなたに最適な解決策を提案してくれます。
まずは勇気を出して、その一本の電話から、あなたの人生の再スタートを切り出しましょう。
古山綜合法律事務所では、借金問題の初回無料相談をおこなっています。
借り入れや家計の状況を丁寧にお伺いし、ご希望を踏まえた解決策をご提案いたします。
ぜひお気軽にご相談ください。
相談のご予約は、電話、WEBフォーム、LINE、チャットで受付中です。
ご都合の良い方法で、お問い合わせください。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。