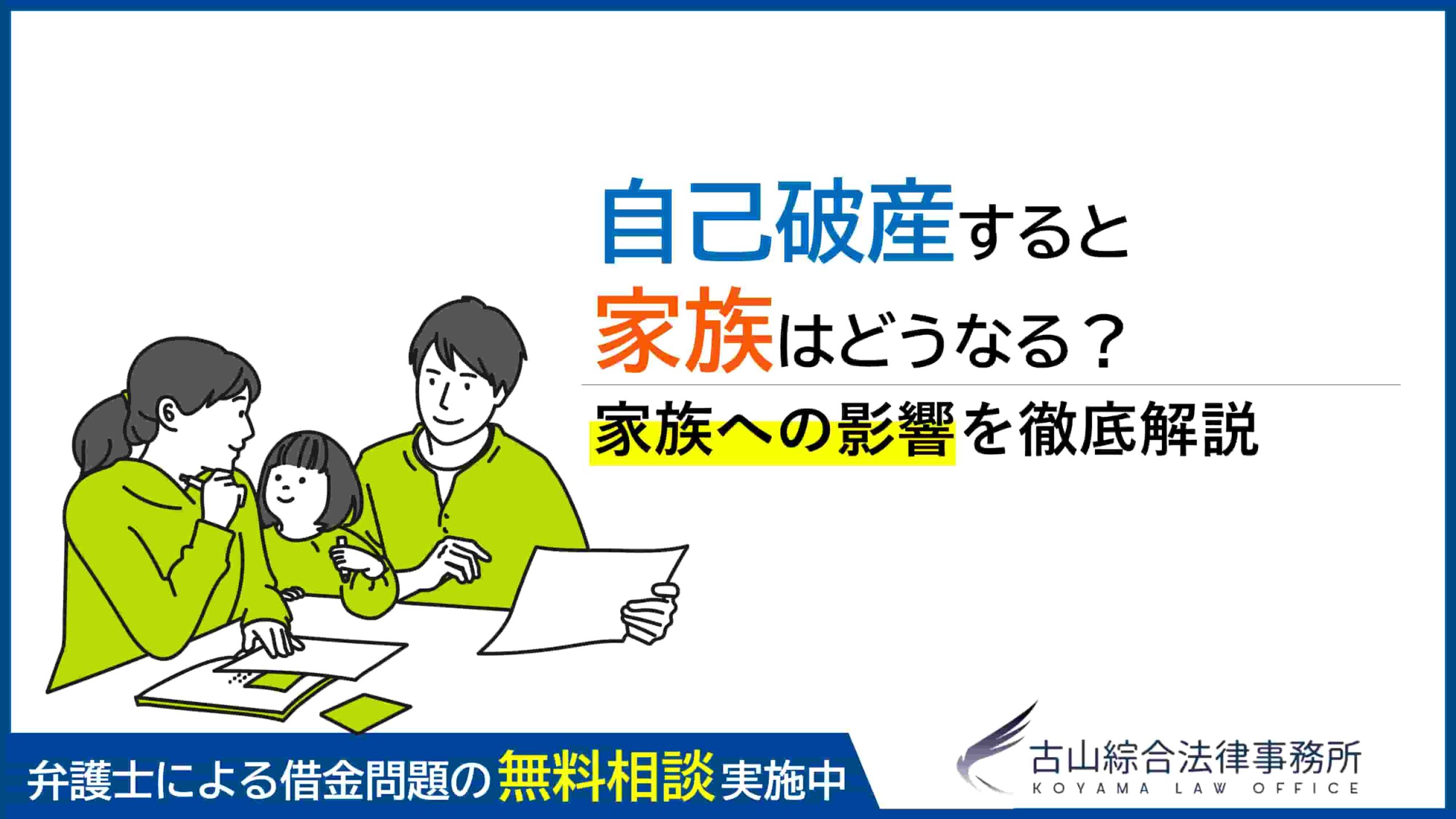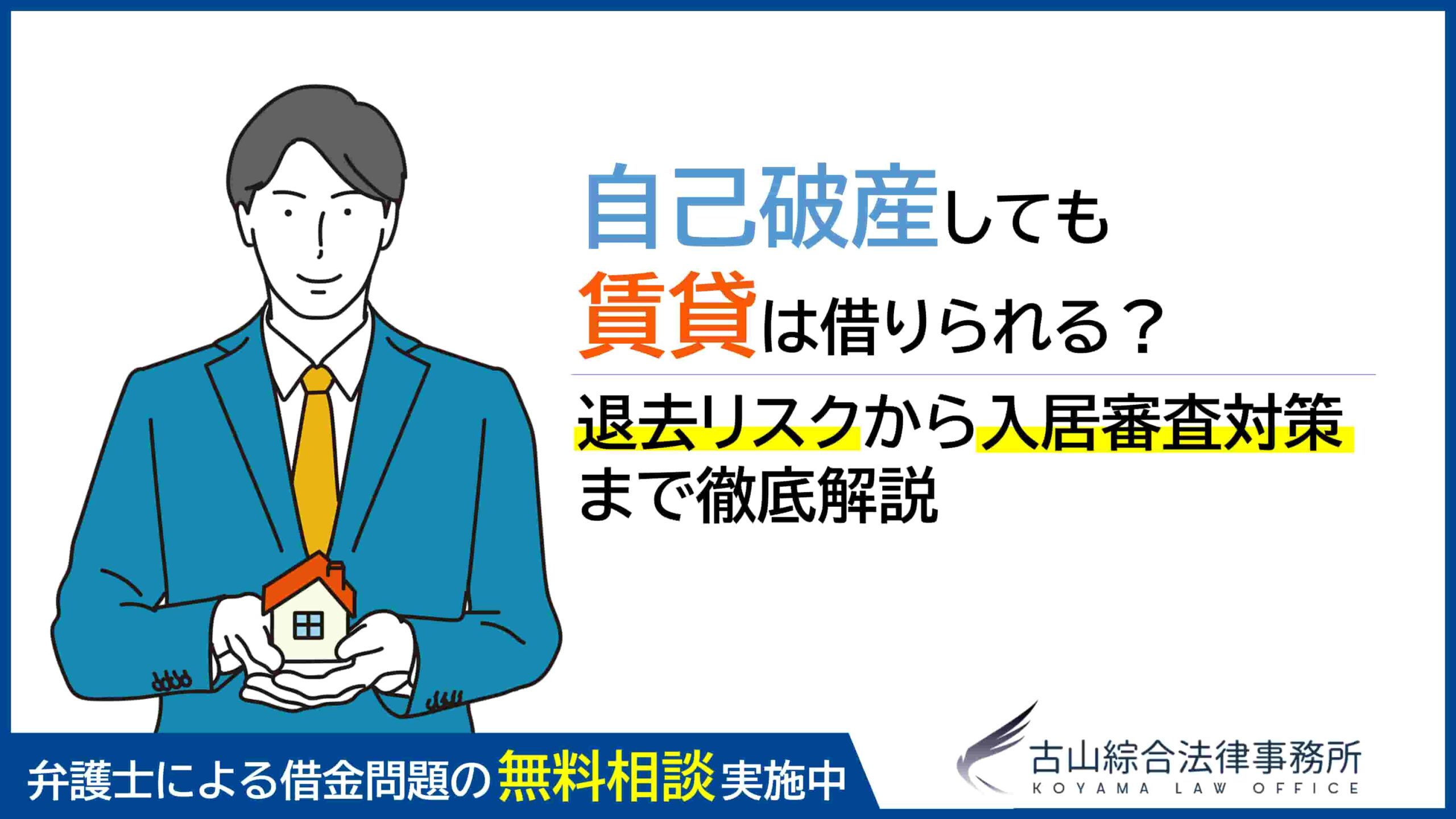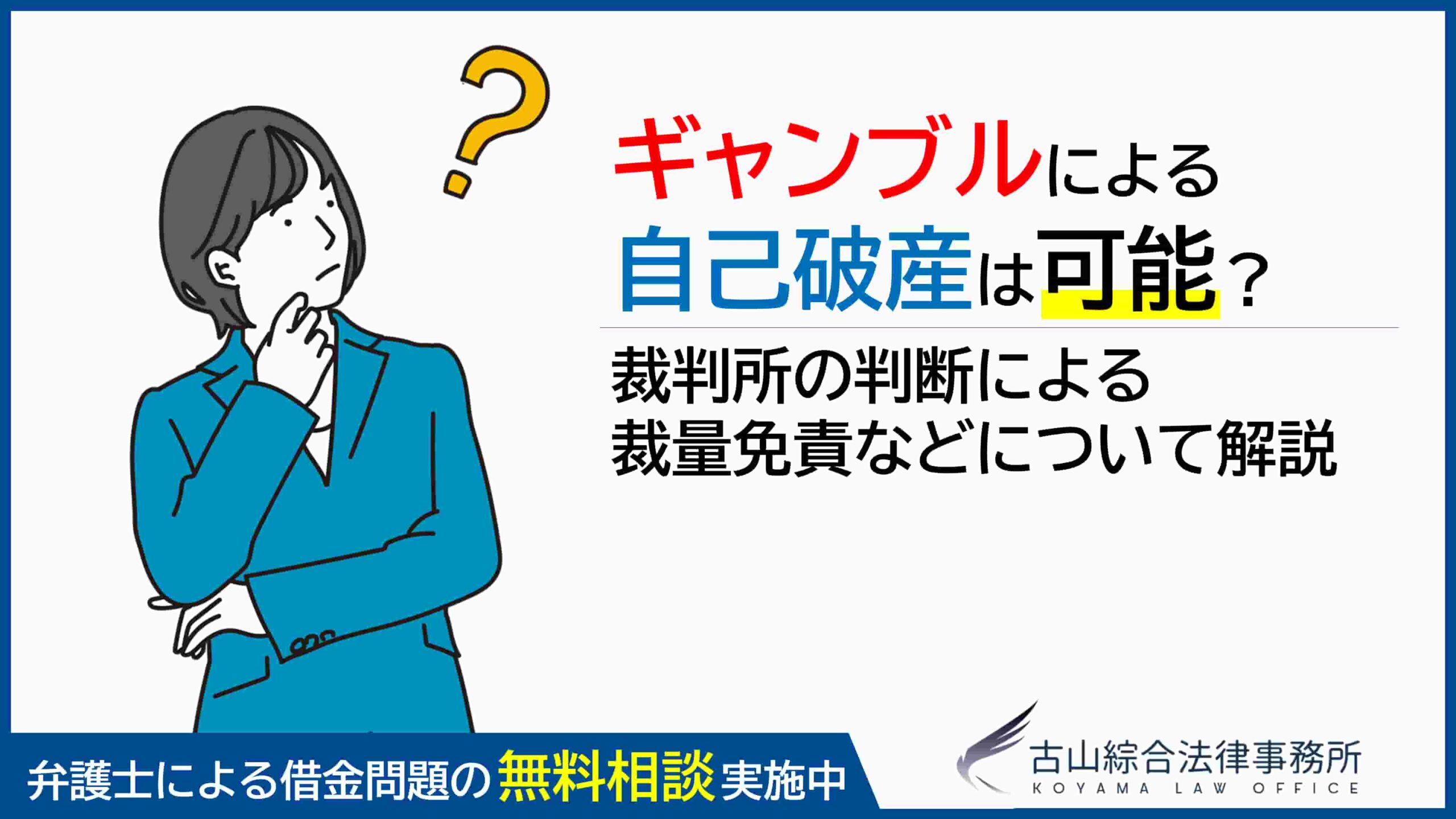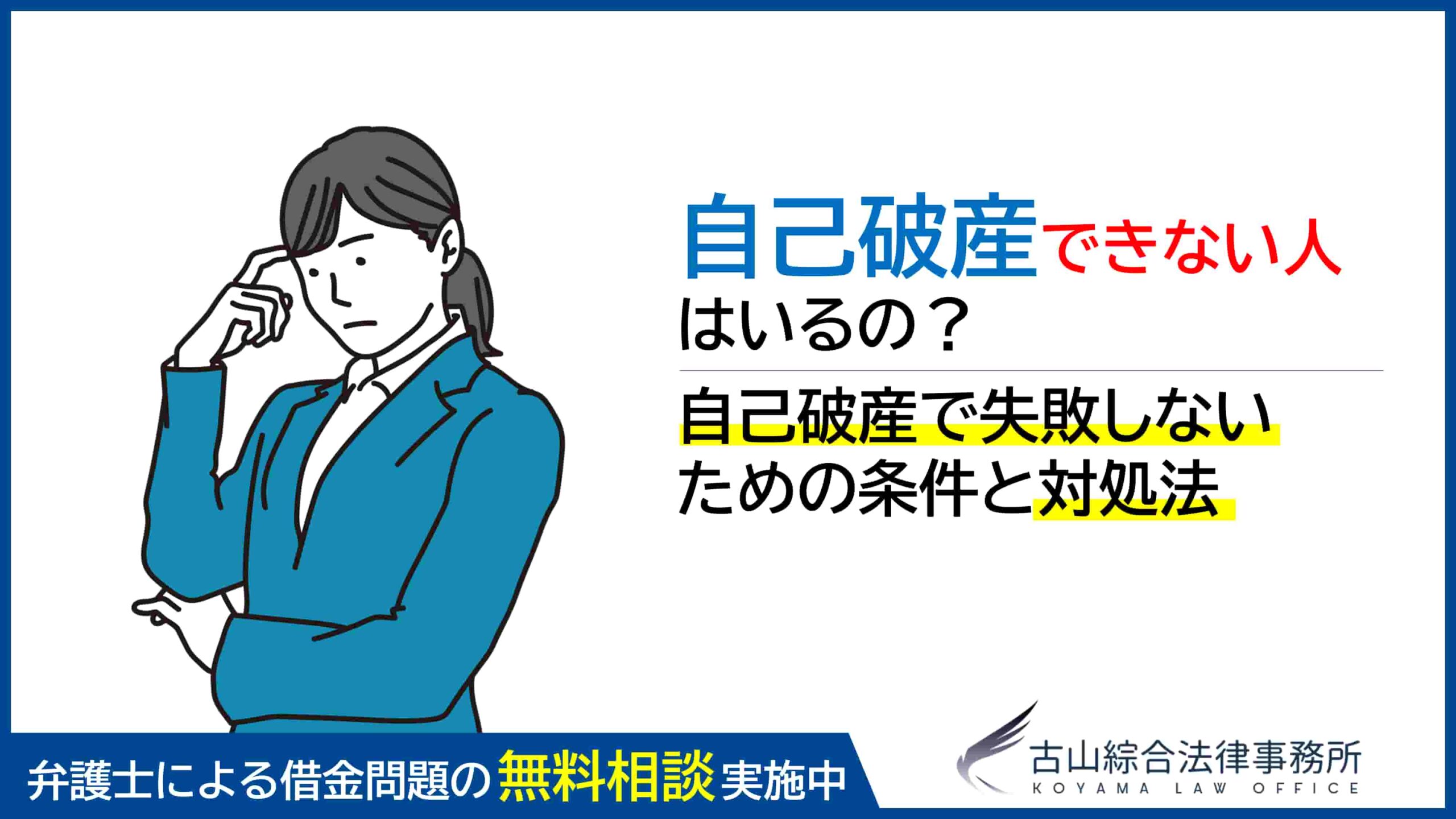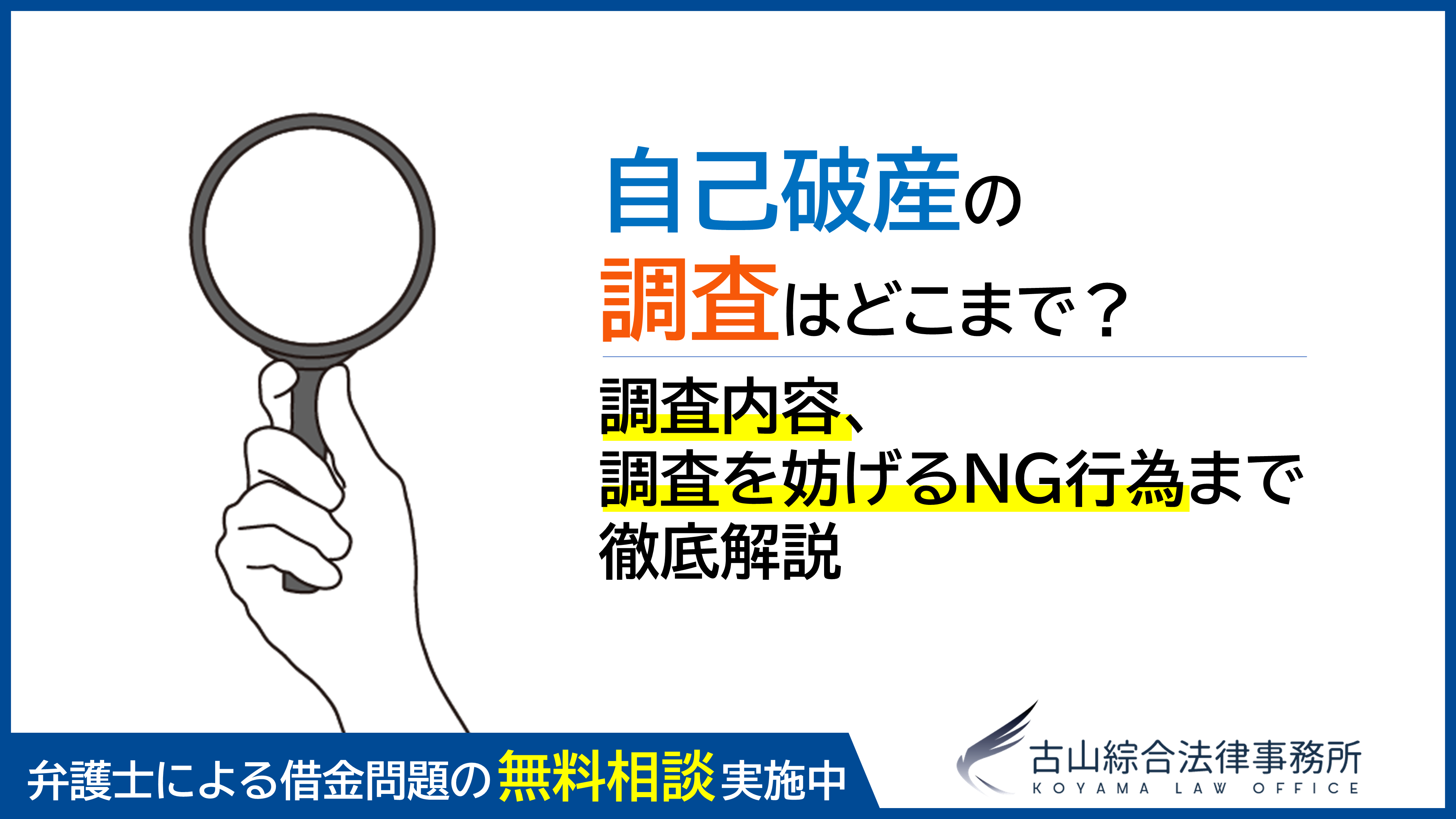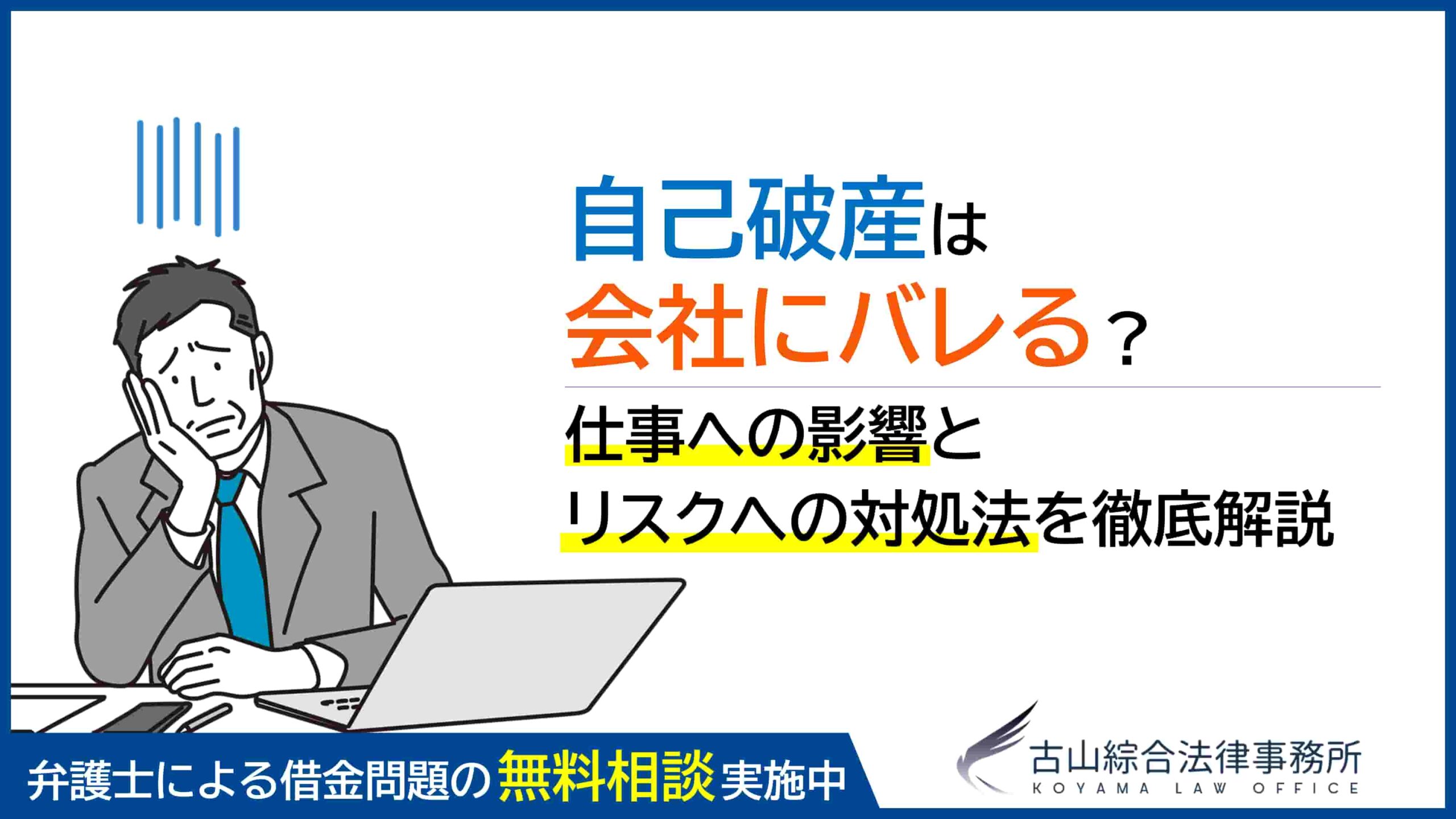2回目の自己破産は可能?免責を受けるために知っておくべきポイント
借金問題
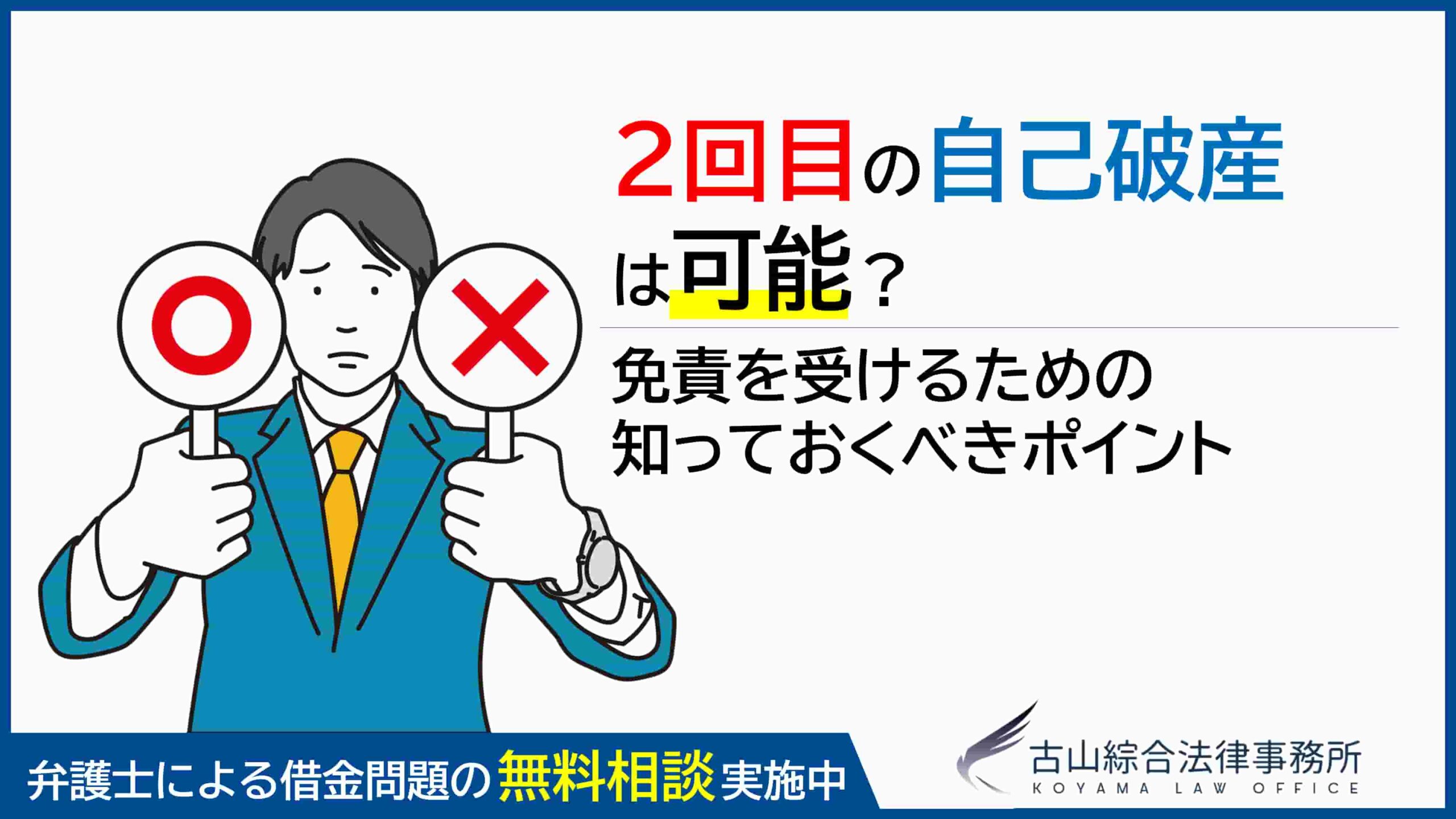
この記事の目次(クリックで開閉)
2回目の自己破産は可能?免責を受けるために知っておくべきポイント
2回目の自己破産は審査が厳格になりますが、再度の破産に至る事情や適切な準備により、再び借金をゼロにすることは可能です。
裁判所に『更生の意思』を認めてもらうためには、1回目とは異なる入念な対策が不可欠です。
本記事では、2回目の自己破産における法的な条件(7年ルール等)や、審査が厳格化するポイント、費用面の違いについて、破産法などの法律的根拠を交えて分かりやすく解説します。
1. 1回目の自己破産から再度手続きはできるのか
2回目の自己破産は可能です。
自己破産制度に回数制限はないため、2回目や3回目であっても手続き自体は問題なく行えます。
ただし、『申立てができること』と、『実際に借金がゼロになる(免責許可が下りる)こと』は別の問題です。
2回目の手続きでは、1回目よりも審査が厳しくなるのが一般的であり、前回の破産後の行動や、なぜ再び借金を作ってしまったのかという経緯が詳細に調査されます。
2. 2回目の自己破産で免責が認められるための主な条件
2回目の免責獲得には、『前回の免責から7年経過しているか』『借金の原因は何か』という2つの条件を重要視して審査をおこないます。
裁判所は提出された証拠や書類に基づき、「この申立人は本当に反省しているか」「経済的に更生できるか」を審査します。
そのため、単に申立てを行うだけでなく、ご自身の家計状況を整理し、いつどのように借金が増えたのかを明確にしておくことが重要です。
2-1. 前回の自己破産から7年以上経過していること
前回の免責許可決定の確定日から7年以内の申立ては「期間の制限(免責不許可事由)」に該当するため、原則として借金免除を認める免責決定は得られません(破産法第252条第1項第10号)。
ただし、7年に達していなくても、「裁量免責(破産法第252条第2項)」という制度があります。
これは、裁判所が一切の事情を考慮して、相当と認めるときに限り免責を許可できる制度です。
突発的な事故、家族の深刻な病気、犯罪被害(詐欺被害)、リストラなど、本人の努力だけでは回避困難な事情がある場合は、「なぜ短期間で再び経済的破綻に至ったのか」を具体的に説明することで免責が認められる可能性があります。
いずれにせよ、自身の収支や返済状況など、客観的で信用性の高い資料を用意し、裁判所に説明できるよう準備を進めることが大切です。
2-2. 同じ原因・理由での借金でも免責を受ける可能性はある?
前回と全く同じ原因(例えばギャンブル、浪費、投資の失敗など)で多重債務におちいった場合、裁判所から「反省が見られない」「制度を悪用しているのではないか」と疑われやすくなります。
しかし、借金の原因が同じであっても、免責が絶対に不可能というわけではありません。ここでも裁量免責の適用を目指すことになります。
特に、ギャンブルや浪費などの自己責任が大きいケースでも、以下のような行動が評価されれば、免責の余地が生まれます。
- 専門機関への相談
ギャンブル依存症のクリニックに通院している、自助グループに参加している。 - 家計の管理
家計簿を詳細につけ、無駄な支出を削減している。 - 家族の協力
親族が金銭管理を監督している。
再度の手続きで不利にならないためにも、原因が重複してしまった背景を正直に説明し、二度と同じ失敗を繰り返さない意思を明確に示すことが対応策の第一歩となります。
3. 2回目の自己破産における審査の厳しさ
2回目の自己破産は、1回目よりも審理が格段に厳しくなる傾向があります。
手続きにおける最も大きな違いは、手続き費用・期間の負担が大きい「管財事件(かんざいじけん)」として扱われる可能性が極めて高いという点です。
1回目の破産では、財産がほとんどない場合、手続きが簡易で済む「同時廃止事件」になることが多いですが、2回目では詳細な調査が必要と判断されることが一般的です。
これまでの生活の中で改善が見られているか、資産隠しがないかを破産管財人が徹底的にチェックするため、書類に不備がないよう慎重な準備が求められます。
3-1. 破産管財人が選任される可能性の上昇
2回目の破産申立てでは、ほぼ確実に破産管財人が選任される「管財事件」となります。
破産管財人とは、裁判所の代わりに借金の経緯や財産状況を調査する弁護士のことです。
参照 破産管財人の主な業務
- 財産の徹底調査
預金、保険、車、マイホームなどの不動産、退職金見込額などが詳細に調査され、換価(お金に換えること)できるものは処分し、債権者への配当に回されます。 - 生活状況の監督
破産手続き中の郵便物が管財人に転送されたり、引っ越しや旅行に制限がかかったりします。また、毎月の家計収支表の提出、面談が実施されることがあります。 - 免責調査
「本当に免責させてよいか」を判断するため、管財人との面談が行われます。
裁判所に免責決定に関する意見を提出し、裁判所はその内容をもとに判断します。
管財事件になると、同時廃止事件と比べて手続きが長期化(半年〜1年以上)するだけでなく、後述する予納金などの費用も高額になる可能性があります。
この点は申立前に理解しておく必要があります。
3-2. 事情説明や反省文の提出が必要になるケース
2回目の自己破産では、前回との違いや再度の債務超過に至った経緯を詳細に説明するための資料提出が求められます。
特に重要になるのが「陳述書」や「反省文」です。
これらは、裁判官や破産管財人が「再発を防ぐ意思があるか」を確認するうえで重要な判断材料となります。
また、同じような借金の原因を重ねた傾向が見られる場合には、表向きの言葉による反省だけでなく、具体的な生活再建に向けた行動や今後の改善努力を形にして示す必要があります。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
4. 2回目の自己破産で注意すべき免責不許可事由
2回目の自己破産では、特に免責不許可事由(破産法第252条第1項各号)に該当する行為の有無が厳しくチェックされます。
免責不許可事由とは、裁判所が債務者に重大な落ち度があるとみなし、免責を認めない理由となる項目です。
代表的なものとして、以下の行為が挙げられます。
参照 免責許可事由の一例
- 浪費・ギャンブル
パチンコ、競馬、FX、身の丈に合わない高級品の購入など。 - 詐術を用いた借入
収入を偽って融資を受けるなど。 - 偏頗弁済(へんぱべんさい)
特定の債権者(親族や友人など)だけに優先して返済すること。
債権者への公平性を害する行為として禁止されています。
2回目の申立て時に免責不許可事由がある場合、審査の目は非常に厳しくなります。
4-1. 浪費やギャンブルによる借金への裁量免責の判断
ギャンブルや浪費は免責不許可事由の典型例です。
ただ、その事実だけで直ちに免責が否定されるわけではありません。
その後の行動次第で、裁判所の裁量により免責(裁量免責)が認められる可能性があります。
裁判所や破産管財人は、本人が本気で生活を立て直そうとしているのかを見極めるために、過去の過ちを繰り返さないという明確な姿勢と証拠を求めます。
- 家計簿の提出
1円単位での収支管理、収入内で生活していることを示し、管財人の指導に従う。 - 反省文の提出
反省に至った原因に対する具体的な改善策に取り組んでいること、二度と破産に至ることがないよう誓約する。
4-2. どうしても原因が重複してしまう場合の対処
借金の原因が重複している場合、ご自身だけで判断して諦めるのは早いです。
反省の意と再発防止策を法的に正しく主張することで、免責の余地は残されています。
まずは隠さずに弁護士へ相談しましょう。
5. 2回目の自己破産にかかる費用と手間
2回目の自己破産では前述の通り「管財事件」になる可能性が高く、費用や手間も1回目より増える傾向があります。
参照 破産管財事件の費用相場
- 弁護士費用
手続きが複雑になるため、同時廃止よりも高めに設定されることが一般的です(相場:40万円〜60万円程度)。 - 裁判所への予納金
破産管財人の報酬として、最低でも20万円程度(少額管財の場合)の現金一括納付が必要になるケースが多いです。
裁判所の判断で破産管財事件になると、同時廃止に比べて、提出書類も多く、調査や面談などが増えるため手続き期間(半年〜1年程度)は長くなり、依頼者様の負担も増えます。
手続きにかかる費用の問題に対しては、法テラス(民事法律扶助制度)の利用や、分割払いに対応している弁護士事務所への依頼などにより負担軽減が可能です。
6. 2回目でも免責が下りないときの対処法
万が一、2回目の免責が認められなかった場合でも、人生が終わるわけではありません。他の手続きや即時抗告などの方法が存在します。
免責不許可の決定には理由があります。
その理由を正確に把握し、弁護士と相談の上で次の一手を検討しましょう。
6-1. 即時抗告の可能性と進め方
破産手続きで免責不許可の決定が出された場合、その決定に不服があれば、通知を受けてから1週間以内に「即時抗告(そくじこうこく)」を行うことができます。
これは高等裁判所に再審理を求める手続きです。
ただし、即時抗告が成功するには、原決定(不許可の判断)をくつがえすだけの新たな事実や証拠が必要です。
単なる不満や「困るから認めてほしい」という主観的な主張だけでは結果は変わりません。
弁護士と相談しながら、抗告審でどのように主張を組み立てるかの検討が必要になります。
6-2. 自己破産以外の債務整理を検討する(任意整理・個人再生など)
2回目の自己破産で免責が得られない、あるいは免責の見込みが低い場合は、他の債務整理手段を検討します。
参照 自己破産以外の債務整理方法
- 個人再生(こじんさいせい)
裁判所を通して借金を大幅に(最大で5分の1〜10分の1程度)減額し、原則3年(最長5年)で分割返済する制度です。
自己破産のような「免責不許可事由」がないため、ギャンブルや浪費などが原因でも利用しやすいのが特徴です。
また、住宅ローン特則を利用すればマイホームを残せるメリットもあります。 - 任意整理
裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長を目指します。
借金の総額を大幅に減らすことはできませんが、毎月の負担額を減らすことはできます。
どの手段が自分に最適かは個別の状況(収入、資産、借金額)によって異なります。
結果的に借金返済の負担を最大限減らす方法を模索することが大切です。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。
7. 1回目との違い・よくある疑問Q&A
2回目の自己破産では1回目とは異なる疑問点も多く、審理の厳しさや負担について気になる方も多いでしょう。
よくある疑問をQ&A形式で整理します。
7-1. 1回目と2回目で審理の内容や負担はどう変わる?
Q:1回目は簡単でしたが、2回目もすぐに終わりますか?
A:いいえ、2回目は「簡単」ではありません。
1回目の自己破産(特に同時廃止)は書類審査中心で比較的スムーズに進むことが多いですが、2回目は管財人が選任され、生活状況や資産について厳密な調査が行われます。
面接の回数も増え、家計簿のチェックも厳しくなる可能性が高いです。
7-2. ギャンブルや浪費の借金があるときの注意点
Q:今もギャンブルをしていますが、破産できますか?
A:直ちにやめる必要があります。
申立て直前までギャンブルや浪費を続けていると、「反省していない」とみなされ、免責不許可となる可能性が極めて高くなります。
また、クレジットカードの現金化(商品券購入後に金券ショップで換金など)も厳禁です。
真摯な反省と、今後は同じ道を歩まないという具体的な裏付け(治療実績や家計改善)を提示できるかが、裁判所に再度のチャンスを与えてもらうための鍵となります。
7-3. 専門家への相談の必要性
Q:弁護士に依頼しなくても、2回目の破産はできますか?
A:手続きは可能ですが、裁量免責の可能性を高めるために専門家への相談をおすすめします。
ここまで解説した通り、2回目の自己破産は、1回目に比べて法的・実務的な難易度が飛躍的に上がります。
- 厳格な調査への対応
管財人からの質問に対し、矛盾なく誠実に回答する必要があります。 - 裁量免責の獲得
法律知識に基づき、破産管財人や裁判官を説得するための書面作成が必要になります。 - 費用や裁判書類の準備
高額になりがちな予納金の工面や、破産管財事件特有の複雑な書類作成・準備が必要です。
こうした複雑な手続きを個人で行うには大きな負担があります。
多くの事例や経験を持つ弁護士や司法書士に相談することで、ご自身の事情を客観的に整理し、「どうすれば免責の可能性が高まるか」という具体的なアドバイスを得られます。
手続き後のトラブルを未然に防ぎ、スムーズに免責許可決定を得るためにも、悩み始めた段階で早めに専門家へ相談することをお勧めします。
9. まとめ
2回目の自己破産は厳しい審査を伴いますが、適切な対策と専門家のサポートがあれば、免責獲得の可能性はあります。
『2回目だから』と諦めず、まずは専門家の無料相談を活用して、再スタートへの第一歩を踏み出してください。
最終的に免責が認められれば、借金はゼロになり、借金問題から解放されて新たな生活への一歩を踏み出すチャンスとなります。
2回目の自己破産を検討する際は、一人で抱え込まず、まずは専門家の無料相談などを利用して情報収集と準備を進めるのもひとつの方法です。
古山綜合法律事務所では、借金問題の初回無料相談を実施中です。
自己破産に関する準備から、債権者対応、申し立てまでトータルでサポートいたします。
分割払いのご相談も可能ですので、お一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください(電話・メール・LINE対応)。
借金問題の無料相談を実施中
受付スタッフが弁護士とのご相談日程を調整いたします。